練習文100問
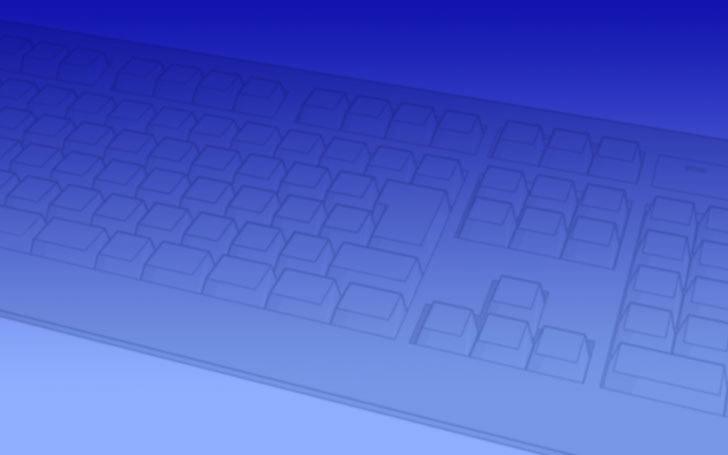
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(にんげんにとってゆたかなしょくじとはなにかをかんがえる。)
人間にとって豊かな食事とは何かを考える。
(べんりなげんだい、きせつをとわずしょくひんをてがるに。)
便利な現代、季節を問わず食品を手軽に。
(ほとんどのかていにれいぞうこがある。ひもちしないものをやすくこうにゅうしほぞんかのう。)
殆どの家庭に冷蔵庫がある。日持ちしない物を安く購入し保存可能。
(しゅしょくもたようなせんたくし。しょくたくはゆたかだがおおくがゆにゅうひん。)
主食も多様な選択肢。食卓は豊かだが多くが輸入品。
(こくないしょうひのしょくりょうのうち、こくさんのわりあいをしめすしょくりょうじきゅうりつ。)
国内消費の食料の内、国産の割合を示す食料自給率。
(かろりーもとでは40%みまん。せんしんくにでさいていすいじゅんだ。)
カロリー基では40%未満。先進国で最低水準だ。
(ゆにゅうにはかいがいとのこうりゅうやゆそうぎじゅつがひつようになる。)
輸入には海外との交流や輸送技術が必要になる。
(むかしはじきゅうりつがたかかった。ゆにゅうまえのしょくたくは?ゆたか?)
昔は自給率が高かった。輸入前の食卓は?豊か?
(せんもんかいわくしょうわ10ねんだいのしょくひんでつくったりょうりはひじょうにゆたか。)
専門家曰く昭和10年代の食品で作った料理は非常に豊か。
(りそうにちかい。とうじはゆそうぎじゅつがとぼしくれいぞうこもみふきゅう。)
理想に近い。当時は輸送技術が乏しく冷蔵庫も未普及。
(じもとでつくられたものやきんかいのさかなをしょくしていた。)
地元で作られた物や近海の魚を食していた。
(にくもしょくたくにのぼりほとんどこくさん。かちくもとくべつなえさをあたえず。)
肉も食卓に上り殆ど国産。家畜も特別な餌を与えず。
(ぼくじょうしゅうへんのくさをたべさせていた。せいようやさいはむずかしかったが。)
牧場周辺の草を食べさせていた。西洋野菜は難しかったが。
(きせつによりげんざいにおとらずせいせんしょくひんがでまわっていた。)
季節により現在に劣らず生鮮食品が出回っていた。
(じこくでさんしゅつされたしょくざいだとおどろく。しょくじはおおきくかわった。)
自国で産出された食材だと驚く。食事は大きく変わった。
(こうどけいざいせいちょうき。ようしょくぶんかでにくやあぶら、たまごのしょうひがかくだい。)
高度経済成長期。洋食文化で肉や油、卵の消費が拡大。
(こむぎでつくられたぱんやめんをこのむひとがふえたそうだ。)
小麦で作られたパンや麺を好む人が増えたそうだ。
(しゅしょくのこめのしょうひはげんしょう。がいしょくやゆにゅうひんのぞうかで。)
主食の米の消費は減少。外食や輸入品の増加で。
(にほんのしょくりょうはかいがいたのみ。ゆにゅうがとまればしょくせいかつは?)
日本の食料は海外頼み。輸入が止まれば食生活は?
(ぶっかじょうしょうにくわえてにはいらぬものもある。かいがいでなにかがおきても。)
物価上昇に加え手に入らぬ物もある。海外で何かが起きても。
など
(せいかつをいじするにはしょくりょうじきゅうりつをたかめるひつようが。)
生活を維持するには食料自給率を高める必要が。
(しゅんのものやじもとさんをえらぶ。べいをしゅしょくにすることがたいせつ。)
旬の物や地元産を選ぶ。米を主食にする事が大切。
(たべのこしをへらすこともじきゅうりつあっぷにつながるこうどうだ。)
食べ残しを減らす事も自給率アップに繋がる行動だ。
(こくさんのものをうまくつかう。めにゅーがならぶしょくたくこそゆたか。)
国産の物を上手く使う。メニューが並ぶ食卓こそ豊か。
(にほんじんはでんとうやむかしながらということばによわい。かんしゅうについて。)
日本人は伝統や昔ながらという言葉に弱い。慣習について。
(おややめうえにしつもんをしたとき、こんきょをせつめいされなくてもなっとく。)
親や目上に質問をした時、根拠を説明されなくても納得。
(ぶっしんついたときからせいかつにあったかんしゅうはむかしから?)
物心ついた時から生活にあった慣習は昔から?
(うつくしいしぜんやしきにめぐまれたにほんにはねんちゅうぎょうじが。)
美しい自然や四季に恵まれた日本には年中行事が。
(おなじようないめーじをもつもののなかにはたんじょうからみじかいものも。)
同じ様なイメージを持つ物の中には誕生から短い物も。
(はつもうではしゃじはふるくからあるが、はじまりは130ねんまえ。)
初詣は社寺は古くからあるが、始まりは130年前。
(ひかくてきさいきんのふうしゅうだ。しょうがつにちかくのじんじゃでてをあわせること。)
比較的最近の風習だ。正月に近くの神社で手を合わせる事。
(にたぎょうじはむかしから。かちょうがかみがまつられているしゃじにとまりこむ。)
似た行事は昔から。家長が神が祭られている社寺に泊り込む。
(ほうさくやかないあんぜんなどをきがんするえほうまいりなどがある。)
豊作や家内安全などを祈願する恵方参りなどがある。
(てがるにじっせんできるようになったのがはつもうで。むかしはきんじょのじんじゃに。)
手軽に実践できるようになったのが初詣。昔は近所の神社に。
(めいじにてつどうがかいぎょう。きがるにりょこうをたのしめるようになり。)
明治に鉄道が開業。気軽に旅行を楽しめるようになり。
(てつどうがいしゃのしゅうきゃくきょうそう。しょうがつのさんぱいきゃくをゆういんするため。)
鉄道会社の集客競争。正月の参拝客を誘引する為。
(もりあがりがぜんこくにひろまりていちゃく。かんしゃをこめておくるせいぼも。)
盛り上がりが全国に広まり定着。感謝を込めて贈る歳暮も。
(しょうがつにそなえたものをしんせきやきんじょにもっていくぎょうじがへんか。)
正月に供えた物を親戚や近所に持って行く行事が変化。
(じょうしやおせわになったひとにおくりものをするようになりぜんこくへ。)
上司やお世話になった人に贈物をするようになり全国へ。
(ねんがじょうは11せいき。ゆうびんせいどがかくりつしはがきがふきゅうしきがるに。)
年賀状は11世紀。郵便制度が確立し葉書が普及し気軽に。
(としだまくじつきはがきはしょうわ。こうあんしたのはおおさかのしたてや。)
年玉くじ付き葉書は昭和。考案したのは大阪の仕立屋。
(せいざはどう?ようしょうきにしょどうをならいさほうのきてんでせいざ。)
正座はどう?幼少期に書道を習い作法の起点で正座。
(れきしをたどるとおもいきものをみにまとったひめもくげもあぐらやたてひざ。)
歴史を辿ると重い着物を身に纏った姫も公家も胡坐や立て膝。
(すわりかたのひとつにせいざはあるがしんぶつをおがむときやみぶんのたかいひとのまえ。)
座り方の一つに正座はあるが神仏を拝む時や身分の高い人の前。
(あしがしびれたちあがるのにじかんがかかるせいざはたたかうぶしにむり。)
足が痺れ立ち上がるのに時間がかかる正座は戦う武士に無理。
(かたくるしいばしょでのすわりかたとなったのはえどじだいしょきいこうだとはんめい。)
堅苦しい場所での座り方となったのは江戸時代初期以降だと判明。
(よのなかにはひとつのといについてふかくついきゅうするがくしゃもそんざいする。)
世の中には一つの問いについて深く追求する学者も存在する。
(くもをせんもんとするけんきゅうしゃはみりょくをかたりつくせないという。)
クモを専門とする研究者は魅力を語り尽くせないと言う。
(おおくのひとにとってうれしくないいきもの?こうかんどはひくい?)
多くの人にとって嬉しくない生き物?好感度は低い?
(くものいとのしんぴにちゃくもく。みためはおなじだが7しゅるいもそんざいする。)
クモの糸の神秘に着目。見た目は同じだが7種類も存在する。
(ふとさやせいしつのことなるものをたくみにつかいわける。)
太さや性質の異なる物を巧みに使い分ける。
(すはたていととよこいとからできている。それぞれせいしつがことなる。)
巣は縦糸と横糸から出来ている。それぞれ性質が異なる。
(ぜんしゃはきょうどつよくさいしょにりんかく。こうしゃはねんえきのつぶがついている。)
前者は強度強く最初に輪郭。後者は粘液の粒が付いている。
(あしやはねがふれるとみうごきがとれなくなるしくみ。)
脚や羽が触れると身動きが取れなくなる仕組み。
(ほかくじはまたちがったいとをとばしつつみこむことができる。)
捕獲時はまた違った糸を飛ばし包み込む事ができる。
(こうてついじょうのきょうど。ひこうきをきゃっちできるかのうせいも。)
鋼鉄以上の強度。飛行機をキャッチできる可能性も。
(かるくてないろんいじょうのじゅうなんせい。しんしゅくじざいでたいねつせいももつ。)
軽くてナイロン以上の柔軟性。伸縮自在で耐熱性も持つ。
(はなしをきいたときかこにみたえいがをおもいだした。)
話を聞いた時過去に見た映画を思い出した。
(けんきゅうしつにいったしょうねんがくもおとこに。いとをとばしとびうつる。)
研究室に行った少年が蜘蛛男に。糸を飛ばし飛び移る。
(とくちょうをしるとげんじつてき?りさいくるもさすてなぶるなしゃかい。)
特長を知ると現実的?リサイクルもサステナブルな社会。
(くもはえこをじっせん。すをはりかえるさいいとをかいしゅうしつかう。)
蜘蛛はエコを実践。巣を張り替える際糸を回収し使う。
(しがいせんにつよいとくちょうも。あたらしいせんいとしてりようできる?)
紫外線に強い特長も。新しい繊維として利用できる?
(ながねんゆめのそざい。いでんしそうさでせいぞうにせいこうしたきぎょうが。)
長年夢の素材。遺伝子操作で製造に成功した企業が。
(かだいはあるがはばひろいぶんやへのおうようがきたいされている。)
課題はあるが幅広い分野への応用が期待されている。
(いとはおくふかい。まなべることもおおい。けんこうへのいしきがたかまる。)
糸は奥深い。学べる事も多い。健康への意識が高まる。
(そうちょうやゆうがたにはしるひと。すとれっちやさんぽをするひとも。)
早朝や夕方に走る人。ストレッチや散歩をする人も。
(あるくことでないぞうしぼうのねんしょうこうかやせいかつしゅうかんびょうをよぼうする。)
歩く事で内臓脂肪の燃焼効果や生活習慣病を予防する。
(とくべつなどうぐはいらずてがる。けんこうといえばせいしんてきなめんもたいせつ。)
特別な道具は要らず手軽。健康と言えば精神的な面も大切。
(にほんにはさんぽやさんさく、ゆうほといったぶんかがそんざいしている。)
日本には散歩や散策、遊歩といった文化が存在している。
(にちじょうをわすれしぜんにこころをときはなちしきおりおりのへんかをたのしむ。)
日常を忘れ自然に心を解き放ち四季折々の変化を楽しむ。
(しぜんへのりかいをふかめるとさんぽへのいしきがたかまりたのしめる。)
自然への理解を深めると散歩への意識が高まり楽しめる。
(すこしあるけばさまざまなしょくぶつにであえる。なまえをしらべちしきをひろげる。)
少し歩けば様々な植物に出会える。名前を調べ知識を広げる。
(すまほのあぷりも。とかいはしぜんがすくない?ちゅういするとたように。)
スマホのアプリも。都会は自然が少ない?注意すると多様に。
(がいろじゅはしゅるいがおおい。しきによってさまざまなすがたをみせてくれる。)
街路樹は種類が多い。四季によって様々な姿を見せてくれる。
(どうろやいしのあいだからかおをだしているくさばなにかんしんさせられる。)
道路や石の間から顔を出している草花に感心させられる。
(しょくぶつだけでなくわれわれをとりまくことがらをしるのもおもしろいことだ。)
植物だけでなく我々を取り巻く事柄を知るのも面白い事だ。
(きしょうにかんすることばはきせつによっておもむきぶかいものがある。)
気象に関する言葉は季節によって趣深いものがある。
(あめのじょうけいをあらわすことばもおおい。おちこみがちだがしてんをかえると。)
雨の情景を表す言葉も多い。落ち込みがちだが視点を変えると。
(いつもとちがうたのしみも。じいんをめぐってれきしにふれてみよう。)
いつもと違う楽しみも。寺院を巡って歴史に触れてみよう。
(ふだんはかよわないしょうみちをあるくのもよい。そうちょうのさんぽもおすすめ。)
普段は通わない小道を歩くのも良い。早朝の散歩もお勧め。
(じかんがゆるやかにかんじられるからだ。げんそうてきなせかい。)
時間が緩やかに感じられるからだ。幻想的な世界。
(くさきがゆれるおと、むしやとりのこえがせんめいにきこえてここちよい。)
草木が揺れる音、虫や鳥の声が鮮明に聞こえて心地良い。
(せいしんめんをあんていさせじょぎんぐでけんこうなからだづくりを。)
精神面を安定させジョギングで健康な体づくりを。
(こんくりーとはさまざまなばしょでしよう。どうろやはし、びるなど。)
コンクリートは様々な場所で使用。道路や橋、ビルなど。
(せめんとにみずやすななどをまぜてつくられる。あんかでてがるに。)
セメントに水や砂等を混ぜて造られる。安価で手軽に。
(いろいろなかたちがかのう。じゅみょうもながいのでさまざまなばしょでしよう。)
色々な形が可能。寿命も長いので様々な場所で使用。
(みずについでおおくつかわれている。せめんとのしゅげんりょうはせっかいせき。)
水に次いで多く使われている。セメントの主原料は石灰石。
(すななどをくっつけるのりのようなやくわり。みずがはいるとねんどのように。)
砂等をくっ付ける糊の様な役割。水が入ると粘土の様に。
(じかんがたつとかたまる。ようとによってはいごうをかえている。)
時間が経つと固まる。用途によって配合を変えている。
(れきしはふるくさいこのものはいせきから。すうせんねんまえのしんせっきじだい。)
歴史は古く最古の物は遺跡から。数千年前の新石器時代。
(こだいろーまでしよう。ちちゅうかいしゅうへんでみられる。よいせめんとは。)
古代ローマで使用。地中海周辺で見られる。良いセメントは。
(えいこくでたんじょう。すうじゅうねんごにこくさんか。さまざまなくにでしよう。きょうどぶそく。)
英国で誕生。数十年後に国産化。様々な国で使用。強度不足。
(てっきんこんくりーとはこうそうびるやしゅうごうじゅうたくとうのおおがたけんちくでしよう。)
鉄筋コンクリートは高層ビルや集合住宅等の大型建築で使用。
(こんくりーとはせんようのこうじょうでつくられる。ざいりょうをけいりょうしねりまぜ。)
コンクリートは専用の工場で造られる。材料を計量し練り混ぜ。
(くるまではこぶ。げんばまではかいてんするどらむがついたくるまではこぶ。)
車で運ぶ。現場迄は回転するドラムが付いた車で運ぶ。
(げんばでけんさをじっし。かたわくのなかにながしこむ。しんどうをあたえならす。)
現場で検査を実施。型枠の中に流し込む。振動を与え均す。
(ゆっくりかたまりはじめ1かげつほどたつとじゅうぶんなきょうどになる。)
ゆっくり固まり始め1か月程経つと十分な強度になる。
(じゅみょうはじょうけんがよければながい。ていきてきにしゅうふくがひつよう。)
寿命は条件が良ければ長い。定期的に修復が必要。
(たがくのひようがひつよう。せいぞうかていではおおくのおんしつこうかがす。)
多額の費用が必要。製造過程では多くの温室効果ガス。
(びせいぶつのはたらきでしゅうふくしたりたいきゅうせいのたかいものをかいはつ。)
微生物の働きで修復したり耐久性の高い物を開発。




