会社法 法人格否認の法理
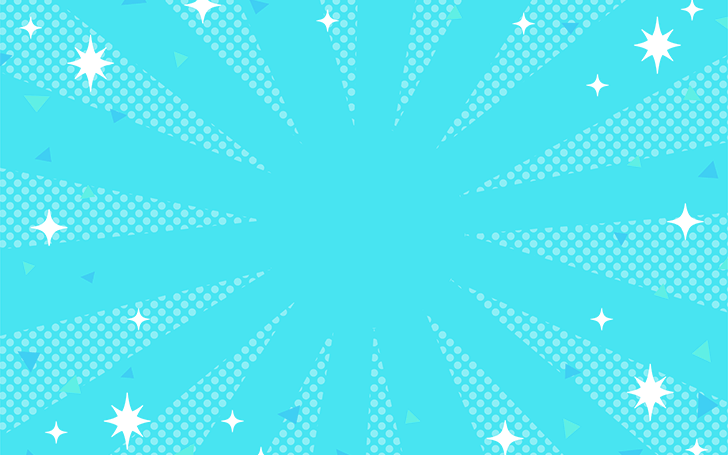
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスタムーア | 6094 | A++ | 6.3 | 96.1% | 329.8 | 2095 | 85 | 37 | 2025/12/26 |
| 2 | KKKKK | 4652 | C++ | 5.0 | 93.4% | 425.4 | 2129 | 150 | 37 | 2025/12/06 |
| 3 | @k | 4610 | C++ | 4.9 | 93.6% | 429.7 | 2124 | 143 | 37 | 2025/12/21 |
| 4 | Andrew | 4201 | C | 4.4 | 94.3% | 475.3 | 2123 | 126 | 37 | 2025/12/23 |
| 5 | arieru | 4094 | C | 4.3 | 93.5% | 486.3 | 2138 | 147 | 37 | 2025/12/25 |
関連タイピング
-
タイピング練習用文章(短め)
プレイ回数4.8万 かな180秒 -
何秒で全部打てるか挑戦してみよう!
プレイ回数436万 短文かな298打 -
ビジネスメールでよく使われる文章です!
プレイ回数176万 長文かな60秒 -
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数93万 長文300秒 -
ピラミッドに関する雑学の長文です。
プレイ回数2.3万 長文1319打 -
主人公ケイトによる物語です
プレイ回数3.5万 長文かな1417打 -
【打鍵/秒8.0〜】高速連打!!!!
プレイ回数5705 長文2400打
問題文
(1ほうじんかくひにんのほうりのていぎ)
1法人格否認の法理の定義
(ほうじんかくたるかいしゃのけいしきてきどくりつせいをつらぬくとせいぎ・こうへいにはんするけっかとなるばあいに)
法人格たる会社の形式的独立性を貫くと正義・公平に反する結果となる場合に、
(とくていのじあんにかぎってかいしゃのどくりつせいをひていし、)
特定の事案に限って会社の独立性を否定し、
(かいしゃとそのしゃいんやほかのかいしゃをどういつしするほうりである。)
会社とその社員やほかの会社を同一視する法理である。
(かいしゃとしゃいんやほかのかいしゃをどういつしし、どちらにたいしてもせいきゅうをかのうにするてんに)
会社と社員やほかの会社を同一視し、どちらに対しても請求を可能にする点に
(そのいぎがある。)
その意義がある。
(2ほうじんかくひにんのほうりのこうひ)
2法人格否認の法理の肯否
(もっとも、かかるほうりがみとめられるか、めいぶんなくもんだいとなる。)
もっとも、かかる法理が認められるか、明文無く問題となる。
(かいしゃにほうじんかくがふよされるのは、かいしゃがしゃかいてきにそんざいするだんたいであり、)
会社に法人格が付与されるのは、会社が社会的に存在する団体であり、
(そうすることがこくみんけいざいじょうゆうようだからである。)
そうすることが国民経済上有用だからである。
(そうだとすれば、ほうじんとしてじったいがないようなばあい(けいがいか)や)
そうだとすれば、法人として実態がないような場合(形骸化)や
(ほうじんかくがらんようされているばあいには、ほうじんかくをひていすることがかのうである。)
法人格が濫用されている場合には、法人格を否定することが可能である。
((みんぽう1じょう3こう)。)
(民法1条3項)。
(3ようけん ほうてきこんきょがいっぱんきていであるいじょうてきようはんいはげんていされなければならない。)
3要件 法的根拠が一般規定である以上適用範囲は限定されなければならない。
((1)けいがいかじれいのばあい)
(1)形骸化事例の場合
(ほうじんとはいうものの、じっしつはしゃいんのこじんきぎょうやおやがいしゃのいちえいぎょうぶもんにすぎない)
法人とはいうものの、実質は社員の個人企業や親会社の一営業部門にすぎない
(ようなばあいである。)
ような場合である。
(たとえば、ぜいきんたいさくでかいしゃをせつりつしたようなばあいである。)
例えば、税金対策で会社を設立したような場合である。
(このばあいには、しゃいんとかいしゃにじっしつてき・けいざいてきないったいせいがみとめられるかいなかが)
この場合には、社員と会社に実質的・経済的な一体性が認められるか否かが
(じゅうようとなる。)
重要となる。
(そこで、1ぎょうむかつどうのはんぷくけいぞく、)
そこで、1業務活動の反復継続、
(2かいしゃとしゃいんのぎむ・ざいさんのぜんぱんてき・けいざいてきこんどう、)
2会社と社員の義務・財産の全般的・経済的混同、
(3めいかくなちょうぼきさい・かいけいくぶんのけつじょ、)
3明確な帳簿記載・会計区分の欠如、
(4かぶぬしそうかい・とりしまりやくかいのふかいさいなどの、きょうこうそしききていのむしなど)
4株主総会・取締役会の不開催等の、強行組織規定の無視等
(のしょじじょうをそうごうてきにこうりょして、じょうきいったいせいのうむをはんだんすべきである。)
の諸事情を総合的に考慮して、上記一体性の有無を判断すべきである。
((2)らんようじれいのばあい)
(2)濫用事例の場合
(かいしゃのはいごにあってしはいするものが、いほうまたはふとうなもくてきのために)
会社の背後にあって支配する者が、違法または不当な目的のために
(かいしゃのほうじんかくをりようするばあいである。)
会社の法人格を利用する場合である。
(たとえば、aにたいしてたがくのしゃくざいをおうbが、きょうせいしっこうをさけるため)
例えば、Aに対して多額の借財を負うBが、強制執行を避けるため
(ぜんざいさんをしゅっししてかぶしきがいしゃcをせつりつしたようなばあいがあげられる。)
全財産を出資して株式会社cを設立したような場合があげられる。
(このばあいには、はいごしゃにいほうふとうなもくてきがあるかがじゅうようとなるから、)
この場合には、背後者に違法不当な目的があるかが重要となるから、
(1はいごしゃがかいしゃをじっしつてきにしはいし、りようしているじじつかんけい(しはいのようけん)にくわえ)
1背後者が会社を実質的に支配し、利用している事実関係(支配の要件)に加え
(2いほうなもくてきというしゅかんてきようそ(もくてきのようけん)もひつようとなるとかいする。)
2違法な目的という主観的要素(目的の要件)も必要となると解する。
(ぐたいてきには、しんきゅうがいしゃのしはいしゃ・やくいん・じぎょうないよう・とりひきあいてのどういつせい・)
具体的には、新旧会社の支配者・役員・事業内容・取引相手の同一性・
(じぎょうようしさんのりゅうよう、じぎょうやしさんのじょうとたいかのがくやしはらいほうほう、)
事業用資産の流用、事業や資産の譲渡対価の額や支払い方法、
(しんがいしゃせつりつについてのさいけんしゃとのこうしょうのうむ、しんがいしゃせつりつのもくてき)
新会社設立についての債権者との交渉の有無、新会社設立の目的
(などをこうりょすることになる。)
などを考慮することになる。








