気象予報士
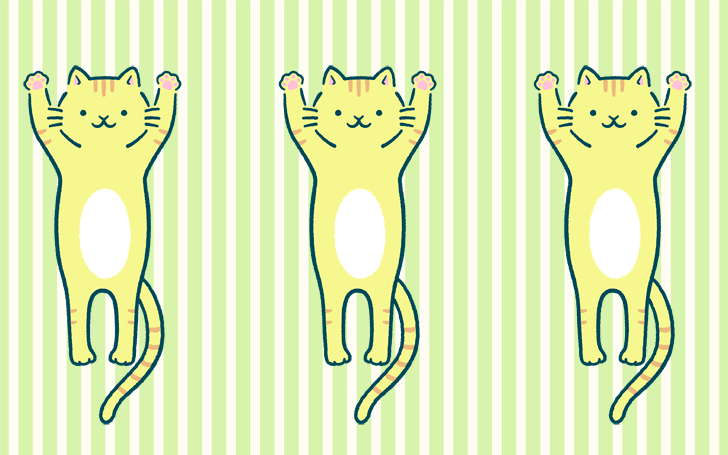
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぽんこつラーメン | 5726 | A | 5.9 | 96.9% | 113.5 | 671 | 21 | 10 | 2025/08/21 |
問題文
(かんそうくうきのたいきそせいはちっそ、さんそ、あるごんで99.9%をしめている)
乾燥空気の大気組成は窒素、酸素、アルゴンで99.9%を占めている
(すいじょうきのりょうはばしょやじかんでおおきくへんかする)
水蒸気の量は場所や時間で大きく変化する
(すいじょうきとにさんかたんそはおんしつこうかをもち、ちひょうめんふきんのきおんをたかめている)
水蒸気と二酸化炭素は温室効果を持ち、地表面付近の気温を高めている
(きんせいとかせいのたいきのしゅせいぶんはにさんかたんそであり、ちきゅうたいきのそせいとはことなる)
金星と火星の大気の主成分は二酸化炭素であり、地球大気の組成とは異なる
(げんざいのちきゅうたいきのみなもとはだつがすによってちちゅうからでてきたきたいである)
現在の地球大気の源は脱ガスによって地中から出てきた気体である
(ちきゅうにうみができたことがげんざいのたいきそせいになったもっともおおきなよういんである)
地球に海ができたことが現在の大気組成になった最も大きな要因である
(さんそはながいきかんにわたってしょくぶつがつくりだした)
酸素は長い期間にわたって植物が作り出した
(たいきには、ちひょうからたいりゅうけん、せいそうけん、ちゅうかんけん、ねつけんというたいきそうがある)
大気には、地表から対流圏、成層圏、中間圏、熱圏という大気層がある
(たいりゅうけんでは1kmじょうしょうするときおんがへいきんでやく6.5どさがる)
対流圏では1㎞上昇すると気温が平均で約6.5℃下がる
(たいりゅうけんはたいようほうしゃによってあたためられたちひょうからねつえねるぎーをえている)
対流圏は太陽放射によって暖められた地表から熱エネルギーを得ている
(たいりゅうけんのたいきのおんどはこうどとともにていかしている)
対流圏の大気の温度は高度とともに低下している
(せいそうけんではおぞん、ねつけんではちっそさんそぶんしがたいようからのしがいせんをきゅうしゅうしている)
成層圏ではオゾン、熱圏では窒素・酸素分子が太陽からの紫外線を吸収している
(せいそうけんではこうどがますときおんがあがる)
成層圏では高度が増すと気温が上がる
(こうどやく80kmまでたいきそせいはいっていである)
高度約80㎞まで大気組成は一定である
(こうどやく5.5kmできあつはちひょうめんの1/2となり、せいそうけんじょうたんで1hpaとなる)
高度約5.5㎞で気圧は地表面の1/2となり、成層圏上端で1hPaとなる
(たいりゅうけんのこうどはせきどうふきんでたかくりょうたんでひくい。なつにたかくふゆにひくい。)
対流圏の高度は赤道付近で高く両端で低い。夏に高く冬に低い。
(たいりゅうけんとちゅうかんけんではこうどとともにきおんがさがる。)
対流圏と中間圏では高度とともに気温が下がる。
(せいそうけんとねつけんではこうどとともにきおんがあがる)
成層圏と熱圏では高度とともに気温が上がる
(おぞんそうはせいそうけんないのこうどやく25kmをちゅうしんにぶんぷする)
オゾン層は成層圏内の高度約25kmを中心に分布する
(せいそうけんのきおんはじょうたんのこうどやく50kmできょくだいとなる)
成層圏の気温は上端の高度約50kmで極大となる
(じょうたいほうていしきはきあつ、みつど、おんどのあいだのかんけいをあらわしている)
状態方程式は気圧、密度、温度の間の関係を表している
(かんそうくうきはすいじょうきをのぞいたくうきである)
乾燥空気は水蒸気を除いた空気である
(しつじゅんくうきはげんじつのくうきとおなじで、かんそうくうきとすいじょうきのこんごうきたいである)
湿潤空気は現実の空気と同じで、乾燥空気と水蒸気の混合気体である
(たいきはくうきかいのおもさとそのじょうげのきあつさがつりあったせいりきがくへいこうのじょうたいにある)
大気は空気塊の重さとその上下の気圧差が釣り合った静力学平行の状態にある
(きあつはたかさとともにしすうかんすうてきにげんしょうする)
気圧は高さとともに指数関数的に減少する
(じょうげのきあつさがおなじきそうはかんきよりだんきのほうがあつい)
上下の気圧差が同じ気層は寒気より暖気の方が厚い
(みずはおんどによってこたい、えきたい、きたいにそうへんかする)
水は温度によって固体、液体、気体に相変化する
(そうへんかするときはせんねつのでいりがある)
相変化するときは潜熱の出入りがある
(ほうわとはくうきちゅうにそのおんどでふくむことのできるさいだいりょうのすいじょうきをふくんでいるじょうたい)
飽和とは空気中にその温度で含むことのできる最大量の水蒸気を含んでいる状態
(ほうわすいじょうきあつはおんどとともにしすうかんすうてきにぞうかする)
飽和水蒸気圧は温度とともに指数関数的に増加する
(しつじゅんくうきのきあつは、かんそうくうきのきあつとすいじょうきのぶんあつのわである)
湿潤空気の気圧は、乾燥空気の気圧と水蒸気の分圧の和である
(こんごうひは、しつじゅんくうきちゅうのすいじょうきのしつりょうとかんそうくうきのしつりょうのひである)
混合比は、湿潤空気中の水蒸気の質量と乾燥空気の質量の比である
(ひしつは、しつじゅんくうきちゅうのすいじょうきのしつりょうとしつじゅんくうきのしつりょうのひである)
比湿は、湿潤空気中の水蒸気の質量と湿潤空気の質量の比である
(そうたいしつどは、ほうわすいじょうきあつ(みつど)にたいするすいじょうきあつ(みつど)のひである)
相対湿度は、飽和水蒸気圧(密度)に対する水蒸気圧(密度)の比である
(ろてんおんどはくうきをひやしていきすいじょうきでほうわしてつゆがはっせいするときのきおんである)
露点温度は空気を冷やしていき水蒸気で飽和して露が発生するときの気温である
(しっすうはきおんとろてんおんどのさである)
湿数は気温と露点温度の差である
(かりおんどは、しつじゅんくうきとおなじきあつとみつどをもつかんそうくうきのおんどである)
仮温度は、湿潤空気と同じ気圧と密度を持つ乾燥空気の温度である
(ひしつをs、きおんをtとすると、かりおんどtvは=t(1+0.61s)とあらわせる)
比湿をs、気温をtとすると、仮温度tvは=t(1+0.61s)と表せる
(ねつりきがくだい1ほうそくからくうきかいにでいりするねつりょうときあつおよびきおんのかんけいがわかる)
熱力学第一法則から空気塊に出入りする熱量と気圧及び気温の関係が分かる
(みほうわくうきかいがだんねつてきにじょうしょうするときのきおんげんりつをかんそうだんねつげんりつという)
未飽和空気塊が断熱的に上昇するときの気温減率を乾燥断熱減率という
(みほうわくうきかいがほうわしているばあいのきおんげんりつをしつじゅんだんねつげんりつという)
未飽和空気塊が飽和している場合の気温減率を湿潤断熱減率という
(おんいはかんそうくうきかいを1000hpaのたかさまでだんねついどうさせたおんどをいう)
温位は乾燥空気塊を1000hPaの高さまで断熱移動させた温度をいう
(そうとうおんいはくうきかいちゅうのすいじょうきのぎょうけつによるせんねつまでかんがえたおんいである)
相当温位は空気塊中の水蒸気の凝結による潜熱まで考えた温位である
(だんねつじょうしょうしたくうきかいのきおんがしゅういよりつめたければあんていあたたかければふあんていである)
断熱上昇した空気塊の気温が周囲より冷たければ安定暖かければ不安定である
(こうどとともにきおんがたかくなるそうをぎゃくてんそうといい、ひじょうにあんていなそうである)
高度とともに気温が高くなる層を逆転層といい、非常に安定な層である
(ぎゃくてんそうはせっちぎゃくてんそう、いりゅうぎゃくてんそうがある)
逆転層は接地逆転層、移流逆転層がある
(くもができるにはえーろぞるとかほうわじょうたいがひつようである)
雲ができるにはエーロゾルと過飽和状態が必要である
(いっぱんに、えーろぞるのかずはりくじょうでおおく、かいじょうでよりすくない)
一般に、エーロゾルの数は陸上で多く、海上でより少ない
(ぎょうけつによるくもつぶのせいちょうそくどは、かほうわどにひれいし、ちょっけいにはんぴれいする)
凝結による雲粒の成長速度は、過飽和度に比例し、直径に反比例する
(すいてきのらっかそくどはそのおおきさにひれいする)
水滴の落下速度はその大きさに比例する
(うんちゅうが0どいじょうのばあいは、へいごうかていでくもつぶがせいちょうし、おんうになる)
雲中が0℃以上の場合は、併合過程で雲粒が成長し、温雨になる
(おなじおんどでもかれいきゃくすいとこおりのほうわすいじょうきあつにはさがあり、こおりのほうがひくい)
同じ温度でも可冷却水と氷の飽和水蒸気圧には差があり、氷の方が低い
(-15どていどですいてきがこおるには、ひょうしょうかくとなるえーろぞるがひつようである)
-15℃程度で水滴が凍るには、氷晶核となるエーロゾルが必要である
(ひょうしょうがかれいきゃくすいてきからじょうはつするすいじょうきをとりこんでせいちょうし、つめたいあめになる)
氷晶が可冷却水滴から蒸発する水蒸気を取り込んで成長し、冷たい雨になる
(ちいさなすいてきのしゅうたんそくどは、はんけいの2じょうにひれいする)
小さな水滴の終端速度は、半径の2乗に比例する
(はんけい1mmていどいじょうのうてきのしゅうたんそくどは、はんけいのへいほうこんにひれいする)
半径1㎜程度以上の雨滴の終端速度は、半径の平方根に比例する
(くもには10しゅるいあり、じょうそううん、ちゅうそううん、かそううん、たいりゅううんにたいべつできる)
雲には10種類あり、上層雲、中層雲、下層雲、対流雲に大別できる
(きりには、ほうしゃぎり、いりゅうぎり、じょうききり、かっしょうぎり、ぜんせんきりの5しゅるいがある)
霧には、放射霧、移流霧、蒸気霧、滑昇霧、前線霧の5種類がある
(えねるぎーのきゅうしゅうこうりつとほうしゃこうりつが100%のりそうてきなぶっしつをこくたいという)
エネルギーの吸収効率と放射効率が100%の理想的な物質を黒体という
(たんいめんせきあたり1びょうかんにほうしゅつされるぜんえねるぎーはこくたいのぜったいおんどの4じょうにひれい)
単位面積当たり1秒間に放出される全エネルギーは黒体の絶対温度の4乗に比例
(たいようほうしゃをたんはほうしゃといい、ちきゅうほうしゃをちょうはほうしゃまたはせきがいほうしゃという)
太陽放射を短波放射といい、地球放射を長波放射または赤外放射という
(ちきゅうのへいきんきどうきょりにとうたつしたときのえねるぎーりょうをたいようていすうという)
地球の平均軌道距離に到達したときのエネルギー量を太陽定数という
(かしこういきのえねるぎーがたいようほうしゃのやくはんぶんをしめている)
可視光域のエネルギーが太陽放射の約半分を占めている
(しょうごのたいようこうどかくをなんちゅうこうどかくといいげしでさいだい、とうじでさいしょうとなる)
正午の太陽高度角を南中高度角といい夏至で最大、冬至で最少となる
(たいようほうしゃはくうきぶんしによってさんらんされる)
太陽放射は空気分子によって散乱される
(たいきのまどは、せきがいほうしゃをほとんどきゅうしゅうしないはちょうたいである)
大気の窓は、赤外放射をほとんど吸収しない波長帯である
(あるべどはしろければおおきくくろければちいさい)
アルベドは白ければ大きく黒ければ小さい
(ぜんてんにっしゃりょうは、ちょくたつにっしゃりょうとさんらんにっしゃりょうのわである)
全天日射量は、直達日射量と散乱日射量の和である
(にゅうしゃするほうしゃえねるぎーとでていくほうしゃえねるぎーはほうしゃへいこうのじょうたいにある)
入射する放射エネルギーと出ていく放射エネルギーは放射平行の状態にある
(ちひょうめんとたいきではほうしゃえねるぎーのしゅうしがきんこうしていない)
地表面と大気では放射エネルギーの収支が均衡していない
(ちひょうめんからたいきへのせんねつとけんねつのいどうによっておぎなわれている)
地表面から大気への潜熱と顕熱の移動によって補われている
(いどべつのほうしゃしゅうしのふきんこうがたいきやかいようのうんどうをもたらしている)
緯度別の放射収支の不均衡が大気や海洋の運動をもたらしている
(ちきゅうたいきのおんどはおんしつこうかによってたもたれている)
地球大気の温度は温室効果によって保たれている
(きあつけいどりょくとは、きあつのたかいほうからひくいほうにむかってとうあつせんとちょっかくにはたらくちから)
気圧傾度力とは、気圧の高い方から低い方に向かって等圧線と直角に働く力
(こりおりちからはきたはんきゅうではうんどうのほうこうにたいしてちょっかくみぎむきにはたらく)
コリオリ力は北半球では運動の方向に対して直角右向きに働く
(こりおりりょくのおおきさはふうそくとsinしーたにひれいする)
コリオリ力の大きさは風速とsinθに比例する
(くうかんすけーるのおおきなげんしょうはじかんすけーるもながい)
空間スケールの大きな現象は時間スケールも長い
(きしょうげんしょうはくうかんすけーるのおおきさによってぶんるいされる)
気象現象は空間スケールの大きさによって分類される
(ちひょうめんのえいきょうをうけるたいきそうのことをたいききょうかいそうという)
地表面の影響を受ける大気層のことを大気境界層という
(たいききょうかいそうはせっちそうとたいりゅうこんごうそう(えくまんそう)にわけられる)
大気境界層は接地層と対流混合層(エクマン層)に分けられる
(ちひょうめんのえいきょうをうけないたいきをじゆうたいきという)
地表面の影響を受けない大気を自由大気という
(たいききょうかいそうないのくうきはさまざまなきしょうようそがとくちょうてきなえんちょくぶんぷをしている)
大気境界層内の空気はさまざまな気象要素が特徴的な鉛直分布をしている
(たいききょうかいそうにはさまざまなうずがあり、みだれたうずをらんうず、みだれたながれをらんりゅうという)
大気境界層にはさまざまな渦があり、乱れた渦を乱渦、乱れた流れを乱流という
(いどべつのほうしゃによるねつのふきんこうはたいきとかいようのねつせんねつゆそうによってかんわされる)
緯度別の放射による熱の不均衡は大気と海洋の熱・潜熱輸送によって緩和される
(たいきのしごめんじゅんかんはちょくせつじゅんかんのはどれーきょくじゅんかん、かんせつじゅんかんのふぇれる)
大気の子午面循環は直接循環のハドレー・極循環、間接循環のフェレル
(あねったいこうあつたいでじょうはつしたすいじょうきはねったいしゅうそくたいやちゅういどたいでのこうすいとなる)
亜熱帯高圧帯で蒸発した水蒸気は熱帯収束帯や中緯度帯での降水となる
(たいきのなんぼくじゅんかんでねつがゆそうされすいじょうきのなんぼくじゅんかんですいじょうきがゆそうされる)
大気の南北循環で熱が輸送され水蒸気の南北循環で水蒸気が輸送される
(なかこういどでは、たいきのとうざいほうこうのじゅんかんとじぇっときりゅうのそんざいでねつがゆそうされる)
中・高緯度では、大気の東西方向の循環とジェット気流の存在で熱が輸送される
(じぇっときりゅうには、あねったいじぇっときりゅうとかんたいぜんせんじぇっときりゅうとがある)
ジェット気流には、亜熱帯ジェット気流と寒帯前線ジェット気流とがある
(へんせいふうはどうにおいてこういどがわにとつをきあつのおねといいていいどがわにとつをきあつのたに)
偏西風波動において高緯度側に凸を気圧の尾根といい低緯度側に凸を気圧の谷
(ちじょうのおんたいていきあつは、じょうそうのきあつのたににたいおうしたけいあつふあんていはである)
地上の温帯低気圧は、上層の気圧の谷に対応した傾圧不安定波である
(にっぽんのきだんはかんれいなおほーつくきだんしべりあきだん、おんだんなおがさわらようじきだん)
日本の気団は寒冷なオホーツク気団・シベリア気団、温暖な小笠原・揚子気団
(ぜんせんはかんきだんとだんきだんのきょうかいであり、かんれいおんだんへいそくていたいがある)
前線は寒気団と暖気団の境界であり、寒冷・温暖・閉塞・停滞がある
(おんたいていきあつはかそうでとうおんせんがしゅうちゅうしてえんちょくしあーがりんかいてんをこえるとはっせい)
温帯低気圧は下層で等温線が集中して鉛直シアーが臨界点を超えると発生
(はったつちゅうのちじょうていきあつは、ちじょうとじょうそうのきあつのたにをむすぶじくがにしにかたむいている)
発達中の地上低気圧は、地上と上層の気圧の谷を結ぶ軸が西に傾いている
(ていきあつはだんきがじょうしょうかんきがこうかしていちえねるぎーがうんどうえねるぎーにへんかんされ)
低気圧は暖気が上昇寒気が降下して位置エネルギーが運動エネルギーに変換され
(べなーるがたたいりゅうは、おーぷんせるがたのくもやくろーずどせるがたのくもをけいせいする)
ベナール型対流は、オープンセル型の雲やクローズドセル型の雲を形成する
(せきらんうんのじゅみょうは30~60ふんていどで、はったつきせいじゅくきすいじゃくきにわけられる)
積乱雲の寿命は30~60分程度で、発達期・成熟期・衰弱期に分けられる
(せいじゅくきのせきらんうんのきょうれつなかこうりゅうとれいきがいしゅつりゅうをだうんばーすとという)
成熟期の積乱雲の強烈な下降流と冷気外出流をダウンバーストという
(かみなりは、ねつらい、かいらい、からい、ねつかいらいにぶんるいされる)
雷は、熱雷、界雷、渦雷、熱界雷に分類される

