【第124回】検定試験 1級
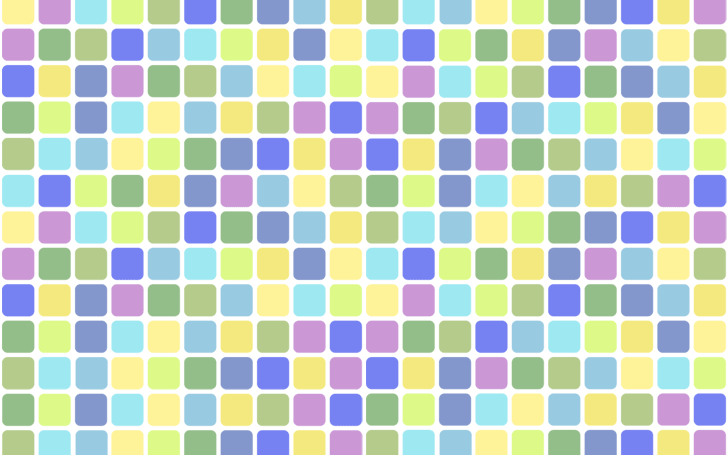
日本語ワープロ検定試験
第124回(令和2年10月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sss | 6324 | S | 6.6 | 95.1% | 316.4 | 2109 | 108 | 41 | 2026/02/06 |
| 2 | PLMKJNB4 | 6035 | A++ | 6.7 | 90.8% | 313.8 | 2106 | 212 | 41 | 2026/01/30 |
| 3 | なり | 5564 | A | 5.8 | 95.0% | 359.6 | 2110 | 109 | 41 | 2026/02/06 |
関連タイピング
-
Mrs.GREEN APPLEの恋と吟です!
プレイ回数1224 歌詞860打 -
プレイ回数1099 歌詞886打
-
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
ミセスぅーーーーー!!!!
プレイ回数283 歌詞かな114打 -
「ロクデナシ」さんの「ただ声一つ」です!!
プレイ回数360 歌詞120秒 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(わたしは、なにかきおくにとどめておきたいしーんにちょくめんしたとき、しゃしんをとる。)
わたしは、何か記憶にとどめておきたいシーンに直面した時、写真を撮る。
(さいきんではけいたいでんわにそのきのうがついているため、きがるにできてとてもべんりだ。)
最近では携帯電話にその機能が付いているため、気軽にできてとても便利だ。
(すこしまえのじだいにおいては、おもいかめらをじさんするひつようがあり、)
少し前の時代においては、重いカメラを持参する必要があり、
(とりだすのもひとくろうだった。)
取り出すのも一苦労だった。
(もっとさかのぼればじつぞうをうつしだすことじたいめずらしく、)
もっとさかのぼれば実像を写し出すこと自体珍しく、
(それがいろあざやかにせんめいにひょうげんされて、)
それが色鮮やかに鮮明に表現されて、
(さらにはてのひらにおさまるおおきさにまでこんぱくとになるなど、)
さらには手のひらに収まる大きさにまでコンパクトになるなど、
(きせきのようなものだったのだ。)
奇跡のようなものだったのだ。
(じつぞうをうつしだそうというがいねんやげんりそのものは、)
実像を写し出そうという概念や原理そのものは、
(きげんぜん3せいきごろにすでにそんざいしていたとされている。)
紀元前3世紀ごろに既に存在していたとされている。
(そして、ひかりをへいめんにさつえいするこころみは16せいきからおこなわれていた。)
そして、光を平面に撮影する試みは16世紀から行われていた。
(それはがかたちによるもので、)
それは画家たちによるもので、
(じっさいのふうけいにそっくりのえをえがくためのものだった。)
実際の風景にそっくりの絵を描くためのものだった。
(くらくしたへやのかべにたいしょうとなるぞうをうつし、)
暗くした部屋の壁に対象となる像を写し、
(それをにんげんがてでなぞっていたのだという。)
それを人間が手でなぞっていたのだという。
(えいぞうをかみやいしにていちゃくさせるしゃしんぎじゅつは、)
映像を紙や石に定着させる写真技術は、
(19せいきはじめにほぼどうじにふくすうのばしょでうまれていた。)
19世紀初めにほぼ同時に複数の場所で生まれていた。
(まさに、さんぎょうかくめいによっておおくのひとがとみをてにしたじだいだったため、)
まさに、産業革命によって多くの人が富を手にした時代だったため、
(しょうぞうがのじゅようがたかまり、いっきにひろがったとされる。)
肖像画の需要が高まり、一気に広がったとされる。
(さらに、せきばんががしんぶんずはんなどにりようされるようになり、)
さらに、石版画が新聞図版などに利用されるようになり、
など
(りあるなひょうげんがついきゅうされるようになっていく。)
リアルな表現が追求されるようになっていく。
(そんなじだいだったこともあり、)
そんな時代だったこともあり、
(あたらしいぎじゅつがつぎつぎとうみだされていった。)
新しい技術が次々と生み出されていった。
(ひかりをかんじてきろくできるざいりょうをもちいたたいぷがはつめいされると、そのかいりょうがすすんだ。)
光を感じて記録できる材料を用いたタイプが発明されると、その改良が進んだ。
(わがくにへでんらいしたのもちょうどそのころだったという。)
わが国へ伝来したのもちょうどそのころだったという。
(ゆにゅうしたのはながさきのぼうえきしょうだとされており、)
輸入したのは長崎の貿易商だとされており、
(やがていくつかのはんでじっけんやけんきゅうがおこなわれるようになった。)
やがて幾つかの藩で実験や研究が行われるようになった。
(げんそんしているもので、にほんじんがさつえいしたさいこのものは、)
現存しているもので、日本人が撮影した最古のものは、
(1857ねんにうつされたしょうぞうしゃしんだといわれている。)
1857年に写された肖像写真だといわれている。
(19せいきのおわりごろになって、とうとうふぃるむがたんじょうする。)
19世紀の終わりごろになって、とうとうフィルムが誕生する。
(そこからかめらじたいのかいりょうもすすみ、)
そこからカメラ自体の改良も進み、
(もちはこびしやすくてきどうせいのあるげんざいのかたちによりちかいものがうみだされた。)
持ち運びしやすくて機動性のある現在の形により近いものが生み出された。
(こうどでせんさいながぞうのふくしゃがかのうとなり、つかいすてのものもとうじょうし、)
高度で繊細な画像の複写が可能となり、使い捨てのものも登場し、
(せんもんてきなちしきがなくてもだれでもかんたんにあつかえるようになった。)
専門的な知識がなくても誰でも簡単に扱えるようになった。
(そして1980ねんだいになると、)
そして1980年代になると、
(がぞうをでんきしんごうにおきかえてきろくするびでおかめらからはってんした、)
画像を電気信号に置き換えて記録するビデオカメラから発展した、
(でんししきのかめらがとうじょうする。)
電子式のカメラが登場する。
(それが、あんかになり、)
それが、安価になり、
(きがるにてにはいるようになったことでさらにひろがりをみせた。)
気軽に手に入るようになったことでさらに広がりを見せた。
(そして、けいたいでんわのたきのうかにより、)
そして、携帯電話の多機能化により、
(ほとんどのひとがいつももちあるくほどにまで、みぢかなものとなっていったのだ。)
ほとんどの人がいつも持ち歩くほどにまで、身近なものとなっていったのだ。







