【第125回】検定試験 準2級
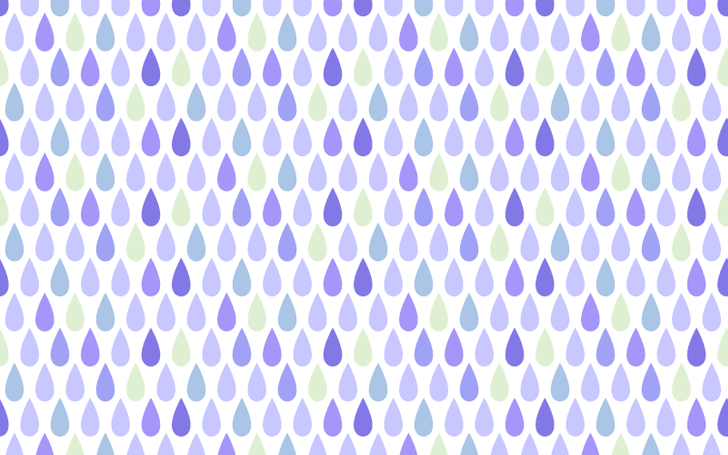
日本語ワープロ検定試験
第125回(令和2年12月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6324 | S | 6.8 | 92.7% | 218.2 | 1497 | 117 | 32 | 2026/01/30 |
| 2 | sss | 6149 | A++ | 6.4 | 95.0% | 230.9 | 1498 | 78 | 32 | 2026/02/06 |
| 3 | やまだ | 3442 | D | 3.8 | 90.5% | 396.5 | 1524 | 159 | 32 | 2026/01/27 |
関連タイピング
-
長文を打つ練習ができます。
プレイ回数35万 長文786打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
日本国憲法の第1章のタイピングです
プレイ回数23 長文かな1583打 -
コレ最後まで打てたらすごいと思う。(フル)
プレイ回数5846 歌詞120秒 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
タイピング練習に関する長文です
プレイ回数24万 長文1159打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(わがくにのなつのごちそうといえば、)
わが国の夏のご馳走といえば、
(うなぎをおもいうかべるひとがすくなくないでしょう。)
ウナギを思い浮かべる人が少なくないでしょう。
(じょうもんじだいのいせきでそのほねがしゅつどしていることから、)
縄文時代の遺跡でその骨が出土していることから、
(このころからしょくようにしていたのではないかとかんがえられています。)
この頃から食用にしていたのではないかと考えられています。
(そして、げんざいのようにたれをつけてやくようになったのは、)
そして、現在のようにタレを付けて焼くようになったのは、
(しょうゆやみりんがふきゅうしたえどじだいだとされています。)
醤油やみりんが普及した江戸時代だとされています。
(このことから、わがくにでふるくからあいされてきたりょうりだといえるでしょう。)
このことから、わが国で古くから愛されてきた料理だといえるでしょう。
(ところが、このままでは)
ところが、このままでは
(これをたべられなくなるひがくるのではないかとしんぱいされています。)
これを食べられなくなる日が来るのではないかと心配されています。
(なぜならきんねん、)
なぜなら近年、
(にほんうなぎのぎょかくりょうがげんしょうしているからです。)
ニホンウナギの漁獲量が減少しているからです。
(なぜ、このようなじたいがおきてしまったのでしょうか。)
なぜ、このような事態が起きてしまったのでしょうか。
(かれらはうみでうまれたあと、かわをのぼってせいちょうしていきますが、)
彼らは海で生まれた後、川を上って成長していきますが、
(ちきゅうおんだんかによるかいようかんきょうのへんどうや)
地球温暖化による海洋環境の変動や
(かせんかんきょうのあっかといったげんしょうがおき、)
河川環境の悪化といった現象が起き、
(それによってせいそくするばしょやえさがげんしょうしているのです。)
それによって生息する場所やエサが減少しているのです。
(また、わたしたちにんげんがひつよういじょうにほかくしてきたことも)
また、わたしたち人間が必要以上に捕獲してきたことも
(げんいんだといわれています。)
原因だといわれています。
(このようなりゆうから、こくないでりゅうつうしているうなぎのほとんどはようしょくだそうです。)
このような理由から、国内で流通しているウナギのほとんどは養殖だそうです。
(これには、ちぎょであるしらすうなぎをもちいていますが、)
これには、稚魚であるシラスウナギを用いていますが、
など
(これについてもぎょかくりょうがげんしょうしているといいます。)
これについても漁獲量が減少しているといいます。
(うなぎというしょくぶんかをまもるためにも、)
ウナギという食文化を守るためにも、
(かんぜんようしょくはじゅうようなとりくみとなるでしょう。)
完全養殖は重要な取り組みとなるでしょう。
(このけんきゅうはながねんつづけられており、)
この研究は長年続けられており、
(2002ねんにたまごからしらすうなぎまでのしいくに、)
2002年に卵からシラスウナギまでの飼育に、
(2010ねんには、じんこうてきにそだてられたせいぎょからえたたまごを)
2010年には、人工的に育てられた成魚から得た卵を
(ふかさせるかんぜんようしょくにせいこうしています。)
孵化させる完全養殖に成功しています。
(さらにその6ねんごには、)
さらにその6年後には、
(けいかくてきなさいらんとねんかんすうせんびのちぎょのせいさんがかのうになりました。)
計画的な採卵と年間数千尾の稚魚の生産が可能になりました。
(しょうぎょうかにむけて、)
商業化に向けて、
(たいりょうせいさんがかのうになるまでにはさまざまなかだいがありますが、)
大量生産が可能になるまでにはさまざまな課題がありますが、
(ふりょうをおぎなうきゅうせいしゅとしてきたいがたかまります。)
不漁を補う救世主として期待が高まります。







