選択公理⇒ツォルンの補題 の証明
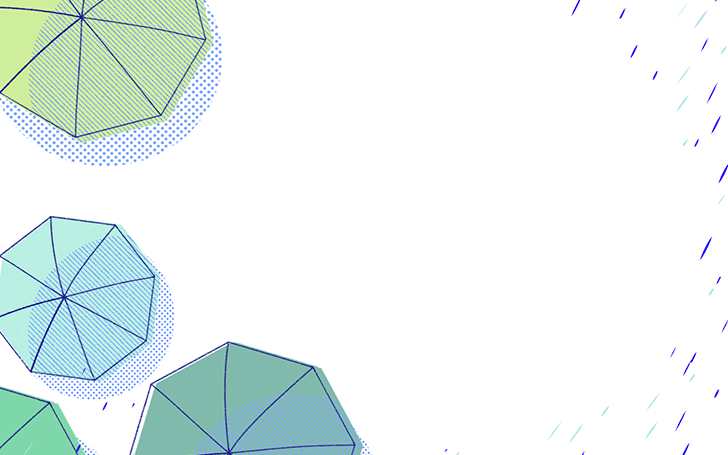
ツォルンの補題の証明のタイピング
選択公理を認めてツォルンの補題を示す証明のタイピングです。
内田伏一先生の証明をもとに、加筆・省略・修正したりタイピングがしやすいよう言い換えたりした文章をタイピングします。
アルファベットは対応する文字をそのまま入力します。ギリシャ文字は"φ"のように表示されますが、「ふぁい」のように読み方を日本語で打ち込みます。かっこ()や無限∞、アスタリスク*などの記号は表示されますが、入力はしません。ただし、コンマ,やダッシュ'は入力します。
参考文献
内田伏一, (2022), 『数学シリーズ 集合と位相 増補新装版』
内田伏一先生の証明をもとに、加筆・省略・修正したりタイピングがしやすいよう言い換えたりした文章をタイピングします。
アルファベットは対応する文字をそのまま入力します。ギリシャ文字は"φ"のように表示されますが、「ふぁい」のように読み方を日本語で打ち込みます。かっこ()や無限∞、アスタリスク*などの記号は表示されますが、入力はしません。ただし、コンマ,やダッシュ'は入力します。
参考文献
内田伏一, (2022), 『数学シリーズ 集合と位相 増補新装版』
関連タイピング
-
「女王の教室」名言集を、お楽しみに!
プレイ回数1519 長文かな1052打 -
速ければ速いほど強い世界
プレイ回数794万 短文かな87打 -
総勢50名の戦国武将を集めてみました
プレイ回数22万 かな60秒 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒 -
主人公ケイトによる物語です
プレイ回数3.7万 長文かな1417打 -
ダンマパダです
プレイ回数134 180秒 -
ビジネスメールでよく使われる文章です!
プレイ回数176万 長文かな60秒 -
何秒で全部打てるか挑戦してみよう!
プレイ回数439万 短文かな298打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(つぉるんのほだい
きのうてきなはんじゅんじょしゅうごうはすくなくともひとつきょくだいげんをもつ)
ツォルンの補題
帰納的な半順序集合は少なくとも一つ極大元をもつ
(しょうめい
xをはんじゅんじょしゅうごうとし,fをxじょうのせんたくかんすうとする.)
証明
Xを半順序集合とし, fをX上の選択関数とする.
(xのせいれつぶぶんしゅうごうwとそのげんaにたいして,でるたw,aをxのげんであって,)
Xの整列部分集合Wとその元aに対して, Δ(W, a)をXの元であって,
(waのにんいのげんよりしんにおおきいものすべてからなるしゅうごうとする.)
W〈a〉の任意の元より真に大きいもの全てからなる集合とする.
(ここでaはでるたw,aにぞくするため,でるたw,aはくうでない.)
ここでaはΔ(W, a)に属するため, Δ(W, a)は空でない.
(xのせいれつぶぶんしゅうごうwがfれつであるということを,wにぞくするにんいのげんaにたいし,)
Xの整列部分集合Wがf列であるということを,Wに属する任意の元aに対し,
(でるたw,aのfによるいきさきがaであるということとさだめる.)
Δ(W, a)のfによる行き先がaであるということと定める.
(たとえば,fxのみをようそにもついってんしゅうごうはfれつである.)
例えば, f(X)のみを要素に持つ一点集合はf列である.
minW=f(X)となることは証明に必要ないため省略しました
(というのも,fxのfxによるせっぺんはくうしゅうごうのため,)
というのも, {f(X)}のf(X)による切片は空集合のため,
(でるたfx,fxはxといっちし,したがってそのfによるいきさきは)
Δ({f(X)}, f(X))はXと一致し, 従ってそのfによる行き先は
(ほかならぬfxとなるからである.したがってfれつはたしかにそんざいする.)
他ならぬf(X)となるからである. 従ってf列は確かに存在する.
(w1,w2をfれつとすると,りょうしゃはいっちするか,)
W1, W2をf列とすると, 両者は一致するか,
ここから原文の(1)の内容
(またはいっぽうがたほうのせっぺんといっちすることをしめす.)
または一方が他方の切片と一致することを示す.
(せいれつしゅうごうのひかくていりより,w1とw2はじゅんじょどうけいであるか,)
整列集合の比較定理より, W1とW2は順序同型であるか,
(またはいっぽうがたほうのせっぺんとじゅんじょどうけいである.)
または一方が他方の切片と順序同型である.
(たとえばw2のげんaにたいしw1とw2aはじゅんじょどうけいであるとしよう.)
例えばW2の元aに対しW1とW2〈a〉は順序同型であるとしよう.
(w1からのじゅんじょどうけいしゃふぁいをとると,ふぁいxはxとなることをしめす.)
W1からの順序同型射φをとると, φ(x)はxとなることを示す.
(vをふぁいxがxとならないw1のげんxぜんたいのしゅうごうとする.)
Vをφ(x)がxとならないW1の元x全体の集合とする.
(vがくうでないとかていし,そのさいしょうげんyをとる.)
Vが空でないと仮定し, その最小元yをとる.
(このとき,yよりしんにちいさいw1のげんxにたいして,)
このとき, yより真に小さいW1の元xに対して,
W1〈y〉=W2〈φ(y)〉であることを原文より詳しく証明します
など
(xすなわちふぁいxはふぁいyみまんのため,xはw2ふぁいyにふくまれる.)
x即ちφ(x)はφ(y)未満のため, xはW2〈φ(y)〉に含まれる.
(したがって,w1yはw2ふぁいyのぶぶんしゅうごうである.)
従って, W1〈y〉はW2〈φ(y)〉の部分集合である.
(ぎゃくにふぁいyみまんのw2のげんxにたいし,yすなわちふぁいyのふぁいによるひきもどしは,)
逆にφ(y)未満のW2の元xに対し,y即ちφ(y)のφによる引き戻しは,
(xのふぁいによるひきもどしすなわちxよりしんにちいさいため,)
xのφによる引き戻し即ちxより真に小さいため,
(w2ふぁいyはw1yのぶぶんしゅうごうである.)
W2〈φ(y)〉はW1〈y〉の部分集合である.
(したがってけっきょく,w1yとw2ふぁいyはいっちする.)
従って結局, W1〈y〉とW2〈φ(y)〉は一致する.
(よって,でるたw1,yとでるたw2,ふぁいyもいっちするため,)
よって, Δ(W1, y)とΔ(W2, φ(y))も一致するため,
(それらのfによるいきさきをかんがえれば,)
それらのfによる行き先を考えれば,
(w1やw2はfれつであることからyとふぁいyはいっちする.)
W1やW2はf列であることからyとφ(y)は一致する.
(これはyがvのげんであることにむじゅんする.)
これはyがVの元であることに矛盾する.
(よってvはくうしゅうごうとなり,にんいのw1のげんxにたいしふぁいxはxとなる.)
よってVは空集合となり, 任意のW1の元xに対しφ(x)はxとなる.
(ゆえにw1はw2aにひとしい.)
ゆえにW1はW2〈a〉に等しい.
(どうようにして,w1のせっぺんがw2とじゅんじょどうけいならそれらはしゅうごうとしていっちし,)
同様にして, W1の切片がW2と順序同型ならそれらは集合として一致し,
(w1とw2がじゅんじょどうけいならそれらはしゅうごうとしていっちすることもしめせる.)
W1とW2が順序同型ならそれらは集合として一致することも示せる.
(すべてのfれつのわしゅうごうwはせいれつしゅうごうであることをしめそう.)
全てのf列の和集合W∞は整列集合であることを示そう.
ここから原文の(2)の内容
(wのくうでないぶぶんしゅうごうmをにんいにとり,mのげんaをとる.)
W∞の空でない部分集合Mを任意にとり, Mの元aをとる.
(aをふくむfれつwをひとつとると,wはせいれつしゅうごうであるから,)
aを含むf列Wを一つとると, Wは整列集合であるから,
(wとmのまじわりはくうでないwのぶぶんしゅうごうのため,そのさいしょうげんmがそんざいする.)
WとMの交わりは空でないWの部分集合のため, その最小元mが存在する.
(このとき,mのさいしょうげんがそんざいし,mといっちすることをしめす.)
このとき, Mの最小元が存在し, mと一致することを示す.
原文では背理法で示していましたが, ここでは直説法で示します
(mのげんyをにんいにとる.yがwにもふくまれていれば,mはyいかである.)
Mの元yを任意にとる. yがWにも含まれていれば, mはy以下である.
(yはwにふくまれていないとし,yをふくむfれつw’をひとつとる.)
yはWに含まれていないとし, yを含むf列W'を一つとる.
(このとき,wとw’はいっちせず,またwのせっぺんはw’といっちしないため,)
このとき, WとW'は一致せず, またWの切片はW'と一致しないため,
(いぜんしめしたことからあるw’のげんbがそんざいしてwとw’bはいっちする.)
以前示したことからあるW'の元bが存在してWとW'〈b〉は一致する.
「以前示したこと」とは(1)の内容のこと
(yはwすなわちw’bにふくまれないため,bはyいかである.)
yはW即ちW'〈b〉に含まれないため, bはy以下である.
(いっぽうmはw’bにふくまれるためmはbみまん,したがってmはyみまんとなる.)
一方mはW'〈b〉に含まれるためmはb未満, 従ってmはy未満となる.
(よっていずれのばあいもmはyいかとなるため,mはmのさいしょうげんとなる.)
よっていずれの場合もmはy以下となるため, mはMの最小元となる.
(ゆえにwはせいれつしゅうごうである.)
ゆえにW∞は整列集合である.
(にんいのfれつwにたいし,wはwであるか,またはそのせっぺんであることをしめす.)
任意のf列Wに対し, WはW∞であるか,またはその切片であることを示す.
ここから原文の(3)の内容
(wはwでないとかていすると,wとwのさしゅうごうのさいしょうげんaがそんざいする.)
WはW∞でないと仮定すると, W∞とWの差集合の最小元aが存在する.
(このとき,wはwaであることをしめそう.)
このとき, WはW∞〈a〉であることを示そう.
(aをふくむfれつw’をひとつとる.wはw’とはなりえず,)
aを含むf列W'を一つとる. WはW'とはなりえず,
(またw’はwのせっぺんとはなりえないため,)
またW'はWの切片とはなりえないため,
(あるw’のげんbがそんざいしてwはw’bとなる.)
あるW'の元bが存在してWはW'〈b〉となる.
(waのげんxをとる.xがwにふくまれていなければ,)
W∞〈a〉の元xをとる. xがWに含まれていなければ,
W∞〈a〉がWに含まれることを原文より詳しく証明します
(xはwとwのさしゅうごうにふくまれていて,さらにaよりしんにちいさいため,)
xはW∞とWの差集合に含まれていて, さらにaより真に小さいため,
(aのさいしょうせいにむじゅんする.したがってxはwにふくまれている.)
aの最小性に矛盾する. 従ってxはWに含まれている.
(よってwaはwのぶぶんしゅうごうである.)
よってW∞〈a〉はWの部分集合である.
(また,w’はwのぶぶんしゅうごうのため,w’aはwaのぶぶんしゅうごう.)
また, W'はW∞の部分集合のため, W'〈a〉はW∞〈a〉の部分集合.
(さらに,aはwすなわちw’bにふくまれないため,bはaいかであり,)
さらに, aはW即ちW'〈b〉に含まれないため, bはa以下であり,
W'〈b〉がW'〈a〉に含まれることを原文より簡潔に証明します
(それゆえw’bはw’aのぶぶんしゅうごうとなる.)
それゆえW'〈b〉はW'〈a〉の部分集合となる.
(したがって,wa,w,w’b,w’a,waは)
従って, W∞〈a〉, W, W'〈b〉, W'〈a〉, W∞〈a〉は
(このじゅんにほうがんかんけいをなすため,これらはすべてひとしい.)
この順に包含関係をなすため, これらは全て等しい.
(よってwはwaといっちする.)
よってWはW∞〈a〉と一致する.
(ゆえに,fれつはwであるか,またはそのせっぺんとひとしくなる.)
ゆえに, f列はW∞であるか, またはその切片と等しくなる.
(wがfれつであることをしめす.wがせいれつしゅうごうであることはすでにしめした.)
W∞がf列であることを示す. W∞が整列集合であることは既に示した.
ここから原文の(4)の内容
(wのげんaをにんいにあたえ,aをふくむfれつwをひとつとる.)
W∞の元aを任意に与え, aを含むf列Wを一つとる.
(このとき,あるwのげんa’がそんざいしてwはwaとなるため,)
このとき, あるW∞の元a'が存在してWはW∞〈a〉となるため,
(waはwa’のaによるせっぺん,つまりwaとひとしくなる.)
W〈a〉はW∞〈a'〉のaによる切片, つまりW∞〈a〉と等しくなる.
(したがってでるたw,aはでるたw,aとひとしくなる.)
従ってΔ(W∞, a)はΔ(W, a)と等しくなる.
(wはfれつよりそれらをfでおくるとaになるため,wはfれつである.)
Wはf列よりそれらをfで送るとaになるため, W∞はf列である.
(いよいよ,xのきょくだいげんがそんざいすることをしめす.)
いよいよ, Xの極大元が存在することを示す.
(これまでしめしてきたことにより,wはほうがんかんけいのいみでさいだいのfれつである.)
これまで示してきたことにより, W∞は包含関係の意味で最大のf列である.
(さらにwはせいれつしゅうごう,とくにぜんじゅんじょしゅうごうであることもしめしたから,)
さらにW∞は整列集合, とくに全順序集合であることも示したから,
(xはきのうてきであることより,wはじょうかいをもつ.)
Xは帰納的であることより, W∞は上界をもつ.
(そのひとつをwとすると,wはxのきょくだいげんであることがつぎのようにしてしめされる.)
その一つをwとすると,wはXの極大元であることが次のようにして示される.
(wがxのきょくだいげんでない,つまりwよりしんにおおきいw’がそんざいするとかていする.)
wがXの極大元でない, つまりwより真に大きいw'が存在すると仮定する.
(wのにんいのげんよりしんにおおきいxのげんぜんたいからなるしゅうごうでるたをさだめる.)
W∞の任意の元より真に大きいXの元全体からなる集合Δ∞を定める.
(wのげんbにたいし,wはbいじょうであり,またw’はwよりしんにおおきいため,)
W∞の元bに対し, wはb以上であり, またw'はwより真に大きいため,
(w’はbよりしんにおおきく,したがってw’はでるたにふくまれる.)
w'はbより真に大きく, 従ってw'はΔ∞に含まれる.
(よってでるたはくうではないため,zをfでるたとあたえ,)
よってΔ∞は空ではないため, zをf(Δ∞)と与え,
(wをwとzからなるいってんしゅうごうのわしゅうごうとさだめる.)
W*をW∞とzからなる一点集合の和集合と定める.
(このとき,wはfれつであることをしめす.)
このとき, W*はf列であることを示す.
(zはでるたのげんであるため,zはwのにんいのげんよりしんにおおきい.)
zはΔ∞の元であるため, zはW∞の任意の元より真に大きい.
(したがって,wのにんいのくうでないぶぶんしゅうごうaにたいし,)
従って, W*の任意の空でない部分集合Aに対し,
(aがzならzはaのさいしょうげんで,そうでなければaからzをのぞいたしゅうごうは)
Aが{z}ならzはAの最小元で, そうでなければAからzを除いた集合は
(wのくうでないぶぶんしゅうごうとなるが,そのさいしょうげんがaのさいしょうげんとなる.)
W∞の空でない部分集合となるが、その最小元がAの最小元となる.
(よってwはせいれつしゅうごうである.)
よってW*は整列集合である.
(wzはwであり,でるたとでるたw,zのていぎはいっちするため,)
W*〈z〉はW∞であり, Δ∞とΔ(W*, z)の定義は一致するため,
(でるたw,zすなわちでるたのfによるいきさきはzとなる.)
Δ(W*, z)即ちΔ∞のfによる行き先はzとなる.
(つぎに,zとことなるwのげんaをにんいにあたえよう.)
次に, zと異なるW*の元aを任意に与えよう.
W*がf列になることについて、原文の証明では不十分なので証明を補います
(zはでるたのげんでaはwのげんであるため,aはzよりしんにちいさい.)
zはΔ∞の元でaはW∞の元であるため, aはzより真に小さい.
(したがってwaとwaはいっちするため,)
従ってW*〈a〉とW∞〈a〉は一致するため,
(でるたw,aとでるたw,aもいっちする.)
Δ(W*, a)とΔ(W∞, a)も一致する.
(aはwのげんでwはfれつのため,)
aはW∞の元でW∞はf列のため,
(でるたw,aすなわちでるたw,aのfによるいきさきはaとなる.)
Δ(W*, a)即ちΔ(W∞, a)のfによる行き先はaとなる.
(よってwはfれつであることがしめされた.)
よってW*はf列であることが示された.
(したがって,wをしんにふくむようなfれつがそんざいすることになるが,)
従って, W∞を真に含むようなf列が存在することになるが,
(このことはwがほうがんかんけいのいみでさいだいのfれつであることにむじゅんする.)
このことはW∞が包含関係の意味で最大のf列であることに矛盾する.
(このむじゅんは,wがxのきょくだいげんでないとかていしたことからしょうじたものである.)
この矛盾は, wがXの極大元でないと仮定したことから生じたものである.
(よってwはxのきょくだいげんである.ゆえにつぉるんのほだいがなりたつ.)
よってwはXの極大元である. ゆえにツォルンの補題が成り立つ.








