刑法
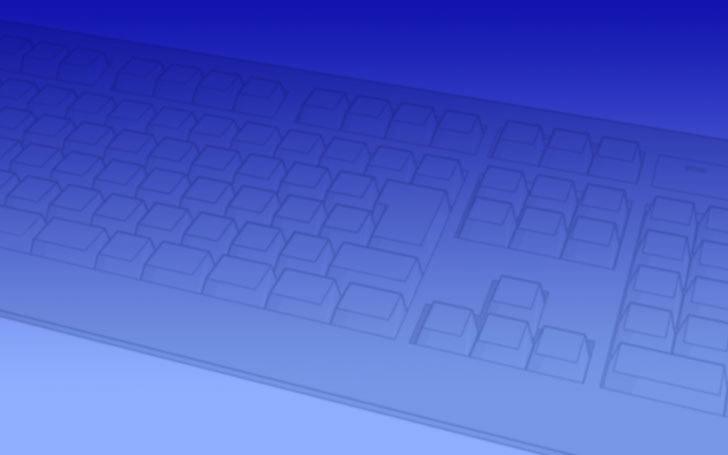
問題文
(じっこうこういとけっかとのいんがかんけいは)
実行行為と結果との因果関係は
(ぐうはつてきけっかをはいじょしてきせいなきせきはんいをかくていするために)
偶発的結果を排除し適正な帰責範囲を確定するために
(きゃっかんてきにそんざいするすべてのじじょうをはんだんしりょうとし)
客観的に存在する全ての事情を判断資料とし
(じょうけんかんけいがあることをぜんていに)
条件関係があることを前提に
(こういのもつきけんがけっかにげんじつかしたかによってはんだんする。)
行為のもつ危険が結果に現実化したかによって判断する。
(さくいぎむはさくいとどうかちといえるばあいにみとめられる。)
作為義務は作為と同価値といえる場合に認められる。
(そして、さくいはけっかにいたるいんがのながれをせっていしそのけいかをしはいするこうい)
そして、作為は結果に至る因果の流れを設定しその経過を支配する行為
(であるから、ふさくいがさくいとどうかちといえるためには)
であるから、不作為が作為と同価値と言えるためには
(いんがけいかをぐたいてきにしはいしたとひょうかできることがひつようであり、)
因果経過を具体的に支配したと評価できることが必要であり、
(そのためには、はいたてきしはいがみとめられかつせんこうこういもしくはほごのひきうけ)
そのためには、排他的支配が認められかつ先行行為もしくは保護の引受け
(がみとめられることがひつようである。)
が認められることが必要である。
(こいとは、はんざいじじつをにんしきしにんようすることをいう。)
故意とは、犯罪事実を認識し認容することをいう。
(にんしきがなければはんたいどうきのけいせいはふかのうであり、)
認識がなければ反対動機の形成は不可能であり、
(にんようがひつようなのは、かしつよりもおもいこいせきにんをきそづけるためである。)
認容が必要なのは、過失よりも重い故意責任を基礎づけるためである。
(せんゆうりだつぶつおうりょうざい(254じょう)のこいできゃっかんてきにはせっとうざい(235じょう))
占有離脱物横領罪(254条)の故意で客観的には窃盗罪(235条)
(をじつげんしたことになるのでちゅうしょうてきじじつのさくごがもんだいとなる。)
を実現したことになるので抽象的事実の錯誤が問題となる。
(かるいつみのこいでおもいつみをじつげんしたばあいについて、38じょう2こうは)
軽い罪の故意で重い罪を実現した場合について、38条2項は
(「おもいつみによってしょだんすることはできない」ときていしてあるが、)
「重い罪によって処断することはできない」と規定してあるが、
(これはおもいつみはせいりつしないというしゅしである。)
これは重い罪は成立しないという趣旨である。
(なぜなら、おもいつみのこいがないにもかかわらずおもいつみのせいりつをみとめるのは)
なぜなら、重い罪の故意がないにもかかわらず重い罪の成立を認めるのは
(せきにんしゅぎにはんするからである。したがって、せっとうざいはせいりつしない。)
責任主義に反するからである。したがって、窃盗罪は成立しない。
(それでは、かるいつみであるせんゆうりだつぶつおうりょうざいがせいりつするか。)
それでは、軽い罪である占有離脱物横領罪が成立するか。
(このてん、せんゆうりだつぶつおうりょうざいのこいはあるが、)
この点、占有離脱物横領罪の故意はあるが、
(それにたいおうするきゃっかんてきじじつはそんざいしない。)
それに対応する客観的事実は存在しない。
(そこで、せんゆうりだつぶつおうりょうざいとせっとうざいのこうせいようけんに)
そこで、占有離脱物横領罪と窃盗罪の構成要件に
(じっしつてきにかさなりあいがみとめられるかがもんだいとなる。)
実質的に重なり合いが認められるかが問題となる。
(こうせいようけんのしゅようなようそはじっこうこういとけっかであるから、)
構成要件の主要な要素は実行行為と結果であるから、
(こうせいようけんがかさなりあうといえるためには、)
構成要件が重なり合うといえるためには、
(こういたいようがきょうつうで、かつ、ほごほうえきがきょうつうであることがひつようである。)
行為態様が共通で、かつ、保護法益が共通であることが必要である。
(このてん、せんゆうりだつぶつおうりょうざいのほごほうえきは「ざいぶつのしょゆうけん」であり、)
この点、占有離脱物横領罪の保護法益は「財物の所有権」であり、
(せっとうざいのほごほうえきは「ざいぶつのしょゆうけんおよびせんゆう」であるから、)
窃盗罪の保護法益は「財物の所有権および占有」であるから、
(りょうざいのほごほうえきはしょゆうけんのげんどできょうつうせいがある。)
両罪の保護法益は所有権の限度で共通性がある。
(また、せんゆうりだつぶつおうりょうざいとせっとうのこういたいようは、)
また、占有離脱物横領罪と窃盗の行為態様は、
(たにんのざいぶつをふほうにりょうとくするこういであるというてんできょうつうせいがある。)
他人の財物を不法に領得する行為であるという点で共通性がある。
(したがって、りょうざいのこうせいようけんはじっしつてきにかさなりあうといえるので、)
したがって、両罪の構成要件は実質的に重なり合うといえるので、
(せんゆうりだつぶつおうりょうざいがせいりつする。)
占有離脱物横領罪が成立する。
(せっとうざい(235じょう)のこいできゃっかんてきにはせんゆうりだつぶつおうりょうざい(254じょう))
窃盗罪(235条)の故意で客観的には占有離脱物横領罪(254条)
(をじつげんしたことになるのでちゅうしょうてきじじつのさくごのもんだいとなる。)
を実現したことになるので抽象的事実の錯誤の問題となる。
(こいとはこうせいようけんがいとうじじつのにんしきにんようをいうところ、)
故意とは構成要件該当事実の認識・認容をいうところ、
(こういしゃがにんしきしたじじつとげんじつにはっせいしたじじつがこうせいようけんをいにするときは)
行為者が認識した事実と現実に発生した事実が構成要件を異にするときは
(はんたいどうきのけいせいはふかのうでありこいはそきゃくされるが、)
反対動機の形成は不可能であり故意は阻却されるが、
(こうせいようけんがじっしつてきにかさなりあうばあいには、かさなりあうげんどで)
構成要件が実質的に重なり合う場合には、重なり合う限度で
(はんたいどうきのけいせいがかのうであるからこいはんがせいりつする。)
反対動機の形成が可能であるから故意犯が成立する。
(そして、こうせいようけんのしゅようなようそがじっこうこういとけっかであるから、)
そして、構成要件の主要な要素が実行行為と結果であるから、
(かさなりあいのはんだんきじゅんは)
重なり合いの判断基準は
(ほごほうえきがきょうつうでかつこういたいようがきょうつうであることである。)
保護法益が共通でかつ行為態様が共通であることである。
(このてん、せんゆうりだつぶつおうりょうざいのほごほうえきは「ざいさんのしょゆうけん」であり、)
この点、占有離脱物横領罪の保護法益は「財産の所有権」であり、
(せっとうざいのほごほうえきは「ざいぶつのしょゆうけんおよびせんゆう」であるから、)
窃盗罪の保護法益は「財物の所有権および占有」であるから、
(りょうざいのほごほうえきはしょゆうけんのげんどできょうつうせいがある。)
両罪の保護法益は所有権の限度で共通性がある。
(また、せんゆうりだつぶつおうりょうざいとせっとうざいのこういたいようは、)
また、占有離脱物横領罪と窃盗罪の行為態様は、
(たにんのざいぶつをふほうにりょうとくするこういであるというてんできょうつうせいがある。)
他人の財物を不法に領得する行為であるという点で共通性がある。
(したがって、りょうざいのこうせいようけんはじっしつてきにかさなりあうといえるので、)
したがって、両罪の構成要件は実質的に重なり合うといえるので、
(せんゆうりだつぶつおうりょうざいのこいせきにんがみとめられ、せんゆうりだつぶつおうりょうざいがせいりつする。)
占有離脱物横領罪の故意責任が認められ、占有離脱物横領罪が成立する。