【第126回】検定試験 1級
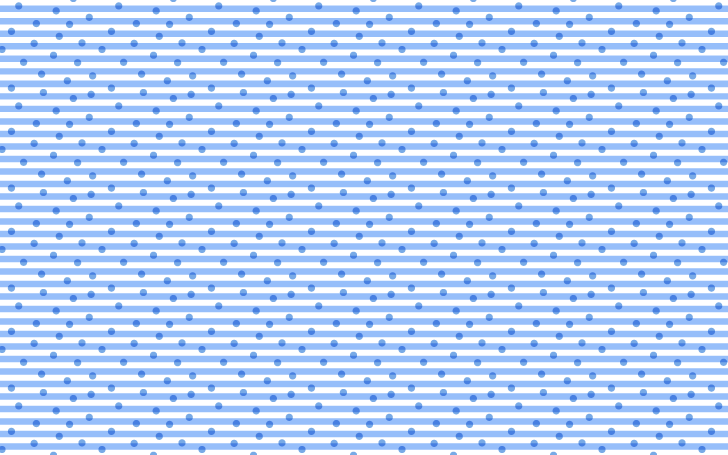
日本語ワープロ検定試験
第126回(令和3年2月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sss | 6266 | S | 6.6 | 95.0% | 312.3 | 2064 | 107 | 40 | 2026/02/07 |
| 2 | PLMKJNB4 | 6234 | A++ | 6.6 | 93.7% | 309.4 | 2067 | 138 | 40 | 2026/01/31 |
| 3 | Tak | 5470 | B++ | 5.6 | 97.0% | 366.9 | 2071 | 64 | 40 | 2026/01/30 |
関連タイピング
-
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
「tuki.」さんの「晩餐歌」です!!(フル)
プレイ回数606 歌詞かな120秒 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
これでー今年の運勢を占おう!
プレイ回数161 457打 -
ミセスぅーーーーー!!!!
プレイ回数283 歌詞かな114打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ことばのなかには、じだいをへていくうちに)
言葉の中には、時代を経ていくうちに
(ちがったぶんみゃくでつかわれるようになったものがたくさんあります。)
違った文脈で使われるようになったものがたくさんあります。
(たとえば、さいきんでは「もる」というたんごがあげられるでしょう。)
例えば、最近では「盛る」という単語が挙げられるでしょう。
(もともとはものをいれてみたす、)
もともとは物を入れて満たす、
(つんでたかくするといういみでつかわれています。)
積んで高くすると言う意味で使われています。
(それがわかものをちゅうしんとして、けしょうやはなしをもるなどのように、)
それが若者を中心として、化粧や話を盛るなどのように、
(おおげさにするということをひょうげんするためにもちいられるようになりました。)
大袈裟にするということを表現するために用いられるようになりました。
(きんねんのじしょには、あたらしいごぎとしてくわえられているといいます。)
近年の辞書には、新しい語義として加えられているといいます。
(どうようのれいには「やばい」もあります。)
同様の例には「やばい」もあります。
(じゅうらいは、きけんやふつごうなじょうきょうがよそうされるさまをあらわすのにしようされていましたが、)
従来は、危険や不都合な状況が予想される様を表すのに使用されていましたが、
(わかもののあいだでさいこうなじょうたいをしめすこうていてきなぶんみゃくでもちいられるようになり、)
若者の間で最高な状態を示す肯定的な文脈で用いられるようになり、
(ごぎがひろがりました。)
語義が広がりました。
(さきごろはっぴょうされたにほんをだいひょうするこくごじてんのかいていばんにも、)
先ごろ発表された日本を代表する国語辞典の改訂版にも、
(このあたらしいようほうがさいようされてわだいとなりました。)
この新しい用法が採用されて話題となりました。
(すでにあたりまえのようにうけいれられている「しるばー」も、)
既に当たり前のように受け入れられている「シルバー」も、
(そんなことばのひとつです。)
そんな言葉の一つです。
(はなしは1973ねんまでさかのぼります。)
話は1973年までさかのぼります。
(とうじのこくてつでは、してつとのきょうそうがはげしくなったため、)
当時の国鉄では、私鉄との競争が激しくなったため、
(あたらしいさーびすをもさくしていました。)
新しいサービスを模索していました。
(そこでたんとうしゃがおもいついたのが、こうれいしゃむけのゆうせんせきをもうけることでした。)
そこで担当者が思い付いたのが、高齢者向けの優先席を設けることでした。
など
(ところが、とうじのこくてつはあかじつづきでよさんがかぎられていました。)
ところが、当時の国鉄は赤字続きで予算が限られていました。
(せいげんのあるなか、せめてしーとだけでもはりかえようとさがしたところ、)
制限のある中、せめてシートだけでも張り替えようと探したところ、
(はままつのこうじょうにとうかいどうしんかんせんむけによういされた)
浜松の工場に東海道新幹線向けに用意された
(あかるいぐれーのぬのじがあまっているのをみつけます。)
明るいグレーの布地が余っているのを見つけます。
(にほんには、しぶくてあじわいのあるものをあらわす「いぶしぎん」ということばがあり、)
日本には、渋くて味わいのある物を表す「いぶし銀」という言葉があり、
(このじだいのすこしまえにりゅうこうしたたんごに、)
この時代の少し前に流行した単語に、
(しょろうのみりょくあるだんせいをさす「ろまんすぐれー」というものがあります。)
初老の魅力ある男性を指す「ロマンスグレー」というものがあります。
(そうしたいんしょうからも、ゆうせんせきのめいしょうにぴったりだということで、)
そうした印象からも、優先席の名称にピッタリだということで、
(しるばーしーととなづけられたといいます。)
シルバーシートと名付けられたといいます。
(そのご、おおてしてつなどにもどうにゅうされてぜんこくにひろがり、)
その後、大手私鉄などにも導入されて全国に広がり、
(そのこしょうはこうれいしゃをあらわすものとなって、いっぱんてきにていちゃくしました。)
その呼称は高齢者を表すものとなって、一般的に定着しました。
(もしこくてつのこうじょうにちがういろのぬのじがあったら、)
もし国鉄の工場に違う色の布地があったら、
(ゆうせんせきもいちじのりゅうこうにおわり、)
優先席も一時の流行に終わり、
(こんなにひろがることはなかったかもしれません。)
こんなに広がることはなかったかもしれません。
(このようないみのかくだいは、いまにはじまったことではありません。)
このような意味の拡大は、今に始まったことではありません。
(ごぎのへんせんがみられることばはかずおおくそんざいします。)
語義の変遷が見られる言葉は数多く存在します。
(たようないみをもつことばをもちいると、)
多様な意味を持つ言葉を用いると、
(ばあいによってはごかいをうむこともあるでしょう。)
場合によっては誤解を生むこともあるでしょう。
(じょうほうをただしくでんたつするためには、)
情報を正しく伝達するためには、
(それをにんしきしてあいてやばめんにあわせてつかいわけていくひつようがあるのです。)
それを認識して相手や場面に合わせて使い分けていく必要があるのです。







