第128回日本語ワープロ検定試験 1級
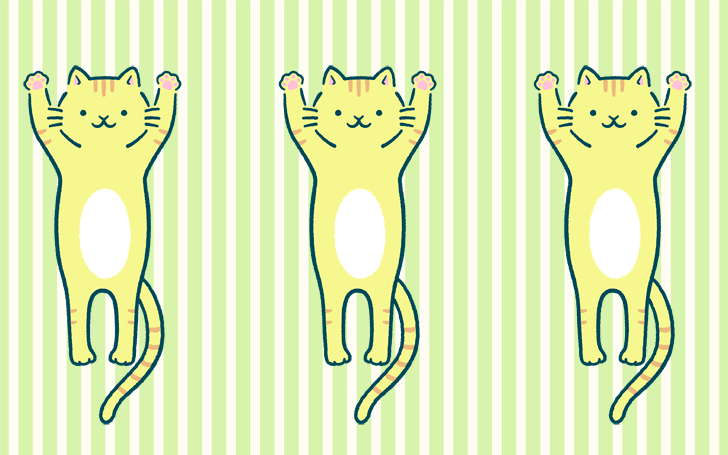
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | δ瑠夏¨ | 6207 | A++ | 6.5 | 95.4% | 312.7 | 2038 | 97 | 31 | 2026/01/06 |
| 2 | ひろみ | 5830 | A+ | 6.1 | 95.7% | 340.8 | 2080 | 93 | 31 | 2026/02/09 |
| 3 | a | 5545 | A | 5.8 | 94.8% | 347.7 | 2038 | 110 | 31 | 2026/01/04 |
| 4 | ku- | 5483 | B++ | 5.7 | 95.5% | 354.9 | 2040 | 94 | 31 | 2026/01/30 |
| 5 | fu-cyobi | 4893 | B | 5.1 | 94.8% | 394.6 | 2041 | 110 | 31 | 2026/01/06 |
関連タイピング
-
長文を打つ練習ができます。
プレイ回数36万 長文786打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
仕事における情報処理スキルについて。
プレイ回数5106 長文かな2104打 -
打ち切れたら天才だ
プレイ回数422 長文540打 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数6692 歌詞120秒 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.7万 歌詞かな200打 -
AIで作成。
プレイ回数130 長文1683打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(くらしのなかでつかっているものが、もっとつかいやすくなってほしいとおもったり、)
暮らしの中で使っているものが、もっと使いやすくなってほしいと思ったり、
(こんなぎじゅつがあったらべんりだろうとかんがえたりすることがあるだろう。)
こんな技術があったら便利だろうと考えたりすることがあるだろう。
(そんなあいであをもとに、けんきゅうかいはつしてじっさいにしょうひんとしてつくりだすひとがいる。)
そんなアイデアを基に、研究開発して実際に商品として作り出す人がいる。
(かれらのおかげで、わたしたちのせいかつがべんりでかいてきなものとなっている。)
彼らのおかげで、わたしたちの生活が便利で快適なものとなっている。
(しかし、そんなあいであをかってにつかわれたり、もほうされたりすれば、)
しかし、そんなアイデアを勝手に使われたり、模倣されたりすれば、
(あたらしいものをつくろうとするひとのいよくはうしなわれてしまうだろう。)
新しいものを作ろうとする人の意欲は失われてしまうだろう。
(そこで、かれらのはつめいをけんりとしてほごすることをもくてきに)
そこで、彼らの発明を権利として保護することを目的に
(こうさつされたもののひとつに、とっきょけんがある。)
考察されたものの一つに、特許権がある。
(では、このれきしをふりかえってみよう。ちゅうせいよーろっぱにおいて、こくおうやせいじかが)
では、この歴史を振り返ってみよう。中世ヨーロッパにおいて、国王や政治家が
(おんけいのしゅだんとしてけんげんをふよすることはあったが、せいどとして)
恩恵の手段として権限を付与することはあったが、制度として
(ととのっていたわけではなかった。きんだいにおけるせいどは、1474ねんにべねちあで)
整っていたわけではなかった。近代における制度は、1474年にベネチアで
(たんじょうし、そのあとえいこくではってんしたといわれている。にほんでは、めいじいしんごに)
誕生し、その後英国で発展したといわれている。日本では、明治維新後に
(ほんかくてきなとっきょけんがこうふされた。しかし、とうじのこくみんはこのせいどをりかいし)
本格的な特許権が公布された。しかし、当時の国民はこの制度を理解し
(りようするまでにいたらず、うんえいめんでももんだいがしょうじたため、そのしこうはよくとしちゅうし)
利用するまでに至らず、運営面でも問題が生じたため、その施行は翌年中止
(されたという。そのあと、せいどのひつようせいがさいかくにんされ、1885ねんには)
されたという。その後、制度の必要性が再確認され、1885年には
(「せんばいとっきょじょうれい」がこうふされた。1959ねんにはぜんめんてきにかいせいされてげんこうほうに)
「専売特許条例」が公布された。1959年には全面的に改正されて現行法に
(いたっている。ぐたいてきにどんなじれいがいままでにあったのだろう。)
至っている。具体的にどんな事例が今までにあったのだろう。
(わたしたちがあたりまえのようにつかっているしょうひんにそれらをはっけんすることが)
わたしたちが当たり前のように使っている商品にそれらを発見することが
(できるので、ふだんからさがしてみるとおもしろいだろう。たとえばどりっぷこーひーの)
できるので、普段から探してみると面白いだろう。例えばドリップコーヒーの
(ふぃるたーがそれにあたるそうだ。じゅうらい、これをのむにはせんようのましんがひつようで)
フィルターがそれに当たるそうだ。従来、これを飲むには専用のマシンが必要で
など
(かんべんではないというもんだいがあった。そこで、ろかきをくみたてて)
簡便ではないという問題があった。そこで、ろ過器を組み立てて
(かっぷにせっちし、そこにねっとうをそそぐことでできあがるというこうぞうを)
カップに設置し、そこに熱湯を注ぐことで出来上がるという構造を
(かんがえだしたのだ。そのおかげで、てがるにほんかくてきなこーひーを)
考え出したのだ。そのおかげで、手軽に本格的なコーヒーを
(たのしめるようになった。また、たいたごはんをすくうさいにもちいるしゃもじは、)
楽しめるようになった。また、炊いたご飯をすくう際に用いるしゃもじは、
(じゅうらいのそざいはひょうめんがなめらかでおこめがふちゃくしやすくふべんだった。)
従来の素材は表面が滑らかでお米が付着しやすく不便だった。
(そこで、ひょうめんにでこぼこをもうけてとくしゅなかこうをほどこしたしょうひんをかいはつした。)
そこで、表面にでこぼこを設けて特殊な加工を施した商品を開発した。
(するとこのしょうひんはよくうれて、げんざいではあたりまえにあるものとして)
するとこの商品はよく売れて、現在では当たり前にあるものとして
(にんちされるようになった。このように、ひびのくらしのなかで、こまったてんを)
認知されるようになった。このように、日々の暮らしの中で、困った点を
(なんとかかいけつできないかといったようぼうにたいして、そのじつげんのためのほうほうを)
何とか解決できないかといった要望に対して、その実現のための方法を
(かんがえることがあらたなかいはつにつながっている。そして、これらをまもるせいどが)
考えることが新たな開発につながっている。そして、これらを守る制度が
(さんぎょうのはってんをささえていくのだろう。)
産業の発展を支えていくのだろう。








