【第124回】検定試験 初段
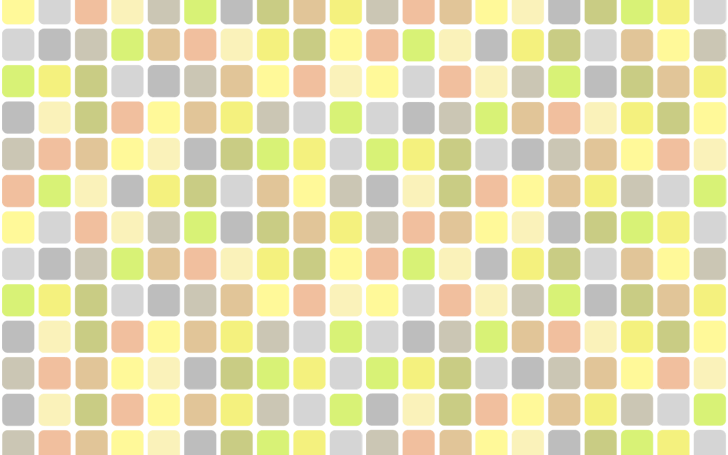
日本語ワープロ検定試験
第124回(令和2年10月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6471 | S | 7.0 | 91.9% | 317.1 | 2250 | 198 | 41 | 2026/01/30 |
| 2 | Taiga | 6435 | S | 6.6 | 96.8% | 339.2 | 2256 | 73 | 41 | 2025/12/30 |
| 3 | sss | 6166 | A++ | 6.4 | 95.2% | 346.7 | 2250 | 112 | 41 | 2026/02/06 |
関連タイピング
-
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
最後まで打てる?
プレイ回数226 歌詞かな336打 -
プレイ回数895 歌詞1350打
-
Mrs.GREEN APPLEの恋と吟です!
プレイ回数1224 歌詞860打 -
ビジネス文書作成のポイントについて。
プレイ回数8983 長文かな2166打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(げんごやねんれいのかきねなくたのしむことができるぶんかのひとつに、おんがくがある。)
言語や年齢の垣根なく楽しむことができる文化の一つに、音楽がある。
(そのれきしはゆうしいぜんにまでさかのぼり、)
その歴史は有史以前にまでさかのぼり、
(てびょうしなどのだがっきけいのりずむがきげんとなったとすいそくされる。)
手拍子などの打楽器系のリズムが起源となったと推測される。
(きゅうせっきじだいにはすでにそんざいしてせいかつのいちぶとなっていたことから、)
旧石器時代には既に存在して生活の一部となっていたことから、
(じんるいのこんげんてきなこうどうであるといえる。)
人類の根源的な行動であるといえる。
(きげんぜん3ぜんねんごろのえじぷとこおうこくじだいのへきがには、)
紀元前3千年ごろのエジプト古王国時代の壁画には、
(おんがくのばめんがえがかれており、)
音楽の場面が描かれており、
(ぎょうじやぎしきにはえんそうをするしゅうかんがあったとかんがえられる。)
行事や儀式には演奏をする習慣があったと考えられる。
(さらに、げんざいのがっきのげんけいとおもわれるものもはっくつされている。)
さらに、現在の楽器の原型と思われるものも発掘されている。
(にほんでも、じょうもんじだいにはそのそんざいがかくにんできる。)
日本でも、縄文時代にはその存在が確認できる。
(なかにはちょうせんはんとうやちゅうごくからわたってきたものもあった。)
中には朝鮮半島や中国から渡ってきたものもあった。
(かまくらやむろまちになると、こゆうのはってんをとげ、)
鎌倉や室町になると、固有の発展を遂げ、
(のうやきょうげんなどのげいのうにとりいれられていく。)
能や狂言などの芸能に取り入れられていく。
(やがて、たいしゅうかがすすむとかきねをこえてたしゅたようなぶんやがまざりあう。)
やがて、大衆化が進むと垣根を超えて多種多様な分野が混ざり合う。
(しょうわにはいるまではぶたいでたのしむのがしゅりゅうだったものが、)
昭和に入るまでは舞台で楽しむのが主流だった物が、
(れこーどやらじおなどのあたらしいぎじゅつがとうじょうしたことで、)
レコードやラジオなどの新しい技術が登場したことで、
(よりきがるにうけいれられるぶんかになり、いっきにひろまっていった。)
より気軽に受け入れられる文化になり、一気に広まっていった。
(りゅうこうかもうまれ、すきなかしゅのまねをするなど、)
流行歌も生まれ、好きな歌手の真似をするなど、
(のうどうてきにたのしまれるようになる。)
能動的に楽しまれるようになる。
(あるきょくをきくとそのとうじのことがおもいだされるといったように、)
ある曲を聴くとその当時のことが思い出されるといったように、
など
(ひとびとのせいかつにみっせつにかんけいしたそんざいとなっている。)
人々の生活に密接に関係した存在となっている。
(さらに、しょうわになるとからおけがとうじょうする。)
さらに、昭和になるとカラオケが登場する。
(がくだんによるなまえんそうではなく、)
楽団による生演奏ではなく、
(ろくおんされたきょくにあわせてまいくをかたてに)
録音された曲に合わせてマイクを片手に
(じぶんのこえをひろうするにほんはっしょうのごらくだ。)
自分の声を披露する日本発祥の娯楽だ。
(それまでいっていのひとしかけいけんできなかった、)
それまで一定の人しか経験できなかった、
(ひとまえでうたうというこういをだれもがきがるにたのしめるものにしてくれた。)
人前で歌うという行為を誰もが気軽に楽しめるものにしてくれた。
(いまやせかいじゅうであいされるようになり、ひとびとのひょうげんのはばをひろげたといえる。)
今や世界中で愛されるようになり、人々の表現の幅を広げたといえる。
(きく、うたう、えんそうするなどのこういはひかくてきふれやすいが、)
聴く、歌う、演奏するなどの行為は比較的触れやすいが、
(さっきょくとなるとそのはーどるはかくだんにあがるだろう。)
作曲となるとそのハードルは格段に上がるだろう。
(しかし、げんだいではさっきょくほじょそふとなどもたすうとうじょうし、いぜんよりみぢかになった。)
しかし、現代では作曲補助ソフトなども多数登場し、以前より身近になった。
(きんねんではじんこうちのうによってじどうてきにきょくをつくりだすというこころみもおこなわれている。)
近年では人工知能によって自動的に曲を作り出すという試みも行われている。
(かんかくでそうさくするものだとおもわれているが、)
感覚で創作するものだと思われているが、
(げんだいにいたるまでにぼうだいなりょうのきょくがつくられてきたことから、)
現代に至るまでに膨大な量の曲が作られてきたことから、
(ていばんがむすうにそんざいするせかいでもある。)
定番が無数に存在する世界でもある。
(じんるいはきょうまでこうちくやもほうをくりかえしてきたが、)
人類は今日まで構築や模倣を繰り返してきたが、
(あたらしいぎじゅつがそれをていりょうかしてすうちにおきかえることをかのうとした。)
新しい技術がそれを定量化して数値に置き換えることを可能とした。
(さらに、のうはをよみとってどんなおんがくがよいかはんだんして、)
さらに、脳波を読み取ってどんな音楽が良いか判断して、
(せんべつしたりさっきょくしたりするしくみもけんきゅうされている。)
選別したり作曲したりする仕組みも研究されている。
(せんもんてきなちしきがなくてもかんたんにふれることがかのうとなったげんだいでは、)
専門的な知識がなくても簡単に触れることが可能となった現代では、
(じんちをこえたあらたなぶんかがうまれていくかもしれない。)
人知を超えた新たな文化が生まれていくかもしれない。








