【第126回】検定試験 準1級
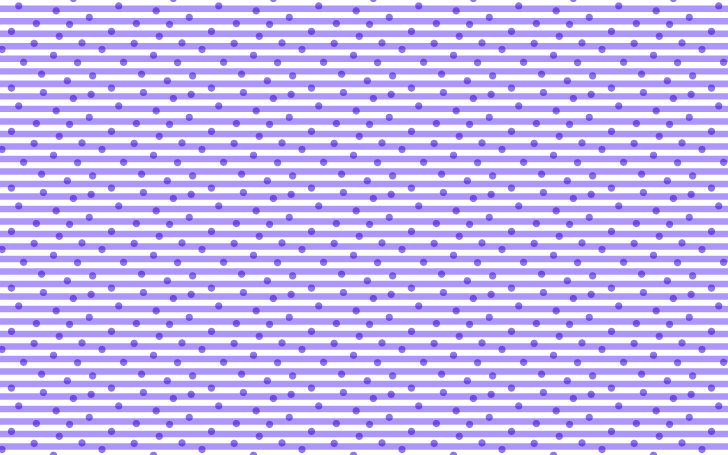
日本語ワープロ検定試験
第126回(令和3年2月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6311 | S | 7.0 | 90.4% | 268.4 | 1893 | 199 | 36 | 2026/01/30 |
| 2 | sss | 6236 | A++ | 6.5 | 95.1% | 287.2 | 1888 | 97 | 36 | 2026/02/07 |
関連タイピング
-
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
上級者向けタイピングゲームだよ
プレイ回数4.1万 長文かな822打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
Mrs.GREEN APPLEのツキマシテハです!
プレイ回数1194 歌詞かな775打 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
打ち切れたらギネス記録!?が好評だったのでつくりました!!
プレイ回数4658 歌詞444打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
タイピング練習に関する長文です
プレイ回数24万 長文1159打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(わたしたちにほんじんは、)
わたしたち日本人は、
(せかいにるいをみないほどのおふろずきだといわれています。)
世界に類を見ないほどのお風呂好きだといわれています。
(おんせんにんきはいうまでもありませんが、)
温泉人気は言うまでもありませんが、
(いえでもほとんどのひとがまいにちのようににゅうよくしているのではないでしょうか。)
家でもほとんどの人が毎日のように入浴しているのではないでしょうか。
(わたしたちにとっておふろは、)
わたしたちにとってお風呂は、
(からだをきれいにするだけでなく、)
体をきれいにするだけでなく、
(つかれをとってりふれっしゅさせるといったもくてきもあります。)
疲れを取ってリフレッシュさせるといった目的もあります。
(さらに、しゃこうのばとしてのやくわりもあるといえます。)
さらに、社交の場としての役割もあるといえます。
(よくそうのことをゆぶねとよぶことがありますが、)
浴槽のことを湯船と呼ぶことがありますが、
(なぜこのようによばれているのでしょう。)
なぜこのように呼ばれているのでしょう。
(これは、えどじだいにじっさいにあったかっきてきなびじねすがもとになっているようです。)
これは、江戸時代に実際にあった画期的なビジネスが基になっているようです。
(とうじのせんとうは、としぶにしゅうちゅうしており、)
当時の銭湯は、都市部に集中しており、
(こうがいにくらすひとびとは、なかなかかようことができませんでした。)
郊外に暮らす人々は、なかなか通うことができませんでした。
(そこで、おゆのはいったはこをつんだふねがうんがをめぐり、)
そこで、お湯の入った箱を積んだ船が運河を巡り、
(まちはずれにすむひとびとのためにせんとうのやくわりをはたしていたのです。)
町外れに住む人々のために銭湯の役割を果たしていたのです。
(これは、かわのみずをりようしていたためこすとがおさえられ、)
これは、川の水を利用していたためコストが抑えられ、
(かくやすではいることがかのうだったため、たくさんのひとびとにしたしまれたそうです。)
格安で入ることが可能だったため、たくさんの人々に親しまれたそうです。
(こうしたびじねすがなりたっていたのは、すいどうのせつびがまだまだふじゅうぶんで、)
こうしたビジネスが成り立っていたのは、水道の設備がまだまだ不十分で、
(まんせいてきにみずがふそくしていたことなどがえいきょうしていたといえます。)
慢性的に水が不足していたことなどが影響していたといえます。
(やがてじだいとともにかくかていにおふろがせっちされるようになると、)
やがて時代とともに各家庭にお風呂が設置されるようになると、
など
(そのかんしゅうはとだえ、ゆぶねということばだけがのこっていったのです。)
その慣習は途絶え、湯船という言葉だけが残っていったのです。
(にゅうよくのれきしはふるいようで、)
入浴の歴史は古いようで、
(6せいきにぶっきょうのでんらいとともにちゅうごくからつたわったといわれています。)
6世紀に仏教の伝来とともに中国から伝わったといわれています。
(しかしとうじは、げんざいのようなおゆにつかるすたいるではなく、)
しかし当時は、現在のようなお湯に浸かるスタイルではなく、
(じょうきでからだのよごれをうかせてあらいながすむしぶろがしゅりゅうでした。)
蒸気で体の汚れを浮かせて洗い流す蒸し風呂が主流でした。
(えどじだいのこうきになると、よくそうがとうじょうし、)
江戸時代の後期になると、浴槽が登場し、
(げんだいしきのにゅうよくがはじまったとされています。)
現代式の入浴が始まったとされています。
(そのころになると、ゆうふくなそうのひとびとは、じたくにせっちするようになります。)
その頃になると、裕福な層の人々は、自宅に設置するようになります。
(それでもまだせんとうがしゅりゅうのなか、たいしょうになると、)
それでもまだ銭湯が主流の中、大正になると、
(それまでもくせいであったあらいばなどはたいるちょうへとかいりょうされ、)
それまで木製であった洗い場などはタイル張へと改良され、
(えいせいめんにおいてもこうじょうしていきます。)
衛生面においても向上していきます。
(そしてしょうわにはいり、じゅうたくのしんかとともにじたくにおふろをもうけるひとがふえ、)
そして昭和に入り、住宅の進化とともに自宅にお風呂を設ける人が増え、
(たいしゅうよくじょうではなくいえでにゅうよくするぶんかがいっぱんかしていったのです。)
大衆浴場ではなく家で入浴する文化が一般化していったのです。
(げんざいでは、じぇっとばすやおんきょうせつびをそなえたものなど、)
現在では、ジェットバスや音響設備を備えたものなど、
(そのしゅるいやけいたいもたようかしています。)
その種類や形態も多様化しています。
(こんごもにほんのおふろぶんかは、さらにしんかしつづけるでしょう。)
今後も日本のお風呂文化は、さらに進化し続けるでしょう。








