【第126回】検定試験 初段
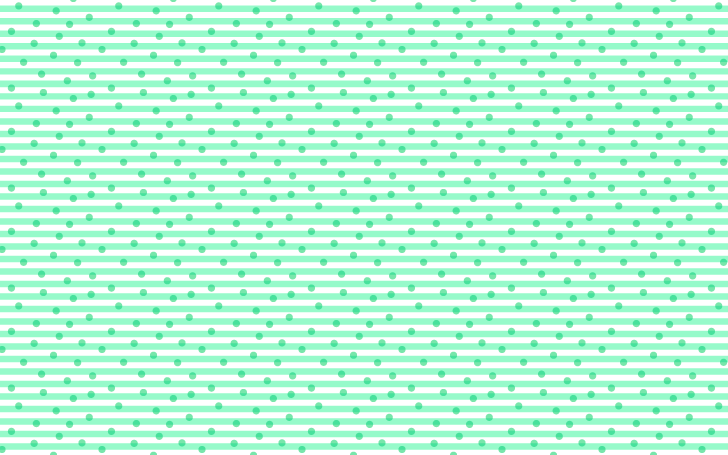
日本語ワープロ検定試験
第126回(令和3年2月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6514 | S+ | 7.0 | 93.0% | 307.6 | 2165 | 161 | 41 | 2026/01/31 |
| 2 | Taiga | 6387 | S | 6.6 | 96.2% | 325.5 | 2164 | 85 | 41 | 2025/12/30 |
| 3 | sss | 6146 | A++ | 6.4 | 95.4% | 334.5 | 2159 | 103 | 41 | 2026/02/07 |
| 4 | Tak | 5207 | B+ | 5.4 | 96.0% | 395.0 | 2146 | 89 | 41 | 2026/01/30 |
| 5 | nao@koya | 5078 | B+ | 5.2 | 97.0% | 414.1 | 2170 | 67 | 41 | 2026/02/22 |
関連タイピング
-
上級者向けタイピングゲームだよ
プレイ回数4.2万 長文かな822打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.6万 歌詞かな200打 -
コレ最後まで打てたらすごいと思う。(フル)
プレイ回数6149 歌詞120秒 -
仕事における情報処理スキルについて。
プレイ回数5003 長文かな2104打 -
打ち切れたら天才だ
プレイ回数270 長文540打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ほんをかおうとおもいたったとき、もちろんみせにでむけばこうにゅうできるし、)
本を買おうと思い立った時、もちろん店に出向けば購入できるし、
(いんたーねっとでかいものをすることもできる。)
インターネットで買い物をすることもできる。
(さらに、げんだいではでんししょせきというせんたくしもあり、)
さらに、現代では電子書籍という選択肢もあり、
(いえにいながらそのばでこうにゅうしてすぐによむことがかのうになった。)
家にいながらその場で購入してすぐに読むことが可能になった。
(しかし、すくなくともほんかくてきなしょうぎょうしゅっぱんがおこなわれるえどじだいいぜんでは、)
しかし、少なくとも本格的な商業出版が行われる江戸時代以前では、
(ほんをにゅうしゅすることはあんいではなかった。)
本を入手することは安易ではなかった。
(まず、いんさつのぎじゅつがはったつするまえはてでかきうつすしかなく、)
まず、印刷の技術が発達する前は手で書き写すしかなく、
(おおくのてまとじかんがかかり、かみやすみなどをよういするひつようもあった。)
多くの手間と時間がかかり、紙や墨などを用意する必要もあった。
(また、そのぜんていとしてげんぽんをたいよし、)
また、その前提として原本を貸与し、
(しょしゃをきょかしてくれるひとをみつけなければならない。)
書写を許可してくれる人を見つけなければならない。
(ゆうじんどうしならまだしも、)
友人同士ならまだしも、
(あかのたにんからかりるばあいにはきんせんのうけわたしがひつようになることもあった。)
赤の他人から借りる場合には金銭の受け渡しが必要になることもあった。
(げんざい、こてんのきょうかしょにけいさいされている「まんようしゅう」や「げんじものがたり」などのさくひんは、)
現在、古典の教科書に掲載されている「万葉集」や「源氏物語」などの作品は、
(しゃほんとしてつたわったもので、)
写本として伝わったもので、
(ちょしゃみずからがかいたげんぽんはみつかっていない。)
著者自らが書いた原本は見つかっていない。
(なぜひとびとはおおくのろうりょくやきんせんをくめんしてまでほんをもとめたのだろう。)
なぜ人々は多くの労力や金銭を工面してまで本を求めたのだろう。
(けんりょくしゃにとって、とうちのかんがえかたやぎじゅつをまなぶことは)
権力者にとって、統治の考え方や技術を学ぶことは
(せいじをおこなうためにひつようふかけつなことだった。)
政治を行うために必要不可欠なことだった。
(しゅうきょうやほうのちしきやぶんかのほとんどは、)
宗教や法の知識や文化のほとんどは、
(7せいきから9せいきにかけてちゅうごくからにほんにつたわったが、)
7世紀から9世紀にかけて中国から日本に伝わったが、
など
(じっさいにないようをしるためにはほんをみてりかいするひつようがあった。)
実際に内容を知るためには本を見て理解する必要があった。
(そのため、けんりょくのいじやせいじのうんえいにしんけつをそそぐちょうていのきぞくには、)
そのため、権力の維持や政治の運営に心血を注ぐ朝廷の貴族には、
(ひつじゅひんだったのだ。)
必需品だったのだ。
(さらに、ほんがきちょうだったこのじだい、)
さらに、本が貴重だったこの時代、
(しょもつをたすうしょぞうすることはちのたいけいをしょゆうすることであり、)
書物を多数所蔵することは知の体系を所有することであり、
(もっているだけでけんりょくのしょうちょうとなった。)
持っているだけで権力の象徴となった。
(またそうもどうようにこれをもとめた。)
また僧も同様にこれを求めた。
(にほんでぶっきょうをふかくまなぶには、)
日本で仏教を深く学ぶには、
(それがかかれたほんをよむいがいにほうほうがなかった。)
それが書かれた本を読む以外に方法がなかった。
(くうかいやさいちょうなど、ちゅうごくにわたったそうたちは、たすうのぶってんをにほんにもちかえった。)
空海や最澄など、中国に渡った僧たちは、多数の仏典を日本に持ち帰った。
(ぶしたちがけんりょくをにぎるようになると、とうちのぎじゅつがないことにきづいた。)
武士たちが権力を握るようになると、統治の技術がないことに気づいた。
(かれらは、じぶんたちではどくじのぶんかをつくることができず、)
彼らは、自分たちでは独自の文化を創ることができず、
(もっぱらくげのようしきをもほうすることでおおくをまなんだのである。)
専ら公家の様式を模倣することで多くを学んだのである。
(さきにのべたとおりしょもつをしょゆうすることはけんりょくのしょうちょうになるが、)
先に述べた通り書物を所有することは権力の象徴になるが、
(みずからつくりだすことができれば、)
自ら作り出すことができれば、
(それいじょうにたちばをきょうかし、かくちょうすることにつながる。)
それ以上に立場を強化し、拡張することにつながる。
(そのため、きぞくやぶしたちはほうやせいど、)
そのため、貴族や武士たちは法や制度、
(れきしやしそう、せいむやぎょうじなどについてみずからあらわした。)
歴史や思想、政務や行事などについて自ら著した。
(しょもつのせいさくは、それじたいがせいじてきなこういだったといえる。)
書物の制作は、それ自体が政治的な行為だったといえる。
(また、しそんによってけいしょうされたぞうしょは、)
また、子孫によって継承された蔵書は、
(いえのれきしをものがたるたいせつなしょうことなっていった。)
家の歴史を物語る大切な証拠となっていった。








