日本語 表現2
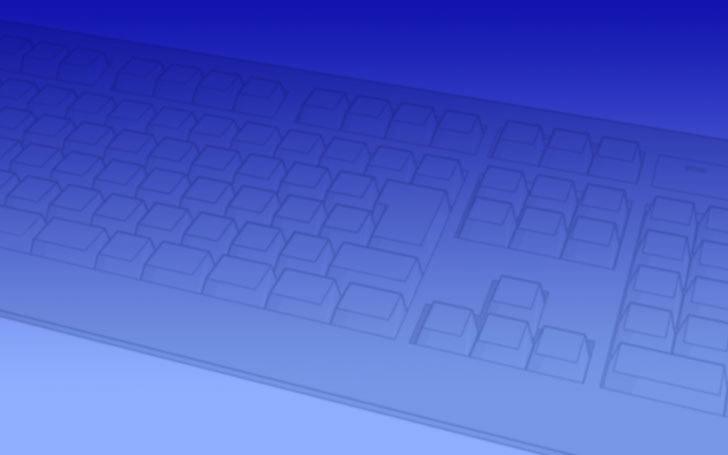
関連タイピング
-
プレイ回数493長文60秒
-
プレイ回数357長文かな60秒
-
プレイ回数264長文かな120秒
-
プレイ回数387長文かな120秒
-
プレイ回数429長文120秒
問題文
(はやおきはさんもんのとくはやおきすることはからだにもよくなにかととくすることがある)
早起きは三文の得 早起きすることは体にもよく何かと得することがある
(あとのまつりじきがはずれてもうなにのいみもなくなったこと)
後の祭り 時機が外れてもう何の意味もなくなったこと
(あぶらをうるむだばなしなどをしてしごとをさぼること)
油を売る 無駄話などをして仕事をサボること
(あめふってじかたまるじけんがおきたあとかえってじたいがあんていすること)
雨降って地固まる 事件が起きた後帰って自体が安定すること
(いきうまのめをぬくゆだんもすきもないこときわめてすばやくぬけめなくたちまわること)
生き馬の目を抜く 油断も隙もないこと極めて素早く抜け目なく立ち回ること
(いしのうえにもさんねんしんぼうすればむくいられる)
石の上にも三年 辛抱すれば報いられる
(いしばしをたたいてわたるようじんぶかくものごとをすすめていくこと)
石橋を叩いて渡る 用心深く物事を進めていくこと
(いしゃのふようじょうたにんのためばかりはたらいてじぶんのほうがおざなりになること)
医者の不養生 他人のためばかり働いて自分の方がおざなりになること
(いたちごっこりょうしゃがおなじことをくりかえし、けっちゃくがつかないこと)
いたちごっこ 両者が同じことを繰り返し、決着がつかないこと
(いのちあってのものだねいのちがなによりたいせつだということ)
命あっての物種 命が何より大切だということ
(うおごころあればみずごころあいてのきもちしだいでこちらもそれにおうじるきもちをもつ)
魚心あれば水心 相手の気持ち次第でこちらもそれに応じる気持ちを持つ
(うごのたけのこにたようなものがぞくぞくとでてくること)
雨後の筍 似たようなものが続々と出てくること
(しよりそだちにんげんとしてのせいちょうにはしゅっしんよりもきょういくやかんきょうがだいじだということ)
氏より育ち 人間としての成長には出身よりも教育や環境が大事だということ
(うそからでたまことうそのつもりでいったことが、あとでじじつになること)
嘘から出たまこと 嘘のつもりで行ったことが、後で事実になること
(えんのしたのちからもちめだたないところでくろうやどりょくをすること)
縁の下の力持ち 目立たないところで苦労や努力をすること
(おかめはちもくぼうかんしゃのほうがとうじしゃよりもものごとのよしあしやしんぎをせいかくにはんだんできる)
岡目八目 傍観者の方が当事者よりも物事の良し悪しや真偽を正確に判断できる
(かえるのこはかえるこはおやににる)
蛙の子は蛙 子は親に似る
(かわいいこにはたびをさせよしゃかいにだしてくろうさせたほうがそのこのためになる)
可愛い子には旅をさせよ 社会に出して苦労させた方がその子のためになる
(かんたんのゆめひとのよのえいこせいすいはゆめのようにはかないもの)
邯鄲の夢 人の世の栄枯盛衰は夢のように儚いもの
(さいおうがうまこうふこうはへんかがおおきく、よそくがつかないことのたとえ)
塞翁が馬 幸不幸は変化が大きく、予測がつかないことのたとえ
(きゆうよけいなことをあれこれおもいなやむこと。とりこしくろう)
杞憂 余計なことをあれこれ思い悩むこと。取り越し苦労
(くさいものにふたいやなことがそとにもれないように、いちじしのぎにかくすこと)
臭いものに蓋 嫌なことが外に漏れないように、一時しのぎに隠すこと
(くちはわざわいのもとふちゅういなはつげんはいざこざのげんいんになる)
口は災いの元 不注意な発言はいざこざの原因になる
(けがのこうみょうあやまってしたことがおもいもよらぬよいけっかをまねくこと)
怪我の功名 謝ってしたことが思いもよらぬ良い結果を招くこと
(げきりんにふれるめうえのひとをひどくいからせる)
逆鱗に触れる 目上の人をひどく怒らせる
(ごうにいってはごうにしたがえそのとちのしゅうかんにしたがってせいかつするのがいちばんよい)
業に行っては郷に従え その土地の習慣に従って生活するのが一番良い
(こうかいさきにたたずことがおわったあとであとでくやんでもなにもならない)
後悔先に立たず ことが終わった後で後で悔やんでも何もならない
(さるもきからおちるたつじんでもしっぱいはする)
猿も木から落ちる 達人でも失敗はする
(さんにんよればもんじゅのちえへいぼんなひとでもなんにんもあつまればすぐれたかんがえがうかぶ)
三人寄れば文殊の知恵 平凡な人でも何人も集まれば優れた考えが浮かぶ
(しょしんわするべからずものごとをはじめたときのしんけんなきもちをもちつづけること)
初心忘るべからず 物事を始めたときの真剣な気持ちを持ち続けること
(ずさんものごとのしかたがいいかげんなこと)
杜撰 物事の仕方がいい加減なこと
(たつとりあとをにごさずたちさるときごがみぐるしくないようにしまつする)
立つ鳥跡を濁さず 立ち去るとき後が見苦しくないように始末する
(たまにきずひじょうにりっぱなものにある、ほんのわずかなけってん)
玉に瑕 非常に立派なものにある、ほんのわずかな欠点
(とらのいをかりるきつねゆうりょくしゃのけんいをうしろだてにしていばること)
虎の威を借る狐 有力者の権威を後ろ盾にして威張ること
(とらのおをふむひじょうにあぶないことをするたとえ)
虎の尾を踏む 非常に危ないことをするたとえ
(とらぬたぬきのかわざんようあてにならないことをあてにしてけいさんしたり、きたいすること)
取らぬ狸の皮算用 あてにならないことをあてにして計算したり、期待すること
(なさけはひとのためならずひとにしんせつにしておけばめぐりめぐってじぶんによいむくいがある)
情けは人のためならず 人に親切にしておけば巡り巡って自分に良い報いがある
(なまびょうほうはおおけがのもとちゅうとはんぱなちしきやぎのうではしっぱいする)
生兵法は大怪我の元 中途半端な知識や技能では失敗する
(にそくのわらじふたつのたちばやしょくぎょうをひとりがかねること)
二足の草鞋 二つの立場や職業を一人が兼ねること
(にとをおうものいっともえずどうじにふたつのことをしてもけっきょくどちらもせいこうしない)
二兎を追うもの一兎も得ず 同時に二つのことをしても結局どちらも成功しない
(にばんせんじまえのくりかえしでもうどくじせいがないこ)
二番煎じ 前の繰り返しでもう独自性がないこ
(ねこにこばんきちょうなもののかちがわからないことのたとえ)
猫に小判 貴重なものの価値がわからないことのたとえ
(ねこのひたいとちなどがとてもせまいことのたとえ)
猫の額 土地などがとても狭いことのたとえ
(のどもとすぎればあつさわすれるくるしみもそのときさえすぎればすぐにわすれてしまう)
喉元過ぎれば熱さ忘れる 苦しみもその時さえ過ぎればすぐに忘れてしまう
(のれんにうでおしすこしもてごたえがないことのたとえ)
暖簾に腕押し 少しも手応えがないことのたとえ
(ひのないところにけむりはたたぬそれなりのこんきょやげんいんがとうわさはたたない)
火のないところに煙は立たぬ それなりの根拠や原因がと噂は立たない
(ひとつあなのむじなおなじたくらみにかんよしているもの)
一つ穴の狢 同じ企みに関与しているもの
(ふくすいぼんにかえらずいちどしてしまったことはとりかえしのつかないことのたとえ)
覆水盆に返らず 一度してしまったことは取り返しのつかないことのたとえ
(まいきょにいとまがないおおすぎてひとつひとつかぞえきれない)
枚挙にいとまがない 多すぎて一つ一つ数え切れない
(みからでたさびじぶんのしたことからうけるさいなん)
身から出た錆 自分のしたことから受ける災難
(みいらどりがみいらになるぎゃくにあいてがわにひきいれられること)
ミイラ取りがミイラになる 逆に相手側に引き入れられること
(むじゅんつじつまがあわないこと)
矛盾 つじつまが合わないこと
(もちはもちやものごとにはそれぞれのせんもんかがおり、しろうとにはとてもかなわないこと)
餅は餅屋 物事にはそれぞれの専門家がおり、素人にはとてもかなわないこと
(ようとうをかかげてくにくをうるひょうめんだけりっぱにみせかけて、じっしつがともなわないこと)
羊頭を掲げて狗肉を売る 表面だけ立派に見せかけて、実質がともなわないこと
(りかにかんむりをたださずうたがいをうけやすいことをするべきではない)
李下に冠を正さず 疑いを受けやすいことをするべきではない




