検定試験3級20
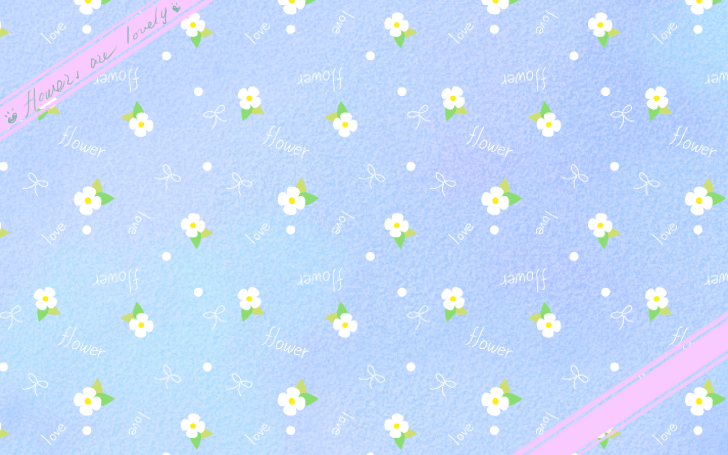
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 5964 | A+ | 6.5 | 92.2% | 191.3 | 1246 | 105 | 28 | 2026/01/12 |
関連タイピング
-
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
コレ最後まで打てたらすごいと思う。(フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
プレイ回数895 歌詞1348打
-
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数5848 歌詞120秒 -
これでー今年の運勢を占おう!
プレイ回数161 457打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
ビジネス文書作成のポイントについて。
プレイ回数8987 長文かな2166打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ひなまつりには、ちらしずしをたべます。)
ひな祭りには、ちらし寿司を食べます。
(このしゅうかんはどうしてできたのでしょうか。)
この習慣はどうしてできたのでしょうか。
(なにかれきしてきなはいけいやりゆうがあるのでしょうか。)
何か歴史的な背景や理由があるのでしょうか。
(むかしからのならわしやぎょうじのりょうりには)
昔からの習わしや行事の料理には
(ゆらいがつきものですが、)
由来が付きものですが、
(ひなまつりとちらしずしにはなんのつながりもありません。)
ひな祭りとちらし寿司には何のつながりもありません。
(しかし、うみやのやまのさちをいろとりどりにもりこんだはなやかなごはんは、)
しかし、海や野山の幸を色とりどりに盛り込んだ華やかなご飯は、
(まさにしょしゅんのおんなのこのおいわいにぴったりです。)
正に初春の女の子のお祝いにぴったりです。
(ちょうりにせんもんてきなぎじゅつがあまりひつようなく、)
調理に専門的な技術があまり必要なく、
(かていでかんたんにつくることができるため、)
家庭で簡単に作ることができるため、
(むかしからはれのひのてづくりりょうりとしてだされることがおおかったようです。)
昔から晴れの日の手作り料理として出されることが多かったようです。
(そして、そのるーつはえどじだいにおかやまはんでこうあんされた、)
そして、そのルーツは江戸時代に岡山藩で考案された、
(ばらずしだといわれています。)
ばら寿司だといわれています。
(ごはんにぐざいをまぜるというあいであがうまれたのは、)
ご飯に具材を混ぜるというアイデアが生まれたのは、
(とうじのはんしゅがおかずはひとつというけんやくれい)
当時の藩主がおかずは一つという倹約令
(「しょくぜんはいちじゅういっさいとする」というおふれを)
「食膳は一汁一菜とする」というおふれを
(だしたことがきっかけです。)
出したことがきっかけです。
(しょみんたちはこれにはんぱつして、)
庶民たちはこれに反発して、
(やくにんのめをごまかすためにすしめしのしたにごうかなぐをかくして、)
役人の目をごまかすために寿司飯の下に豪華な具を隠して、
(こっそりあじわうようになったのがはじまりといわれています。)
こっそり味わうようになったのが始まりといわれています。
など
(そのご、こうしたすたいるのばらずしはどんどんごうかになり)
その後、こうしたスタイルのばら寿司はどんどん豪華になり
(「すしいっしょう、きんいちりょう」といわれるほど、)
「寿司一升、金一両」といわれるほど、
(ぜいをつくしたものをつくらせるひとまであらわれるようになったそうです。)
贅を尽くしたものを作らせる人まで現れるようになったそうです。
(けんやくのためのおふれが、)
倹約のためのおふれが、
(かえってぜいたくなものをうんでしまったというのはひにくなものです。)
かえって贅沢なものを生んでしまったというのは皮肉なものです。
(ちなみにげんざい、きねんびとしてとうろくされている)
ちなみに現在、記念日として登録されている
(6がつ27にち「ちらしずしのひ」は、)
6月27日「ちらし寿司の日」は、
(おかずはひとつというおふれをだしたはんしゅのめいにちだそうです。)
おかずは一つというおふれを出した藩主の命日だそうです。







