有島武郎 或る女108
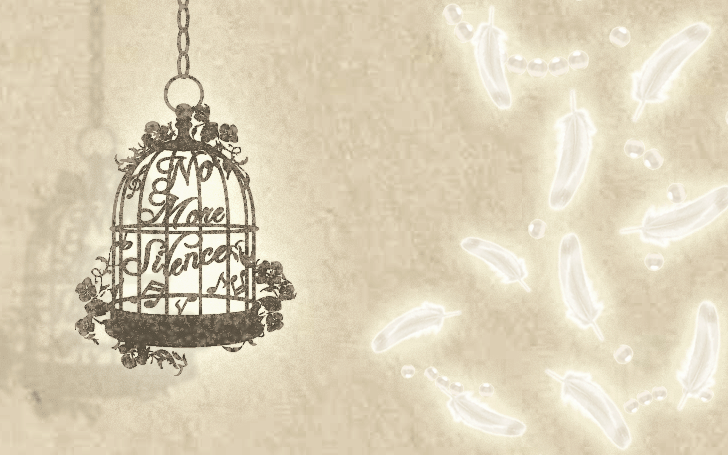
関連タイピング
-
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
AIが書いた文章です。
プレイ回数8712 長文1554打 -
目標:ミスタイプ50以下
プレイ回数18 長文2768打 -
初めての長文 第5弾
プレイ回数1.6万 長文1055打 -
すみません誤字がありました
プレイ回数1152 歌詞1348打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.6万 歌詞かな200打 -
M!LKのイイじゃん (フル)
プレイ回数6473 歌詞120秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ようこはさだよのねいきをうかがっていつものようにかがみをとりだした。)
葉子は貞世の寝息をうかがっていつものように鏡を取り出した。
(そしてかおをすこしでんとうのほうにふりむけてじっとじぶんをうつしてみた。)
そして顔を少し電灯のほうに振り向けてじっと自分を映して見た。
(おびただしいまいにちのぬけげでひたいぎわのいちじるしくすいてしまったのはだいいちに)
おびただしい毎日の抜け毛で額ぎわの著しく透いてしまったのは第一に
(きになった。すこしふりあおいでかおをうつすとほおのこけたのがさほどに)
気になった。少し振り仰いで顔を映すと頬のこけたのがさほどに
(めだたないけれども、あごをひいてしたうつむきになると、くちとみみとのあいだには)
目立たないけれども、顎を引いて下俯きになると、口と耳との間には
(たてにおおきなみぞのようなくぼみができて、かがくこつがめだって)
縦に大きな溝のような凹(くぼ)みができて、下顎骨が目立って
(いかめしくあらわれでていた。ながくみつめているうちにはだんだん)
いかめしく現われ出ていた。長く見つめているうちにはだんだん
(なれてきて、じぶんのいしきでしいてきょうせいするために、やせたかおも)
慣れて来て、自分の意識でしいて矯正するために、やせた顔も
(さほどとはおもわれなくなりだすが、ふとかがみにむかったしゅんかんには、)
さほどとは思われなくなり出すが、ふと鏡に向かった瞬間には、
(これがようこようことひとびとのめをそばだたしたじぶんかとおもうほどみにくかった。)
これが葉子葉子と人々の目をそばだたした自分かと思うほど醜かった。
(そうしてかがみにむかっているうちに、ようこはそのとうえいをじぶんいがいの)
そうして鏡に向かっているうちに、葉子はその投影を自分以外の
(あるたにんのかおではないかとうたがいだした。じぶんのかおよりうつるはずがない。)
ある他人の顔ではないかと疑い出した。自分の顔より映るはずがない。
(それだのにそこにうつっているのはたしかにだれかみもしらぬひとのかおだ。)
それだのにそこに映っているのは確かにだれか見も知らぬ人の顔だ。
(くつうにしいたげられ、あくいにゆがめられ、ぼんのうのためにしりめつれつになった)
苦痛にしいたげられ、悪意にゆがめられ、煩悩のために支離滅裂になった
(もうじゃのかお・・・ようこはせすじにいっときにこおりをあてられたようになって、)
亡者の顔・・・葉子は背筋に一時に氷をあてられたようになって、
(みぶるいしながらおもわずかがみをてからおとした。)
身ぶるいしながら思わず鏡を手から落とした。
(きんぞくのゆかにふれるおとがかみなりのようにひびいた。ようこはあわててさだよをみやった。)
金属の床に触れる音が雷のように響いた。葉子はあわてて貞世を見やった。
(さだよはまっかにじゅうけつしてねつのこもっためをまんじりとひらいて、)
貞世はまっ赤に充血して熱のこもった目をまんじりと開いて、
(さもふしぎそうにちゅううをみやっていた。)
さも不思議そうに中有を見やっていた。
(「あいねえさん・・・とおくでぴすとるのおとがしたようよ」)
「愛ねえさん・・・遠くでピストルの音がしたようよ」
など
(はっきりしたこえでこういったので、ようこがかおをちかよせてなにかいおうと)
はっきりした声でこういったので、葉子が顔を近寄せて何かいおうと
(するとこんこんとしてたわいもなくまたねむりにおちいるのだった。)
すると昏々としてたわいもなくまた眠りにおちいるのだった。
(さだよのねむるのとともに、なんともいえないぶきみなしのおびやかしがそつぜんとして)
貞世の眠るのと共に、何ともいえない不気味な死の脅かしが卒然として
(ようこをおそった。へやのなかにはそこらじゅうにしのかげがみちみちていた。)
葉子を襲った。部屋の中にはそこらじゅうに死の影が満ち満ちていた。
(めのまえのこおりみずをいれたこっぷひとつもつぎのしゅんかんにはひとりでにたおれて)
目の前の氷水を入れたコップ一つも次の瞬間にはひとりでに倒れて
(こわれてしまいそうにみえた。もののかげになってうすぐらいぶぶんはみるみる)
こわれてしまいそうに見えた。物の影になって薄暗い部分は見る見る
(へやじゅうにひろがって、すべてをつめたくくらくつつみおわるかともうたがわれた。)
部屋じゅうに広がって、すべてを冷たく暗く包み終わるかとも疑われた。
(しのかげはもっともこくさだよのめとくちのまわりにあつまっていた。そこにはしが)
死の影は最も濃く貞世の目と口のまわりに集まっていた。そこには死が
(うじのようににょろにょろとうごめいているのがみえた。それよりも・・・)
蛆のようににょろにょろとうごめいているのが見えた。それよりも・・・
(それよりもそのかげはそろそろとようこをめがけてしほうのかべからあつまり)
それよりもその影はそろそろと葉子を目がけて四方の壁から集まり
(ちかづこうとひしめいているのだ。ようこはほとんどそのしのすがたをみるように)
近づこうとひしめいているのだ。葉子はほとんどその死の姿を見るように
(おもった。あたまのなかがしーんとひえとおってさえきったさむさがぞくぞくと)
思った。頭の中がシーンと冷え通って冴えきった寒さがぞくぞくと
(ししをふるわした。)
四肢を震わした。
(そのときしゅくちょくしつのかけどけいがとおくのほうでいちじをうった。)
その時宿直室の掛け時計が遠くのほうで一時を打った。
(もしこのおとをきかなかったら、ようこはおそろしさのあまりじぶんのほうから)
もしこの音を聞かなかったら、葉子は恐ろしさのあまり自分のほうから
(しゅくちょくしつへかけこんでいったかもしれなかった。ようこはおびえながらみみを)
宿直室へ駆け込んで行ったかもしれなかった。葉子はおびえながら耳を
(そばだてた。しゅくちょくしつのほうからかんごふがぞうりをばたばたとひきずってくる)
そばだてた。宿直室のほうから看護婦が草履をばたばたと引きずって来る
(おとがきこえた。ようこはほっといきをついた。そしてあわてるようにみを)
音が聞こえた。葉子はほっと息をついた。そしてあわてるように身を
(うごかして、さだよのあたまのひょうのうのとけぐあいをしらべてみたり、かいまきをととのえて)
動かして、貞世の頭の氷嚢の溶け具合をしらべて見たり、搔巻を整えて
(やったりした。うみのそこにひとつしずんでぎらっとひかるかいがらのように、)
やったりした。海の底に一つ沈んでぎらっと光る貝殻のように、
(ゆかのうえでかげのなかにものすごくよこたわっているかがみをとりあげてふところに)
床の上で影の中に物すごく横たわっている鏡を取り上げてふところに
(いれた。そうしていっしついっしつとちかづいてくるかんごふのあしおとにみみをすましながら)
入れた。そうして一室一室と近づいて来る看護婦の足音に耳を澄ましながら
(またかんがえつづけた。)
また考え続けた。
(こんどはさんないのいえのありさまがさながらまざまざとめに)
今度は山内(さんない)の家のありさまがさながらまざまざと目に
(みるようにそうぞうされた。おかがよふけにそこをおとずれたときにはくらちがたしかに)
見るように想像された。岡が夜ふけにそこを訪れた時には倉地が確かに
(いたにちがいない。そしていつものとおりいっしゅのねばりづよさをもってようこの)
いたに違いない。そしていつものとおり一種の粘り強さを持って葉子の
(ことづてをとりつぐおかにたいして、はげしいことばでそのりふじんなきょうきじみた)
言伝てを取り次ぐ岡に対して、激しい言葉でその理不尽な狂気じみた
(ようこのできごころをののしったにちがいない。くらちとおかとのあいだにはあんあんりに)
葉子の出来心をののしったに違いない。倉地と岡との間には暗々裏に
(あいこにたいするこころのそうとうがおこなわれたろう。おかのさしだすしへいのたばを)
愛子に対する心の争闘が行われたろう。岡の差し出す紙幣の束を
(いかりにまかせてたたみのうえにたたきつけるくらちのいたけだかなようす、しょうじょには)
怒りに任せて畳の上にたたきつける倉地の威丈高な様子、少女には
(ありえないほどのれいせいさでひとごとのようにふたりのあいだの)
あり得ないほどの冷静さで他人事(ひとごと)のように二人の間の
(いきさつをふしめながらにみまもるあいこのいっしゅのどくどくしいようえんさ。)
いきさつを伏し目ながらに見守る愛子の一種の毒々しい妖艶さ。
(そういうすがたがさながらめのまえにうかんでみえた。ふだんのようこだったら)
そういう姿がさながら目の前に浮かんで見えた。ふだんの葉子だったら
(そのそうぞうはようこをそのばにいるようにこうふんさせていたであろう。けれども)
その想像は葉子をその場にいるように興奮させていたであろう。けれども
(しのきょうふにはげしくおそわれたようこはなんともいえないけんおのじょうをもってのほかには)
死の恐怖に激しく襲われた葉子はなんともいえない嫌悪の情をもってのほかには
(そのばめんをそうぞうすることができなかった。)
その場面を想像する事ができなかった。
(なんというあさましいひとのこころだろう。)
なんというあさましい人の心だろう。
(けっきょくはなにもかもほろびていくのに、えいえんなはいいろのちんもくのなかにくずれこんで)
結局は何もかも滅びて行くのに、永遠な灰色の沈黙の中にくずれ込んで
(しまうのに、もくぜんのどんらんにしんかのかぎりをもやして、がきどうようにいのちを)
しまうのに、目前の貪婪に心火の限りを燃やして、餓鬼同様に命を
(かみあうとはなんというあさましいこころだろう。しかもそのみにくいあらそいの)
かみ合うとはなんというあさましい心だろう。しかもその醜い争いの
(たねをまいたのはようこじしんなのだ。そうおもうとようこはじぶんのこころと)
種子(たね)をまいたのは葉子自身なのだ。そう思うと葉子は自分の心と
(にくたいとがさながらうじむしのようにきたなくみえた。・・・なんのために)
肉体とがさながら蛆虫のようにきたなく見えた。・・・何のために
(いままであってないようなもうしゅうにくるしみぬいてそれをせいめいそのもののように)
今まであってないような妄執に苦しみ抜いてそれを生命そのもののように
(だいじにかんがえぬいていたことか。それはまるでさだよがしじゅうみているらしい)
大事に考え抜いていた事か。それはまるで貞世が始終見ているらしい
(あくむのひとつよりもさらにはかないものではないか。・・・こうなると)
悪夢の一つよりもさらにはかないものではないか。・・・こうなると
(くらちさえがえんもゆかりもないもののようにとおくかんがえられだした。)
倉地さえが縁もゆかりもないもののように遠く考えられ出した。
(ようこはすべてのもののむなしさにあきれたようなめをあげていまさららしく)
葉子はすべてのもののむなしさにあきれたような目をあげて今さららしく
(へやのなかをながめまわした。なんのかざりもない、しゅうどういんのないぶのような)
部屋の中をながめ回した。なんの飾りもない、修道院の内部のような
(はだかなしつないがかえってすがすがしくみえた。おかののこしたさだよのまくらもとの)
裸な室内がかえってすがすがしく見えた。岡の残した貞世の枕もとの
(はなたばだけが、そしておそらくは(じぶんではみえないけれども)これほどの)
花束だけが、そしておそらくは(自分では見えないけれども)これほどの
(いそがしさのあいだにもじぶんをふんしょくするのをわすれずにいるようこじしんがいかにも)
忙しさの間にも自分を粉飾するのを忘れずにいる葉子自身がいかにも
(ふはくなたよりないものだった。ようこはこうしたこころになると、ねつに)
浮薄なたよりないものだった。葉子はこうした心になると、熱に
(うかされながらいっぽいっぽなんのこころのわだかまりもなくしにちかづいていく)
浮かされながら一歩一歩なんの心のわだかまりもなく死に近づいて行く
(さだよのかおがこうごうしいものにさえみえた。ようこはいのるようなわびるようなこころで)
貞世の顔が神々しいものにさえ見えた。葉子は祈るようなわびるような心で
(しみじみとさだよをみいった。)
しみじみと貞世を見入った。
(やがてかんごふがさだよのへやにはいってきた。けいしきいっぺんのおじぎを)
やがて看護婦が貞世の部屋にはいって来た。形式一ぺんのお辞儀を
(ねむそうにして、しんだいのそばにちかよると、むとんじゃくなふうに)
睡そうにして、寝台のそばに近寄ると、
無頓着(むとんじゃく)なふうに
(ようこがいれておいたけんおんきをだしてひにすかしてみてから、むねのひょうのうを)
葉子が入れておいた検温器を出して灯にすかして見てから、胸の氷嚢を
(とりかえにかかった。ようこはじぶんひとりのてでそんなことをしてやりたいような)
取りかえにかかった。葉子は自分一人の手でそんな事をしてやりたいような
(あいちゃくとしんせいさとをさだよにかんじながらかんごふをてつだった。)
愛着と神聖さとを貞世に感じながら看護婦を手伝った。
(「さあちゃん・・・さ、ひょうのうをとりかえますからね・・・」)
「貞(さあ)ちゃん・・・さ、氷嚢を取りかえますからね・・・」
(とやさしくいうと、うわごとをいいつづけていながらやはりさだよはそれまで)
とやさしくいうと、譫言をいい続けていながらやはり貞世はそれまで
(ねむっていたらしく、いたいたしいまでおおきくなっためをひらいて、まじまじと)
眠っていたらしく、痛々しいまで大きくなった目を開いて、まじまじと
(いがいなひとでもみるようにようこをみるのだった。)
意外な人でも見るように葉子を見るのだった。








