中学歴史2古墳時代
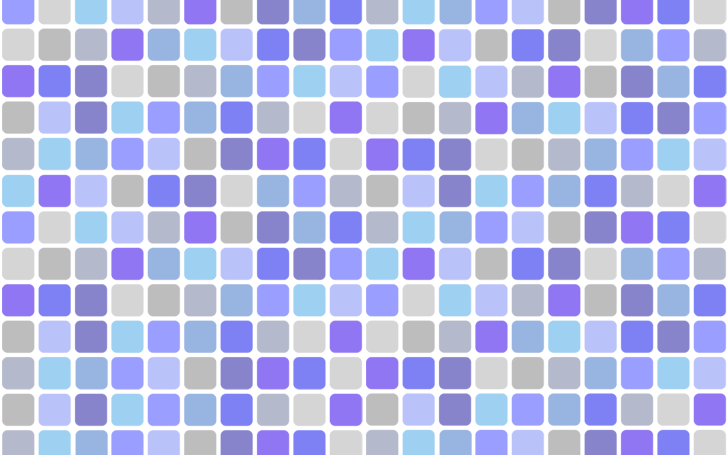
関連タイピング
-
速ければ速いほど強い世界
プレイ回数794万 短文かな87打 -
僕が初めて作ったタイピングゲームです。
プレイ回数1055 180秒 -
何秒で全部打てるか挑戦してみよう!
プレイ回数439万 短文かな298打 -
簡単な短文タイピングです。
プレイ回数18万 かな60秒 -
プレイ回数2.6万 短文かな60秒
-
メジャーな国からマイナーな国まで幅広くピックアップ!
プレイ回数16万 60秒 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒 -
よく使われる四文字熟語をピックアップしてみました
プレイ回数20万 かな60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(こふんじだい)
古墳時代
(こふんじだいは、3せいきこうはんから6せいきまつごろまでつづいた。)
古墳時代は、3世紀後半から6世紀末ごろまで続いた。
(こふんとは、おうやかくちのごうぞくのはかのこと。)
古墳とは、王や各地の豪族の墓のこと。
(こふんのふんきゅうじょうには、やきもののはにわ(はにわ)がおかれた。)
古墳の墳丘上には、焼き物のはにわ(埴輪)がおかれた。
(いえ、ひと、どうぶつなどさまざまなけいじょうのはにわがある。)
家、人、動物などさまざまな形状のはにわがある。
(やまとせいけん(やまとおうけん)~こふんじだいの3せいきこうはんごろ。)
大和政権(ヤマト王権)~古墳時代の3世紀後半ごろ。
(ゆうりょくなごうぞくがれんごうしたやまとせいけん(やまとおうけん)がならぼんちにせいりつした。)
有力な豪族が連合した大和政権(ヤマト王権)が奈良盆地に成立した。
(やまとせいけんのおうのことをおおきみといいます。)
大和政権の王のことを大王といいます。
(たいりくとのこうりゅう)
大陸との交流
(こふんじだいには、たいりくとのこうりゅうもさかんになった。)
古墳時代には、大陸との交流もさかんになった。
(ちゅうごくやちょうせんはんとうからにほんにうつりすんだひとびとをとらいじんという。)
中国や朝鮮半島から日本に移り住んだ人々を渡来人という。
(とらいじんによって、にほんにさまざまなぶんぶつやぶんかがつたわった。)
渡来人によって、日本にさまざまな文物や文化が伝わった。
(たとえば、すえきやかんじ、じゅがく(じゅきょう)、ぶっきょうなど。)
例えば、須恵器や漢字、儒学(儒教)、仏教など。
(すえきは、こうおんでやいたどき。)
須恵器は、高温で焼いた土器。
(かたく、くろっぽいいろ(こいはいいろ)をしている。)
かたく、黒っぽい色(こい灰色)をしている。
(ちょうせんはんとうのくだらというくにからは、かんじ、じゅがく(じゅきょう)、ぶっきょうがつたわった。)
朝鮮半島の百済という国からは、漢字、儒学(儒教)、仏教が伝わった。
(にほんとくだらはゆうこうかんけいにあった。)
日本と百済は友好関係にあった。








