第44回 速度問題 2級
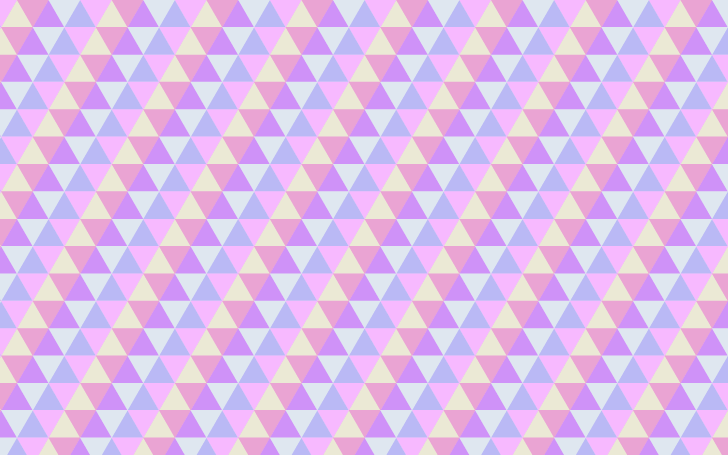
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiga | 6846 | S++ | 6.9 | 98.2% | 139.2 | 970 | 17 | 23 | 2025/12/28 |
| 2 | maro | 6536 | S+ | 6.7 | 96.8% | 146.1 | 987 | 32 | 23 | 2026/01/09 |
| 3 | PLMKJNB4 | 6249 | A++ | 6.7 | 93.3% | 144.5 | 972 | 69 | 23 | 2026/02/01 |
| 4 | ku- | 5789 | A+ | 5.9 | 97.5% | 161.5 | 959 | 24 | 23 | 2025/12/28 |
| 5 | nao@koya | 4989 | B | 5.0 | 98.3% | 192.0 | 974 | 16 | 23 | 2025/12/28 |
関連タイピング
-
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
GReeeeNのキセキです。
プレイ回数3672 歌詞1426打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
ビジネス文書作成のポイントについて。
プレイ回数8983 長文かな2166打 -
最後まで打てる?
プレイ回数226 歌詞かな336打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
上級者向けタイピングゲームだよ
プレイ回数4.1万 長文かな822打 -
プレイ回数895 歌詞1350打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(おおくのにほんじんは、たんにおちゃといえばりょくちゃをいめーじする。)
多くの日本人は、単にお茶といえば緑茶をイメージする。
(また、こうちゃはあかみをおびている。)
また、紅茶は赤みを帯びている。
(この「ちゃ」というかんじはつちのようないろもいみするが、)
この「茶」という漢字は土のような色も意味するが、
(のみものをまえにしてそのぎゃっぷをいしきするひとはすくないだろう。)
飲み物を前にしてそのギャップを意識する人は少ないだろう。
(ちゃいろというなまえがつかわれたのはいがいにふるく、)
茶色という名前が使われたのは意外に古く、
(へいあんじだいのしょもつにはすでにそんざいしていた。)
平安時代の書物にはすでに存在していた。
(ぬのじのせんしょくににだしたしるがしようされたため、)
布地の染色に煮出した汁が使用されたため、
(とうじはまだきちょうなおちゃをのむひとはすくなくても、)
当時はまだ貴重なお茶を飲む人は少なくても、
(そのなまえがふきゅうすることになった。)
その名前が普及することになった。
(つまり、とうじのまれていたはのいろは、)
つまり、当時飲まれていた葉の色は、
(ちゃいろだったということである。)
茶色だったということである。
(えどじだいのちゅうきにあたらしいかこうほうほうがひろまると、)
江戸時代の中期に新しい加工方法が広まると、
(おちゃはみどりいろにへんかした。)
お茶は緑色に変化した。
(しかし、すでににちじょうさはんじということばがいっぱんてきになるほど、)
しかし、すでに日常茶飯事という言葉が一般的になるほど、
(おちゃはしょみんにのまれ、いろのなまえもていちゃくしていた。)
お茶は庶民に飲まれ、色の名前も定着していた。
(そのむじゅんはそのごもへんかしないで、)
その矛盾はその後も変化しないで、
(げんだいまでdnaのようにうけつがれている。)
現代までDNAのように受け継がれている。
(このようにいちどていちゃくしたなまえやしゅうかんは、じだいがかわっても、)
このように一度定着した名前や習慣は、時代が変わっても、
(せだいをこえてそのままでんしょうされることがおおい。)
世代を超えてそのまま伝承されることが多い。
(そのなかには、さまざまなけいいやできごとがおりこまれ、)
その中には、様々な経緯や出来事が織り込まれ、
など
(のこっているかのうせいがある。)
残っている可能性がある。
(ちいさなぎもんでもしらべていくと、)
小さな疑問でも調べていくと、
(いがいなじじつにめぐりあえるかもしれない。)
意外な事実に巡り会えるかもしれない。








