軍用鼠1 海野十三
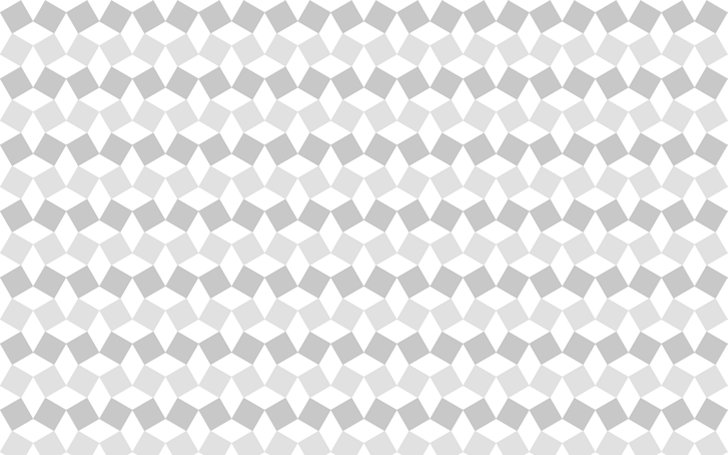
軍用鼠/海野十三 著
青空文庫より引用
青空文庫より引用
関連タイピング
-
コレ最後まで打てたらすごいと思う。(フル)
プレイ回数6246 歌詞120秒 -
長文を打つ練習ができます。
プレイ回数36万 長文786打 -
AIで作成。
プレイ回数139 長文1683打 -
初心者の方、暇ならプレイしてみて!
プレイ回数36万 496打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.7万 歌詞かな200打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
SEKAI NO OWARIさんのDragonNightです!!
プレイ回数40 歌詞60秒 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(たんていしょうせつかのうめのじゅうごは、つくえのうえにげんこうようしをのべて、いきはなはだしょうちんして)
探偵小説家の梅野十伍は、机の上に原稿用紙を展べて、意気甚だ銷沈して
(いた。たなのとけいをみると、ししんはにじじゅうごふんをさしていた。それはごごのにじ)
いた。棚の時計を見ると、指針は二時十五分を指していた。それは午後の二時
(ではなくて、ごぜんのにじであった。かーてんをかかげてそとをみると、すとーぶの)
ではなくて、午前の二時であった。カーテンをかかげて外を見ると、ストーブの
(あたたかみであせをかいたがらすどをとおして、まるでしんかいのそこのようにあやめもわかぬ)
温か味で汗をかいた硝子戸を透して、まるで深海の底のように黒目も弁かぬ
(まっくらやみがかれをとじこめていることがわかった。もうすうじかんすればよるが)
真暗闇が彼を閉じこめていることが分った。もう数時間すれば夜が
(あけるであろう。するとまどのそともあかるくなって、でんしゃがちん.ちんうごきだす)
明けるであろう。すると窓の外も明るくなって、電車がチン.チン動きだす
(ことであろう。するとそのでんしゃから、ひとりのつめえりすがたのじっちょくなしょうねんがおりてきて、)
ことであろう。するとその電車から、一人の詰襟姿の実直な少年が下りてきて、
(ほちょうをととのえてもんのなかへはいってくるだろう。そしてげんかんわきのおしぼたんをしょうねんの)
歩調を整えて門のなかへ入ってくるだろう。そして玄関脇の押し釦を少年の
(ゆびさきがおすと、おくのまのべるがかまびすしくじじーんとなるであろう。うめのじゅうごは)
指先が押すと、奥の間のベルが喧しくジジーンと鳴るであろう。梅野十伍は
(そのべるのねをきいたしゅんかんにかならずやしんぞうまひをおこし、てつやのつくえのうえに)
そのベルの音を聞いた瞬間に必ずや心臓麻痺を起し、徹夜の机の上に
(ぶったおれてあえなくなるにちがいないとおもっているのである。げんこうしのうえには、)
ぶったおれてあえなくなるに違いないと思っているのである。原稿紙の上には、
(ただのいちぎょうはんくもしたためてないのである。まったくのぶらんくである。うえのいちまいの)
ただの一行半句も認めてないのである。全くのブランクである。上の一枚の
(げんこうようしがそうであるばかりではなく、そのしたのいちまいももうひとつしたのいちまいも、)
原稿用紙がそうであるばかりではなく、その下の一枚ももう一つ下の一枚も、
(いやいえじゅうのかみをさがしてみてもただのいちじだってかいてないのである。それだのに、)
いや家中の紙を探してみても只の一字だって書いてないのである。それだのに、
(あさになると、かならずつめえりのしょうねんが、じのかいてあるげんこうしをとりにくるのである。)
朝になると、必ず詰襟の少年が、字の書いてある原稿紙を取りに来るのである。
(しょうねんはうめのじゅうごのにょうぼうにうやうやしくけいれいをして、きっとこんなふうにいうに)
少年は梅野十伍の女房に恭々しく敬礼をして、きっとこんな風に云うに
(ちがいない。「ええ、てまえはたんていしょうせつせんもんざっし「しんたんてい」へんしゅうきょくのつかいのもので)
違いない。「ええ、手前は探偵小説専門雑誌『新探偵』編集局の使いの者で
(ございます。おやくそくのせんせいのげんこうをいただきにまいりました、はい」)
ございます。御約束のセンセイの原稿を頂きにまいりました、ハイ」
(ーーそれをかんがえるとうめのじゅうごはじぶんのかおのまえできょくばだんのうえたるらいおんに)
ーーそれを考えると梅野十伍は自分の顔の前で曲馬団の飢えたるライオンに
(ぴんくいろのうらのついたおおきなくちをかーっとひらかれたようなきょうふをかんずるので)
ピンク色の裏のついた大きな口をカーッと開かれたような恐怖を感ずるので
など
(あった。じつにせんりつすべきことではある。なぜかれは、げんこうようしのますめのなかに)
あった。実に戦慄すべきことではある。なぜ彼は、原稿用紙の桝目のなかに
(いちじもはんかくもかけないのであるか。そしてどくがすのしけんだいにさいようされたしゅうじんの)
一字も半画も書けないのであるか。そして毒瓦斯の試験台に採用された囚人の
(ように、いきはなはだしょうちんしているのであるか。これにはむろんわけがあった。)
ように、意気甚だ銷沈しているのであるか。これには無論ワケがあった。
(わけなくしてものごとというものはけっかがありえない。じつはこのごろ)
ワケなくして物事というものは結果が有り得ない。実はこのごろ
(うめのじゅうごにとってなにがおそろしいといって、たんていしょうせつをかくほどおそろしいことは)
梅野十伍にとって何が恐ろしいといって、探偵小説を書くほど恐ろしいことは
(ないのであった。こんげつかれがひとつのたんていしょうせつをはっぴょうすれば、このよくげつには)
ないのであった。今月彼が一つの探偵小説を発表すれば、この翌月には
(そのしょうせつが、すくなくともじっかしょのひひょうだいのうえにのぼらされ、そこでそれぞれ)
その小説が、すくなくとも十ヶ所の批評台の上にのぼらされ、そこでそれぞれ
(しっこうにんのおもいおもいのしゅみによって、ぎゃくさつされなければならなかった。)
執行人の思い思いの趣味によって、虐殺されなければならなかった。
(もしこれがにんげんぎゃくさつのばあいだったら、もっとらくなはずだった。なぜならにんげんの)
もしこれが人間虐殺の場合だったら、もっと楽な筈だった。なぜなら人間の
(せいめいはひとつであるから、いっぺんさしころされればそれでしゅうきょくであって、そのあと)
生命は一つであるから、一遍刺し殺されればそれで終局であって、その後
(にどもさんどもかさねてころされなおさぬでもよい。ところが、しょうせつぎゃくさつのばあいは)
二度も三度も重ねて殺され直さぬでもよい。ところが、小説虐殺の場合は
(じっぺんでもにじっぺんでもひったてられていってはねんいりのぎゃくさつをうけるのであるから、)
十遍でも二十遍でも引立てられていっては念入の虐殺をうけるのであるから、
(たまったものではない、もっともいくたびころされてもしゅうねんぶかくいきかわるので)
たまったものではない、尤もいくたび殺されても執念深く生き換わるので
(あるから、しっこうにんのほうでもごうをにやすのであろうが。しっこうにんのおおくは、)
あるから、執行人の方でも業を煮やすのであろうが。執行人の多くは、
(いろいろなしきさいにわかれているにしてもいずれもたんていしょうせつしじょうろんじゃであって、)
いろいろな色彩に分れているにしてもいずれも探偵小説至上論者であって、
(しんはっぴょうのたんていしょうせつはじゅうらいかつてなかりしこうとうてきのものならざるべからずと)
新発表の探偵小説は従来曾て無かりし高踏的のものならざるべからずと
(さけんでいる。だからいやしくもじゅうらいのだれかのたんていしょうせつがしめしたさいこうれべるにくらべて)
叫んでいる。だから苟も従来の誰かの探偵小説が示した最高レベルに較べて
(じょうとうでないたんていしょうせつをはっぴょうしようものなら、それはうえたるらいおんのまえに)
上等でない探偵小説を発表しようものなら、それは飢えたるライオンの前に
(うさぎをはなつにひとしいけっかとなる。だからぼんくらさっかのうめのじゅうごなどはいつも)
兎を放つに等しい結果となる。だからボンクラ作家の梅野十伍などはいつも
(ひがいざいりょうばかりていきょうしているようなものであった。ーーと、かれはかけない)
被害材料ばかり提供しているようなものであった。ーーと、彼は書けない
(わけを、こんなところにおしつけているのだった。しかし、がんらい、かれは)
ワケを、こんなところに押しつけているのだった。しかし、元来、彼は
(うまれつきのひがいもうそうかそうしょうであったから、どこまでほんきでこれをかけないわけに)
生れつきの被害妄想仮装症であったから、どこまで本気でこれを書けないワケに
(かんさんしているのかわからなかった。じつをいえば、かれにはもっとこころあたりの)
換算しているのか分らなかった。実をいえば、彼にはもっと心当りの
(かけないわけをもっていたのである。それはぶちまけたはなし、かれはもうたんていしょうせつの)
書けないワケを持っていたのである。それはブチまけた話、彼はもう探偵小説の
(ねたをただのひとつももちあわせていなかったのである。さきごろまでたったひとつ)
ネタを只の一つも持ち合わせていなかったのである。さきごろまでたった一つ
(ねたがのこっていたが、それもせんじつつかいはたしてしまったのでいまはもうねたに)
ネタが残っていたが、それも先日使い果してしまったので今はもうネタに
(ついてはまったくのむいちもんのじょうたいにあった。しかるにこのあけがたまでに、)
ついては全くの無一文の状態にあった。しかるにこの暁方までに、
(なにがなんでもいっぺんのたんていしょうせつをかきあげてしまわねばならぬというので)
なにがなんでも一篇の探偵小説を書き上げてしまわねばならぬというので
(あるから、これはいかにいきしょうちんしまいとおもってもしょうちんしないわけには)
あるから、これは如何に意気銷沈しまいと思っても銷沈しないわけには
(ゆかないのであった。そんなことをかんがえているうちにも、とけいのはりはばかしょうじきに)
ゆかないのであった。そんなことを考えているうちにも、時計の針は馬鹿正直に
(どんどんまわってゆき、やがてくるあかつきまでのよゆうがずんずんみじかくなって)
ドンドン廻ってゆき、やがて来る暁までの余裕がズンズン短くなって
(ゆくのだった。なにかはやく、かくべきだいざいをかんがえつかないことには、いったいこれは)
ゆくのだった。なにか早く、書くべき題材を考えつかないことには、一体これは
(どういうことになるんだ。じこくはごぜんにじさんじっぷんまさにうしみつすぎとはなった。)
どういうことになるんだ。時刻は午前二時三十分正に丑満すぎとはなった。
(あたりはいよいよしーんとふけわたってーーいやただいま、てんじょうをねずみがごとごと)
あたりはいよいよシーンと更け渡ってーーイヤ只今、天井を鼠がゴトゴト
(はしりだした。しーんとふけわたってのもんくはとりけしである。このときうめのじゅうごは、)
走りだした。シーンと更け渡っての文句は取消しである。このとき梅野十伍は、
(にくにくしげなるうわめをつかってねずみのはしるてんじょういたをにらみつけていたが、そのうちに)
憎々しげなるうわ目をつかって鼠の走る天井板を睨みつけていたが、そのうちに
(どうしたものかかいちゅうからぬっとかたてをだして、「うむ、すまん」といいながら、)
何うしたものか懐中からヌッと片手を出して、「うむ、済まん」といいながら、
(てんじょううらのかたをふしおがんだのであった。かれはきゅうにげんきづいて、げんこうようしをてもとへ)
天井裏のかたを伏し拝んだのであった。彼は急に元気づいて、原稿用紙を手許へ
(ひきよせ、ぺんをとりあげた。いよいよなにかかんがえついてかくらしい。)
引きよせ、ペンを取り上げた。いよいよなにか考えついて書くらしい。
(かれはまず、げんこうようしのらんに「1」とたいしょした。それはげんこうのだいいちぺーじたることを)
彼はまず、原稿用紙の欄に「1」と大書した。それは原稿の第一頁たることを
(しめすものであった。かれはこののんぶるをあんぱんのようなおおきなもじでかくことが)
示すものであった。彼はこのノンブルを餡パンのような大きな文字で書くことが
(すきであった。げんこうのだいいちじをしたためたかれは、こんどはぺんをとりなおして)
好きであった。原稿の第一字を認めた彼は、こんどはペンを取り直して
(だいろくぎょうめのとっぷのしめんへもっていった。いよいよほんぶんをかくきらしい。)
第六行目のトップの紙面へ持っていった。いよいよ本文を書く気らしい。
(「うめだじゅうはちは、よるのふくるのをまって、こわれたおおどけいのうらからそっと)
「梅田十八は、夜の更くるのを待って、壊れた大時計の裏からソッと
(ぬけだした。まっくらなじゃりじゃりするいしのかいだんを、はらばいになって)
抜けだした。真暗なジャリジャリする石の階段を、腹匍いになって
(そろそろとのぼっていった。かいだんをのぼりきると、ぼんやりときいろいひのともった)
ソロソロと登っていった。階段を登りきると、ボンヤリと黄色い灯の点った
(おおひろまがいちぼうのうちにみわたされた。まほうつかいのようばは、いちぐうのしんだいのうえに)
大広間が一望のうちに見わたされた。魔法使いの妖婆は、一隅の寝台の上に
(くうくうとあらたかないびきをかいてねむっている。きかいはまさにいまだった」)
クウクウとあらたかな鼾をかいて睡っている。機会は正に今だった」







