【青空文庫】夢十夜 第一夜 2/2
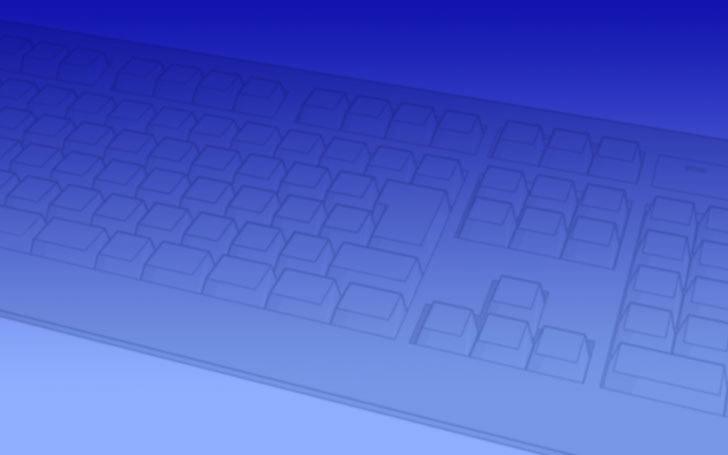
関連タイピング
-
古典落語の名作、寿限無でタイピング
プレイ回数1.8万 かな232打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数258 長文2992打 -
いろは歌
プレイ回数1.6万 かな87打 -
プレイ回数147 長文3594打
-
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数304 長文3235打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数518 長文3370打 -
プレイ回数344 長文2998打
-
プレイ回数175 長文1662打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(じぶんはそれからにわへおりて、しんじゅがいであなをほった。)
自分はそれから庭へ下りて、真珠貝で穴を掘った。
(しんじゅがいはおおきななめらかなふちのするどいかいであった。)
真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭どい貝であった。
(つちをすくうたびに、かいのうらにつきのひかりがさしてきらきらした。)
土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してきらきらした。
(しめったつちのにおいもした。)
湿った土の匂もした。
(あなはしばらくしてほれた。)
穴はしばらくして掘れた。
(おんなをそのなかにいれた。そしてやわらかいつちを、うえからそっとかけた。)
女をその中に入れた。そして柔らかい土を、上からそっと掛けた。
(かけるたびにしんじゅのうらにつきのひかりがさした。)
掛けるたびに真珠の裏に月の光が差した。
(それからほしのかけのおちたのをひろってきて、かろくつちのうえへのせた。)
それから星の欠片の落ちたのを拾ってきて、かろく土の上へ乗せた。
(だきあげてつちのうえへおくうちに、じぶんのむねとてがすこしあたたかくなった。)
抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖かくなった。
(じぶんはこけのうえにすわった。)
自分は苔の上に座った。
(これからひゃくねんのあいだこうしてまっているんだなとかんがえながら、)
これから百年の間こうして待っているんだなと考えながら、
(うでぐみをして、まるいはかいしをながめていた。)
腕組をして、丸い墓石を眺めていた。
(そのうちに、おんなのいったとおりひがひがしからでた。)
そのうちに、女の云った通り日が東から出た。
(おおきなあかいひであった。)
大きな赤い日であった。
(それがまたおんなのいったとおり、やがてにしへおちた。)
それがまた女の云った通り、やがて西へ落ちた。
(あかいまんまでのっとおちていった。)
赤いまんまでのっと落ちて行った。
(ひとつとじぶんはかんじょうした。)
一つと自分は勘定した。
(しばらくするとまたからくれないのてんとうがのそりとあがってきた。)
しばらくするとまた唐紅の天道がのそりと上って来た。
(そうしてだまってしずんでしまった。ふたつとまたかんじょうした。)
そうして黙って沈んでしまった。二つとまた勘定した。
(じぶんはこういうふうにひとつふたつとかんじょうしていくうちに、)
自分はこう云う風に一つ二つと勘定して行くうちに、
など
(あかいひをいくつみたかわからない。)
赤い日をいくつ見たか分からない。
(かんじょうしても、かんじょうしても、しつくせないほどあかいひがあたまのうえをとおりこしていった)
勘定しても、勘定しても、しつくせないほど赤い日が頭の上を通り越して行った
(それでもひゃくねんがまだこない。)
それでも百年がまだ来ない。
(しまいには、こけのはえたまるいいしをながめて、)
しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、
(じぶんはおんなにだまされたのではなかろうかとおもいだした。)
自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。
(するといしのしたからはすにじぶんのほうへむいてあおいくきがのびてきた。)
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。
(みるまにながくなってちょうどじぶんのむねあたりまできてとどまった。)
見る間に長くなってちょうど自分の胸あたりまで来て留まった。
(とおもうと、すらりとゆらぐくきのいただきに、こころもちくびをかたむけていたほそながいいちりんのつぼみが)
と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が
(ふっくらとはなびらをひらいた。)
ふっくらと花弁を開いた。
(まっしろなゆりがはなのさきでほねにこたえるほどにおった。)
真白な百合が鼻の先で骨に堪えるほど匂った。
(そこへはるかのうえから、ぽたりとつゆがおちたので、)
そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、
(はなはじぶんのおもみでふらふらとうごいた。)
花は自分の重みでふらふらと動いた。
(じぶんはくびをまえへだしてつめたいつゆのしたたる、しろいはなびらにせっぷんした。)
自分は首を前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。
(じぶんがゆりからかおをはなすとひょうしにおもわず、)
自分が百合から顔を離すと拍子に思わず、
(とおいそらをみたら、あかつきのほしがたったひとつまたたいていた。)
遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
(「ひゃくねんはもうきていたんだな」とこのときはじめてきがついた。)
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気が付いた。





