紫式部 源氏物語 松風 2 與謝野晶子訳
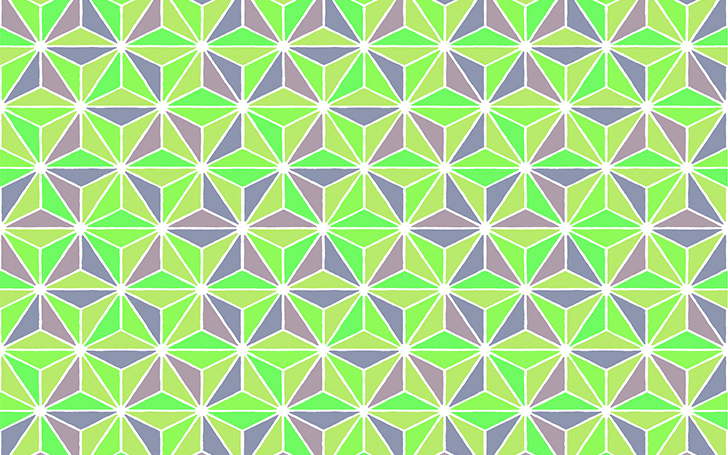
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤス | 7398 | 光 | 7.8 | 94.4% | 380.9 | 2994 | 176 | 44 | 2026/02/05 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(げんじのつくっているみどうはだいかくじのみなみにあたるところで、たきどのなどのびじゅつてきなことは)
源氏の作っている御堂は大覚寺の南にあたる所で、滝殿などの美術的なことは
(だいかくじにもおとらない。あかしのさんそうはかわにめんしたところで、たいぼくのまつのおおいなかへそぼくに)
大覚寺にも劣らない。明石の山荘は川に面した所で、大木の松の多い中へ素朴に
(しんでんのたてられてあるのも、さんそうらしいさびしいおもむきがでているようにみえた。)
寝殿の建てられてあるのも、山荘らしい寂しい趣が出ているように見えた。
(げんじはないぶのせつびまでもじしんのほうでさせておこうとしていた。)
源氏は内部の設備までも自身のほうでさせておこうとしていた。
(したしいひとたちをもまたひそかにあかしへむかえにたたせた。)
親しい人たちをもまたひそかに明石へ迎えに立たせた。
(まぬがれがたいいんねんにひかれていよいよそこをさるときになったのであるとおもうと、)
免れがたい因縁に引かれていよいよそこを去る時になったのであると思うと、
(おんなのこころはなじみぶかいあかしのうらになごりがおしまれた。ちちのにゅうどうをひとりぼっちで)
女の心は馴染深い明石の浦に名残が惜しまれた。父の入道を一人ぼっちで
(のこすこともくつうであった。なぜじぶんだけはこんなかなしみをしなければ)
残すことも苦痛であった。なぜ自分だけはこんな悲しみをしなければ
(ならないのであろうと、ほがらかなうんめいをもつひとがうらやましかった。)
ならないのであろうと、朗らかな運命を持つ人がうらやましかった。
(りょうしんもげんじにむかえられてむすめがしゅっきょうするというようなことはながいあいだねてもさめても)
両親も源氏に迎えられて娘が出京するというようなことは長い間寝てもさめても
(ねがっていたことで、それがじつげんされるよろこびはあっても、そのひをかぎりに)
願っていたことで、それが実現される喜びはあっても、その日を限りに
(むすめたちとわかれてこどくになるしょうらいをかんがえるとたえがたくかなしくて、)
娘たちと別れて孤独になる将来を考えると堪えがたく悲しくて、
(よるもひるもものおもいににゅうどうはぼうとしていた。いうことはいつもおなじで、)
夜も昼も物思いに入道は呆としていた。言うことはいつも同じで、
(「そしてわたくしはひめぎみのかおをみないでいるのだね」
そればかりである。)
「そして私は姫君の顔を見ないでいるのだね」
そればかりである。
(ふじんのこころにもひじょうにかなしかった。これまでもすでにおなじいえにはすまず)
夫人の心にも非常に悲しかった。これまでもすでに同じ家には住まず
(べっきょのかたちになっていたのであるから、あかしがじょうきょうしたあとにじぶんだけが)
別居の形になっていたのであるから、明石が上京したあとに自分だけが
(のこるひつようもみとめてはいないものの、ちほうにいるあいだだけのかりのふうふのなかでも)
残る必要も認めてはいないものの、地方にいる間だけの仮の夫婦の中でも
(つきひがかさなってなじみのふかくなったひとたちはわかれがたいものに)
月日が重なって馴染の深くなった人たちは別れがたいものに
(ちがいないのであるから、ましてふじんにとってはがんこながいのつよいおっとでは)
違いないのであるから、まして夫人にとっては頑固な我意の強い良人では
(あったが、あかしにつくったいえでおわるいのちをよそうして、しんらいしてきた)
あったが、明石に作った家で終わる命を予想して、信頼して来た
など
(つまなのであるからにわかにわかれてきょうへいってしまうことはこころぼそかった。)
妻なのであるからにわかに別れて京へ行ってしまうことは心細かった。
(こうみょうをみうしなったひとになっていなかのせいかつをしていたわかいにょうぼうなどは、)
光明を見失った人になって田舎の生活をしていた若い女房などは、
(そせいのできたほどにうれしいのであるが、うつくしいあかしのうらのふうけいにせっするひの)
蘇生のできたほどにうれしいのであるが、美しい明石の浦の風景に接する日の
(またないであろうことをおもうことでこころのめいることもあった。)
またないであろうことを思うことで心のめいることもあった。
(これはあきのことであったからことにものごとがしんでおもわれた。)
これは秋のことであったからことに物事が沁んで思われた。
(しゅったつのひのよあけに、すずしいあきかぜがふいていて、むしのこえもするとき、あかしのきみは)
出立の日の夜明けに、涼しい秋風が吹いていて、虫の声もする時、明石の君は
(うみのほうをながめていた。にゅうどうはごやにおきたままでいて、はなをすすりながら)
海のほうをながめていた。入道は後夜に起きたままでいて、鼻をすすりながら
(ぶつぜんのつとめをしていた。かどでのひはえんぎをいわって、ふきつなことはだれもいっさい)
仏前の勤めをしていた。門出の日は縁起を祝って、不吉なことはだれもいっさい
(さけようとしているが、ちちもむすめもしのぶことができずにないていた。ちいさいひめぎみは)
避けようとしているが、父も娘も忍ぶことができずに泣いていた。小さい姫君は
(ひじょうにうつくしくて、やこうのたまとおもわれるれいしつのそなわっているのを、)
非常に美しくて、夜光の珠と思われる麗質の備わっているのを、
(これまでどれほどにゅうどうがあいしたかしれない。そふのあいによくなじんでいるひめぎみを)
これまでどれほど入道が愛したかしれない。祖父の愛によく馴染んでいる姫君を
(にゅうどうはみて、
「そうぎょうのわたくしがひめぎみのそばにいることはえんりょすべきだと)
入道は見て、
「僧形の私が姫君のそばにいることは遠慮すべきだと
(これまでもおもいながら、かたときだっておかおをみねばいられなかったわたくしは、)
これまでも思いながら、片時だってお顔を見ねばいられなかった私は、
(これからさきどうするつもりだろう」
となく。)
これから先どうするつもりだろう」
と泣く。
(「ゆくさきをはるかにいのるわかれぢにたえぬはおいのなみだなりけり
)
「行くさきをはるかに祈る別れ路にたへぬは老いの涙なりけり
(ふきんしんだわたくしは」
といって、おちてくるなみだをぬぐいかくそうとした。)
不謹慎だ私は」
と言って、落ちてくる涙を拭い隠そうとした。
(あまぎみが、きょうじだいのさこんのちゅうじょうのおっとに、
)
尼君が、京時代の左近中将の良人に、
(「もろともにみやこはいできこのたびやひとりのなかのみちにまどわん」
)
「もろともに都は出できこのたびや一人野中の道に惑はん」
(といってなくのもどうじょうされることであった。しんらいをしあってすぎた)
と言って泣くのも同情されることであった。信頼をし合って過ぎた
(ねんげつをおもうと、どうなるかわからぬむすめのあいじんのこころをたのみにして、)
年月を思うと、どうなるかわからぬ娘の愛人の心を頼みにして、
(みすてたきょうへかえることがあまぎみをはかなくさせるのであった。あかしが、
)
見捨てた京へ帰ることが尼君をはかなくさせるのであった。明石が、
(「いきてまたあいみんことをいつとてかかぎりもしらぬよをばたのまん
)
「いきてまた逢ひ見んことをいつとてか限りも知らぬ世をば頼まん
(おくってだけでもくださいませんか」
とちちにたのんだが、それはじじょうが)
送ってだけでもくださいませんか」
と父に頼んだが、それは事情が
(ゆるさないことであるとにゅうどうはいいながらもとちゅうがきづかわれるふうがみえた。)
許さないことであると入道は言いながらも途中が気づかわれるふうが見えた。




