中島敦 名人伝 4/4
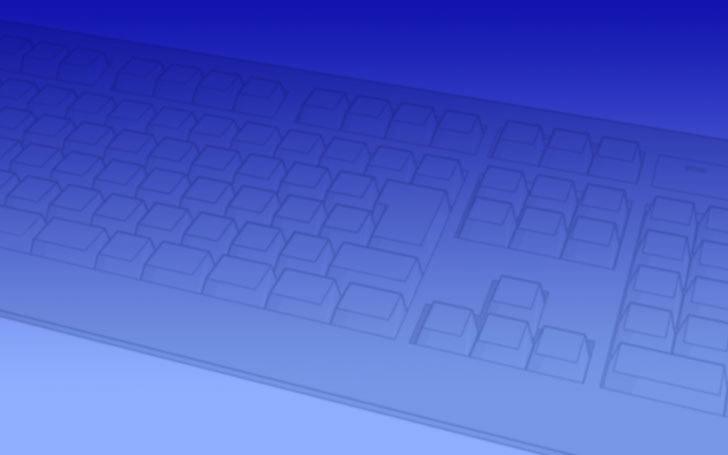
関連タイピング
-
仕事における情報処理スキルについて。
プレイ回数5213 長文かな2104打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
すみません誤字がありました
プレイ回数1427 歌詞1348打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数95万 長文300秒 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
タイピング練習に関する長文です
プレイ回数25万 長文1159打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.8万 歌詞かな200打 -
アスノヨゾラ哨戒班のタイピングです!
プレイ回数562 歌詞かな442打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(かんたんのみやこは、てんかいちのめいじんとなってもどってきたきしょうをむかえて、)
邯鄲の都は、天下一の名人となって戻って来た紀昌を迎えて、
(やがてがんぜんにしめされるにちがいないそのみょうぎへのきたいにわきかえった。)
やがて眼前に示されるに違いないその妙技への期待に湧返った。
(ところがきしょうはいっこうにそのようぼうにこたえようとしない。)
ところが紀昌は一向にその要望に応えようとしない。
(いや、ゆみさえたえててにとろうとしない。)
いや、弓さえ絶えて手に取ろうとしない。
(やまにはいるときにたずさえていったようかんまきんのゆみもどこかへすててきたようすである。)
山に入る時に携えて行った楊幹麻筋の弓もどこかへ棄てて来た様子である。
(そのわけをたずねたひとりにこたえて、きしょうはものうげにいった。)
そのわけを訊ねた一人に答えて、紀昌は懶げに言った。
(しいはなすなく、しげんはげんをさり、ししゃはいることなしと。)
至為は為す無く、至言は言を去り、至射は射ることなしと。
(なるほどと、しごくものわかりのいいかんたんのとじんしはすぐにがてんした。)
なるほどと、至極物分りのいい邯鄲の都人士はすぐに合点した。
(ゆみをとらざるゆみのめいじんはかれらのほこりとなった。)
弓を執らざる弓の名人は彼等の誇なった。
(きしょうがゆみにふれなければふれないほど、)
紀昌が弓に触れなければ触れないほど、
(かれのむてきのひょうばんはいよいよけんでんされた。)
彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。
(さまざまなうわさがひとびとのくちからくちへとつたわる。)
様々な噂が人々の口から口へと伝わる。
(まいやさんこうをすぎるころ、)
毎夜三更を過ぎる頃、
(きしょうのいえのおくじょうでなにもののたてるともしれぬゆづるのおとがする。)
紀昌の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ弓弦の音がする。
(めいじんのうちにやどるしゃどうのかみがしゅじんこうのねむっているかんにたいないをぬけだし、)
名人の内に宿る射道の神が主人公の睡っている間に体内を脱け出し、
(ようまをはらうべくてっしょうしゅごにあたっているのだという。)
妖魔を払うべく徹宵守護に当っているのだという。
(かれのいえのちかくにすむいちしょうにんはあるよるきしょうのいえのじょうくうで、)
彼の家の近くに住む一商人はある夜紀昌の家の上空で、
(くもにのったきしょうがめずらしくもゆみをてにして、)
雲に乗った紀昌が珍しくも弓を手にして、
(いにしえのめいじん・げいとようゆうきのふたりをあいてに)
古の名人・羿と養由基の二人を相手に
(うでくらべをしているのをたしかにみたといいだした。)
腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。
など
(そのときさんめいじんのはなったやはそれぞれよぞらにあおじろいこうぼうをひきつつ)
その時三名人の放った矢はそれぞれ夜空に青白い光芒を曳きつつ
(さんしゅくとてんろうせいとのあいだにきえさったと。)
参宿と天狼星との間に消去ったと。
(きしょうのいえにしのびいろうとしたところ、へいにあしをかけたとたんに)
紀昌の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足を掛けた途端に
(ひとみちのさっきがしんかんとしたいえのなかからはしりでてまともにひたいをうったので、)
一道の殺気が森閑とした家の中から奔り出てまともに額を打ったので、
(おぼえずそとにてんらくしたとはくじょうしたとうぞくもある。)
覚えず外に顛落したと白状した盗賊もある。
(じらい、じゃしんをいだくものどもはかれのじゅうきょのじっちょうしほうはさけてまわりみちをし、)
爾来、邪心を抱く者共は彼の住居の十町四方は避けて廻り道をし、
(かしこいわたりどりどもはかれのいえのじょうくうをとおらなくなった。)
賢い渡り鳥共は彼の家の上空を通らなくなった。
(くもとたちこめるめいせいのただなかに、めいじんきしょうはしだいにおいていく。)
雲と立罩める名声のただ中に、名人紀昌は次第に老いて行く。
(すでにはやくしゃをはなれたかれのこころは、)
既に早く射を離れた彼の心は、
(ますますこたんきょせいのいきにはいっていったようである。)
ますます枯淡虚静の域にはいって行ったようである。
(でくのごときかおはさらにひょうじょうをうしない、かたることもまれとなり、)
木偶のごとき顔は更に表情を失い、語ることも稀となり、
(ついにはこきゅうのうむさえうたがわれるにいたった。)
ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。
(「すでに、われとかれとのべつ、ぜとひとのぶんをしらぬ。)
「既に、我と彼との別、是と非との分を知らぬ。
(めはみみのごとく、みみははなのごとく、はなはくちのごとくおもわれる。」)
眼は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる。」
(というのが、ろうめいじんばんねんのじゅっかいである。)
というのが、老名人晩年の述懐である。
(かんようしのもとをじしてからよんじゅうねんののち、きしょうはしずかに、)
甘蠅師の許を辞してから四十年の後、紀昌は静かに、
(まことにけむりのごとくしずかによをさった。)
誠に煙のごとく静かに世を去った。
(そのよんじゅうねんのかん、かれはたえてしゃをくちにすることがなかった。)
その四十年の間、彼は絶えて射を口にすることが無かった。
(くちにさえしなかったくらいだから、ゆみやをとってのかつどうなどあろうはずがない。)
口にさえしなかった位だから、弓矢を執っての活動などあろうはずが無い。
(もちろん、ぐうわさくしゃとしてはここでろうめいじんにちょうびのだいかつやくをさせて、)
もちろん、寓話作者としてはここで老名人に掉尾の大活躍をさせて、
(めいじんのしんにめいじんたるゆえんをあきらかにしたいのはやまやまながら、)
名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、
(いっぽう、また、なんとしてもこじにしるされたじじつをまげるわけにはいかぬ。)
一方、また、何としても古書に記された事実を曲げる訳には行かぬ。
(じっさい、ろうごのかれについてはただのむいにしてかしたとばかりで、)
実際、老後の彼についてはただ無為にして化したとばかりで、
(つぎのようなみょうなはなしのほかにはなにひとつつたわっていないのだから。)
次のような妙な話の外には何一つ伝わっていないのだから。
(そのはなしというのは、かれのしぬいちにねんまえのことらしい。)
その話というのは、彼の死ぬ一二年前のことらしい。
(あるひおいたるきしょうがちじんのもとにまねかれていったところ、)
ある日老いたる紀昌が知人の許に招かれて行ったところ、
(そのいえでひとつのきぐをみた。)
その家で一つの器具を見た。
(たしかにみおぼえのあるどうぐだが、)
確かに見憶えのある道具だが、
(どうしてもそのなまえがおもいだせぬし、そのようともおもいあたらない。)
どうしてもその名前が思出せぬし、その用途も思い当らない。
(ろうじんはそのいえのしゅじんにたずねた。)
老人はその家の主人に尋ねた。
(それはなんとよぶしなもので、またなににもちいるのかと。)
それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。
(しゅじんは、きゃくがじょうだんをいっているとのみおもって、)
主人は、客が冗談を言っているとのみ思って、
(にやりととぼけたわらいかたをした。)
ニヤリととぼけた笑い方をした。
(ろうきしょうはしんけんになってふたたびたずねる。)
老紀昌は真剣になって再び尋ねる。
(それでもあいてはあいまいなわらいをうかべて、きゃくのこころをはかりかねたようすである。)
それでも相手は曖昧な笑を浮べて、客の心をはかりかねた様子である。
(さんどきしょうがまじめなかおをしておなじといをくりかえしたとき、)
三度紀昌が真面目な顔をして同じ問を繰返した時、
(はじめてしゅじんのかおにきょうがくのいろがあらわれた。)
始めて主人の顔に驚愕の色が現れた。
(かれはきゃくのめをじっとみつめる。あいてがじょうだんをいっているのでもなく、)
彼は客の眼を凝乎と見詰める。相手が冗談を言っているのでもなく、
(きがくるっているのでもなく、)
気が狂っているのでもなく、
(またじぶんがききちがえをしているのでもないことをたしかめると、)
また自分が聞き違えをしているのでもないことを確かめると、
(かれはほとんどきょうふにちかいろうばいをしめして、どもりながらさけんだ。)
彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、吃りながら叫んだ。
(「ああ、ふうしが、ーーここんむそうのしゃのめいじんたるふうしが、)
「ああ、夫子が、古今無双の射の名人たる夫子が、
(ゆみをわすれはてられたとや? ああ、ゆみというなも、そのつかいみちも!」)
弓を忘れ果てられたとや? ああ、弓という名も、その使い途も!」
(そのごとうぶんのかん、かんようのみやこでは、がかはえふでをかくし、)
その後当分の間、邯鄲の都では、画家は絵筆を隠し、
(がくじんはしつのげんをたち、こうしょうはきくをてにするのをはじたということである。)
楽人は瑟の絃を断ち、工匠は規矩を手にするのを恥じたということである。








