恐怖について1 海野十三
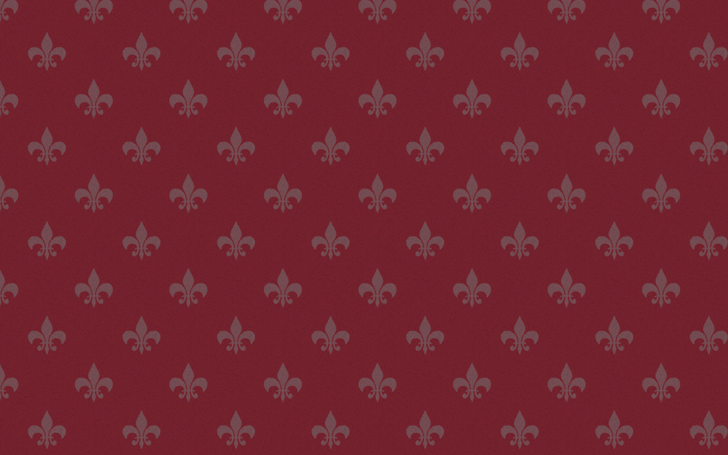
旧字体を新字体に変更
恐怖について/海野十三 著
青空文庫より引用
青空文庫より引用
関連タイピング
-
すみません誤字がありました
プレイ回数1340 歌詞1348打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
Mrs.GREEN APPLEさんの「クスシキ」です!!(フル)
プレイ回数342 歌詞120秒 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.7万 歌詞かな200打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
仕事における情報処理スキルについて。
プレイ回数5119 長文かな2104打 -
上級者向けタイピングゲームだよ
プレイ回数4.2万 長文かな822打 -
長文を打つ練習ができます。
プレイ回数36万 長文786打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(きょうふなんて、なくもがなである。)
恐怖なんて、無くもがなである。
(ーーとかたづけてしまうひとは、はなしにならない。きょうふはにんげんのしんけいをしげきすることが)
ーーと片づけてしまう人は、話にならない。恐怖は人間の神経を刺激することが
(おおきい。ひどいばあいは、そのばにたちすくんでしんぞうまひをおこしたり、あるいは)
大きい。ひどい場合は、その場に立ち竦んで心臓麻痺を起したり、或いは
(いっしゅんにしてとうはつことごとくしろくなってはくはつきとなったりする。そんなきょうふにじぶんじしんが)
一瞬にして頭髪悉く白くなって白髪鬼となったりする。そんな恐怖に自分自身が
(おそわれることはかなわんが、そういうきょうふがこのよにあることをきくのは)
襲われることはかなわんが、そういう恐怖がこの世にあることを聴くのは
(きわめてきょうみぶかい。たんていしょうせつがよろこばれるひとつのげんいんは、きょうふというものが)
極めて興味深い。探偵小説が喜ばれる一つの原因は、恐怖というものが
(もられていることにある。たんていしょうせつをこのむわたしとして、きょうふにみりょくをかんずるのは、)
盛られていることに在る。探偵小説を好む私として、恐怖に魅力を感ずるのは、
(とうぜんのことであろう。きょうはひとつ、へいぜいわたしのかんじているきょうふのじつれいを)
当然のことであろう。今日は一つ、平生私の感じている恐怖の実例を
(すこしひろって、どうこうのしょくんにささげようとおもう。)
すこし拾って、同好の諸君に捧げようと思う。
(わたしはふみきりをとおることがおそろしい。うちのきんじょには、ばんにんのいないふみきりがあって、)
私は踏切を通ることが恐しい。うちの近所には、番人の居ない踏切があって、
(よくこどもがひきころされ、「まのふみきり」などとしんぶんにかきたてられたものである。)
よく子供が轢き殺され、「魔の踏切」などと新聞に書きたてられたものである。
(あすこへいきかかると、れっしゃがかぜをきってとんできて、めとはなとのあいだをごうごうと)
あすこへ行き掛ると、列車が風を切って飛んできて、目と鼻との間を轟々と
(いきすぎることがある。れっしゃがつうかしてから、そのひかっているれーるを)
行き過ぎることがある。列車が通過してから、その光っているレールを
(またぐときに、なんともめいじょうしがたいせんりつをおぼえる。もしもじぶんのめがくるっていて、)
跨ぐときに、何とも名状し難い戦慄を覚える。もしも自分の眼が狂っていて、
(れっしゃがみえないのだったらどうだろう。こうまたいだひょうしに、じぶんは)
列車が見えないのだったらどうだろう。こう跨いだ拍子に、自分は
(ひきころされているのだ。にんげんというものは、しんでも、しんだとは)
轢き殺されているのだ。人間というものは、死んでも、死んだとは
(きがつかないものだというはなしをきいているので、れーるをまたぎおえたとおもっても)
気がつかないものだという話を聞いているので、レールを跨ぎ終えたと思っても
(あんしんならない。こんなふうにきょうふをもってふみきりをわたるのは、わたしひとりなのだろうか。)
安心ならない。こんな風に恐怖をもって踏切を渡るのは、私一人なのだろうか。
(こどもをだいて、びるでぃんぐのおくじょうへのぼったことがある。さいしょはたしか)
子供を抱いて、ビルディングの屋上へ上ったことがある。最初はたしか
(あさくさのふじかんだとおもった。のぼってみるとかんないのにぎやかさにくらべて、おくじょうは)
浅草の富士館だと思った。上ってみると館内の賑やかさに比べて、屋上は
など
(ひとひとりいないのである。したをのぞいてみると、つうこうのひとのあたまばかりがみえる。)
人一人いないのである。下を覗いてみると、通行の人の頭ばかりが見える。
(ほどうまではたいへんとおい。わたしはかいぶつじゅうりょくにきゅうにひっぱられるけはいをかんじた。)
舗道までは大変遠い。私は怪物重力に急に引張られる気配を感じた。
(そのときわたしのうでのなかにいたこどもが、むしんでわたしのかおをたたいた。ごむまりのように)
そのとき私の腕の中にいた子供が、無心で私の顔を叩いた。ゴム毬のように
(かるいこどもである。わたしはとつぜん、うでをのばしてこどもをぽいとしたにおとしてみたい)
軽い子供である。私は突然、腕を伸ばして子供をポイと下に墜としてみたい
(しょうどうにおそわれた。「これは、いけない!」わたしはいっしょうけんめいに、じぶんじしんをしかった。)
衝動に襲われた。「これは、いけない!」私は一生懸命に、自分自身を叱った。
(しかしかいぶつじゅうりょくはわたしにのりうつって、(はやくこどもをしたになげろ!)とさそう。)
しかし怪物重力は私にのりうつって、(早く子供を下に抛げろ!)と誘う。
(わたしはりつぜんとしてきょうふにおそわれた。もっとあそんでいたいとこどもがなきだすのも)
私は慄然として恐怖に襲われた。もっと遊んでいたいと子供が泣きだすのも
(かまわず、むちゅうではしごだんのほうへたいきゃくしていった。それいらい、こどもを)
構わず、夢中で梯子段の方へ退却していった。それ以来、子供を
(つれているときは、おくじょうへのぼらないことにしている。)
連れているときは、屋上へのぼらないことにしている。
(ゆめのなかにみるきょうふのうち、とくにおそろしいこうけいがふたつある。ひとつは、)
夢の中に見る恐怖のうち、特に恐ろしい光景が二つある。一つは、
(そらをみていると、たいようがきゅうにふたつにふえ、あれよあれよとみているあいだに)
空をみていると、太陽が急に二つに殖え、アレヨアレヨと見ている間に
(みっつにもよっつにもふえてゆくのをみるときだ。そんなときのたいようは、)
三つにも四つにも殖えてゆくのをみるときだ。そんなときの太陽は、
(いつもひかりをうしなって、まるでしゅぼんのようないろをしている。のもやまも、)
いつも光を失って、まるで朱盆のような色をしている。野も山も、
(いつのまにかまるぼうずになり、ぷすぷすとつめたいすいじょうきがたちのぼってくる。)
いつの間にか丸坊主になり、プスプスと冷い水蒸気が立ちのぼってくる。
(せかいのおわりだ!わたしはびっしょりねあせをかいて、めがさめる。)
世界の終りだ!私はビッショリ寝汗をかいて、目が醒める。
(もうひとつは、ふろいどせんせいのごやっかいものだが、こうずいのゆめをみるときだ。)
もう一つは、フロイド先生の御厄介ものだが、洪水の夢をみるときだ。
(あめはくらいそらからじゃんじゃんふっている。みずだみずだというこえがするので、)
雨は暗い空からジャンジャン降っている。水だ水だという声がするので、
(そとにでてみる。なるほどみずかさがましている。すいめんはてのとどきそうなちかくにまで)
外に出てみる。なるほど水嵩が増している。水面は手のとどきそうな近くにまで
(あがっている。かわはばはもううみのようにひろくなっている。あおいみずはごうごうと)
上っている。川幅はもう海のように広くなっている。碧い水は轟々と
(うずをまいて、したへながれてゆく。かみてをみてみれば、かわもがうえへ)
渦を巻いて、下へ流れてゆく。上手をみてみれば、川面が上へ
(かたむいているではないか。これではみずのへるみこみはぜんぜんない。ふとわたしはかわしもに、)
傾いているではないか。これでは水の減る見込は全然ない。不図私は川下に、
(かぞくをのこしてきたことをおもいだす。このみずがかわしもへおちてゆくときは、)
家族を残して来たことを思い出す。この水が川下へ落ちてゆくときは、
(わたしのかぞくのぜんぶのおぼれしぬるときだ、とそうおもうと、)
私の家族の全部の溺れ死ぬるときだ、とそう思うと、
(わたしはたえがたいきょうふにおそわれて、めがさめる。)
私は堪え難い恐怖に襲われて、目が醒める。
(なんにもおとのしないところへゆくと、これがまたおそろしい。いつだったかようしゅんの)
何にも音のしないところへゆくと、これがまた恐ろしい。いつだったか陽春の
(まひる、こうがいのひろいのはらへでた。れんげやたんぽぽが、たいへんきれいに)
真昼、郊外の広い野原へ出た。蓮華や蒲公英が、たいへん綺麗に
(さきひろがっている。わたしはどうしんにかえって、それをいっぽんいっぽん、みぎてでつんでは)
咲き拡がっている。私は童心に帰って、それを一本一本、右手で摘んでは
(ひだりてにたばねてゆく。はなたばはだんだんおおきくなっていった。しまいに)
左手に束ねてゆく。花束はだんだん大きくなっていった。しまいに
(つみくたびれて、のはらのまんなかにたちどまった。きゅうにじぶんのしんぺんがきになりだす。)
摘みくたびれて、野原の真中に立ちどまった。急に自分の身辺が気になり出す。
(みみをすましてきくと、さあたいへんだ。ひとごえもしなければ、こうじょうのきてきのおとも)
耳を澄まして聴くと、サア大変だ。人声もしなければ、工場の汽笛の音も
(きこえない。さっきまでふいていたかぜさえおさまって、まったくおとというものが)
聞えない。さっきまで吹いていた風さえ治まって、全く音というものが
(きこえない。こまくがあってもなんにもならない。じぶんはしんでしまったのでは)
聞えない。鼓膜があってもなんにもならない。自分は死んでしまったのでは
(ないかーーと、そうおもったしゅんかん、めいじょうすべからざるせんりつがぜんしんに)
ないかーーと、そう思った瞬間、名状すべからざる戦慄が全身に
(はいのぼってきた。・・・・・・あとでかんがえると、あのときは、せきでもするとか、)
匍いのぼって来た。……後で考えると、あのときは、咳でもするとか、
(ぐんかでもうたえばよかったのにとおもう。)
軍歌でも歌えばよかったのにと思う。








