谷崎潤一郎 刺青②(終)
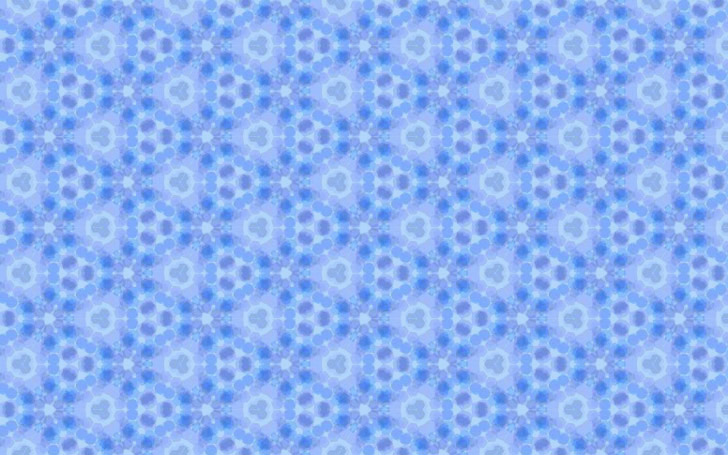
関連タイピング
-
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
深海生物について。長文です
プレイ回数5325 長文かな1965打 -
かなりの難しさ
プレイ回数2363 長文864打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
底辺Youtuberが底辺タイピングを作ってみたぞ!
プレイ回数115 長文380打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(「このえにはおまえのこころがうつっているぞ」こういって、)
「この絵にはお前の心が映って居るぞ」こう云って、
(せいきちはこころよげにわらいながら、むすめのかおをのぞきこんだ。「どうして)
清吉は快げに笑いながら、娘の顔をのぞき込んだ。「どうして
(こんなおそろしいものを、わたしにおみせなさるのです」と、むすめはあおざめたひたいをもたげて)
こんな恐ろしいものを、私にお見せなさるのです」と、娘は青褪めた額を擡げて
(いった。「このえのおんなはおまえなのだ。このおんなのちがおまえのからだにまじっているはずだ」)
云った。「この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に交って居る筈だ」
(と、かれはさらにほかのいっぽんのかくはばをひろげた。それは「ひりょう」というかくだいであった。)
と、彼は更に他の一本の畫幅を展げた。それは「肥料」と云う畫題であった。
(かくめんのちゅうおうに、わかいおんながさくらのみきへみをよせて、あしもとにるいるいとたおれているおおくの)
畫面の中央に、若い女が桜の幹へ身を倚せて、足下に累々と斃れている多くの
(おとこたちのむくろをみつめている。おんなのしんぺんをまいつつ)
男たちの屍骸(むくろ)を見つめて居る。女の身辺を舞いつつ
(かちどきをうたうことりのむれ、おんなのひとみにあふれたるおさえがたきほこりと)
凱歌(かちどき)をうたう小鳥の群、女の瞳に溢れたる抑え難き誇りと
(よろこびのいろ。それはたたかいのあとのけしきか、はなぞののはるのけしきか。それをみせられた)
歓びの色。それは戦いの跡の景色か、花園の春の景色か。それを見せられた
(むすめは、われとわがこころのそこにひそんでいたなにものかを、さぐりあてたるここちであった。)
娘は、われとわが心の底に潜んで居た何物かを、探りあてたる心地であった。
(「これはおまえのみらいをえにあらわしたのだ。ここにたおれているひとたちは、みなこれから)
「これはお前の未来を絵に現わしたのだ。此処に斃れて居る人達は、皆これから
(おまえのためにいのちをすてるのだ」こういって、せいきちはむすめのかおとすんぶんたがわぬかくおもてのおんなを)
お前の為に命を捨てるのだ」こう云って、清吉は娘の顔と寸分違わぬ畫面の女を
(ゆびさした。「ごしょうだから、はやくそのえをしまってください」と、むすめはゆうわくをさける)
指さした。「後生だから、早く其の絵をしまって下さい」と、娘は誘惑を避ける
(がごとく、かくおもてにそむいてたたみのうえへつっぷしたが、やがてふたたびくちびるをわななかした。)
が如く、畫面に背いて畳の上へ突俯したが、やがて再び唇をわななかした。
(「おやかた、はくじょうします。わたしはおまえさんのおさっしどおり、そのえのおんなのようなしょうぶんを)
「親方、白状します。私はお前さんのお察し通り、其の絵の女のような性分を
(もっていますのさ。ーーだからもうかんにんして、それをひっこめておくんなさい」)
持って居ますのさ。ーーだからもう堪忍して、其れを引っ込めてお呉んなさい」
(「そんなひきょうなことをいわずと、もっとよくこのえをみるがいい。それをおそろし)
「そんな卑怯な事を云わずと、もっとよく此の絵を見るがいい。それを恐ろし
(がるのも、まあいまのうちだろうよ」こういったせいきちのかおには、いつものいじの)
がるのも、まあ今のうちだろうよ」こう云った清吉の顔には、いつもの意地の
(わるいわらいがただよっていた。しかしむすめのつむりはよういにあがらなかった。じゅばんの)
悪い笑いが漂って居た。然し娘の頭(つむり)は容易に上らなかった。襦袢の
(そでにかおをおおうていつまでもつっぷしたまま、「おやかた、どうかわたしをかえしておくれ。)
袖に顔を蔽うていつまでも突俯したまま、「親方、どうか私を帰しておくれ。
など
(おまえさんのそばにいるのはおそろしいから」と、いくどかくりかえした。「まあまち)
お前さんの側に居るのは恐ろしいから」と、幾度か繰り返した。「まあ待ち
(なさい。おれがおまえをりっぱなきりょうのおんなにしてやるから」といいながら、せいきちは)
なさい。己がお前を立派な器量の女にしてやるから」と云いながら、清吉は
(なにげなくむすめのそばにちかよった。かれのふところにはかつてわらんいからもらったますいざいのびんが)
何気なく娘の側に近寄った。彼の懐には嘗て和蘭医から貰った麻睡剤の壜が
(しのばせてあった。)
忍ばせてあった。
(ひはうららかにかわもをいて、はちじょうのざしきはもえるようにてった。みなもから)
日はうららかに川面を射て、八畳の座敷は燃えるように照った。水面から
(はんしゃするこうせんが、むしんにねむるむすめのかおや、しょうじのかみにこんじきのはもんを)
反射する光線が、無心に眠る娘の顔や、障子の紙に金色(こんじき)の波紋を
(えがいてふるえていた。へやのしきりをたてきってほりもののどうぐをてにしたせいきちは、)
描いてふるえて居た。部屋のしきりを閉て切って刺青の道具を手にした清吉は、
(しばらくはただうっとりとしてすわっているばかりであった。かれはいまはじめて)
暫くは唯恍惚(うっとり)としてすわって居るばかりであった。彼は今始めて
(おんなのみょうそうをしみじみあじわうことができた。そのうごかぬかおにあいたいして、じゅうねんひゃくねん)
女の妙相をしみじみ味わう事が出来た。その動かぬ顔に相対して、十年百年
(このいっしつにせいざするとも、なおあくことをしるまいとおもわれた。いにしえのめんふぃすの)
この一室に静坐するとも、なお飽く事を知るまいと思われた。古のメンフィスの
(たみが、そうごんなるえじぷとのてんちを、ぴらみっどとすふぃんくすとで)
民が、荘厳なる埃及(エジプト)の天地を、ピラミッドとスフィンクスとで
(かざったように、せいきちはせいじょうなにんげんのひふを、じぶんのこいでいろどろうとするので)
飾ったように、清吉は清浄な人間の皮膚を、自分の恋で彩ろうとするので
(あった。やがてかれはひだりてのこゆびとななしゆびとおやゆびのあいだにはさんだえふでのほを、むすめの)
あった。やがて彼は左手の小指と無名指と拇指の間に挿んだ絵筆の穂を、娘の
(せにねかせ、そのうえからみぎてではりをさしていった。わかいほりものしのこころは)
背にねかせ、その上から右手で針を刺して行った。若い刺青師の霊(こころ)は
(ぼくじゅうのなかにとけて、ひふににじんだ。しょうちゅうにまぜてほりこむりゅうきゅうしゅのいってきいってきは、)
墨汁の中に溶けて、皮膚に滲んだ。焼酎に交ぜて刺り込む琉球朱の一滴々々は、
(かれのいのちのしたたりであった。かれはそこにわがたましいのいろをみた。いつしかひるも)
彼の命のしたたりであった。彼は其処に我が魂の色を見た。いつしか午も
(すぎて、のどかなはるのひはようやくくれかかったが、せいきちのてはすこしもやすまず、)
過ぎて、のどかな春の日は漸く暮れかかったが、清吉の手は少しも休まず、
(おんなのねむりもやぶれなかった。むすめのかえりのおそきをあんじてむかいにでたはこやまでが、)
女の眠りも破れなかった。娘の帰りの遅きを案じて迎いに出た箱屋迄が、
(「あのこならもうとうにかえっていきましたよ」といわれておいかえされた。)
「あの娘(こ)ならもう疾うに帰って行きましたよ」と云われて追い返された。
(つきがたいがんのとしゅうやしきのうえにかかって、ゆめのようなひかりがえんがんいったいのいえいえのざしきに)
月が対岸の土州屋敷の上にかかって、夢のような光が沿岸一帯の家々の座敷に
(ながれこむころには、ほりものはまだはんぶんもできあがらず、せいきちはいっしんにろうそくのしん)
流れ込む頃には、刺青はまだ半分も出来上らず、清吉は一心に蝋燭の心(しん)
(をかきたてていた。いってんのいろをそそぎこむのも、かれにとってはよういなわざで)
を掻き立てて居た。一点の色を注ぎ込むのも、彼に取っては容易な業で
(なかった。さすはり、ぬくはりのたびごとにふかいといきをついて、じぶんのこころがさされる)
なかった。さす針、ぬく針の度毎に深い吐息をついて、自分の心が刺される
(ようにかんじた。はりのあとはしだいしだいにきょだいなじょろうぐものかたちをそなえ)
ように感じた。針の痕は次第々々に巨大な女郎蜘蛛の形象(かたち)を具え
(はじめて、ふたたびよるがしらしらとしらみはじめたじぶんには、このふしぎなましょうのどうぶつは、)
始めて、再び夜がしらしらと白み初めた時分には、この不思議な魔性の動物は、
(はちほんのあしをのばしつつ、せいちめんにわだかまった。はるのよるは、のぼりくだりのかわぶねのろごえに)
八本の肢を伸ばしつつ、背一面に蟠った。春の夜は、上り下りの河船の櫓声に
(あけはなれて、あさかぜをはらんでくだるしらほのいただきからうすらぎはじめるかすみのなかに、なかす、)
明け放れて、朝風を孕んで下る白帆の頂から薄らぎ始める霞の中に、中洲、
(はこざき、れいがんじまのいえいえのいらかがきらめくころ、せいきちはようやくえふでをおいて、むすめのせに)
箱崎、霊岸島の家々の甍がきらめく頃、清吉は漸く絵筆を擱いて、娘の背に
(ほりこまれたくものかたちをながめていた。そのほりものこそはかれのせいめいのすべてで)
刺り込まれた蜘蛛のかたちを眺めて居た。その刺青こそは彼の生命のすべてで
(あった。そのしごとをなしおえたあとのかれのこころはうつろであった。)
あった。その仕事をなし終えた後の彼の心は
空虚(うつろ)であった。
(ふたつのひとかげはそのままややしばらくうごかなかった。そうして、ひくく、かすれたこえが)
二つの人影は其のまま稍々暫く動かなかった。そうして、低く、かすれた声が
(へやのよかべにふるえてきこえた。「おれはおまえをほんとうのうつくしいおんなにするために、)
部屋の四壁に震えて聞えた。「己はお前をほんとうの美しい女にする為に、
(ほりもののなかへおれのたましいをうちこんだのだ、もういまからはにほんこくじゅうに、おまえにまさるおんなは)
刺青の中へ己の魂をうち込んだのだ、もう今からは日本国中に、お前に優る女は
(いない。おまえはもういままでのようなおくびょうなこころはもっていないのだ。おとこというおとこは、)
居ない。お前はもう今迄のような臆病な心は持って居ないのだ。男と云う男は、
(みんなおまえのこやしになるのだ。・・・」そのことばがつうじたか、)
皆なお前の肥料(こやし)になるのだ。・・・」其の言葉が通じたか、
(かすかに、いとのようなうめきごえがおんなのくちびるにのぼった。むすめはしだいしだいにちかくを)
かすかに、糸のような呻き声が女の唇にのぼった。娘は次第々々に知覚を
(かいふくしてきた。おもくひきいれては、おもくひきだすかたいきに、くものあしはいけるが)
恢復して来た。重く引き入れては、重く引き出す肩息に、蜘蛛の肢は生けるが
(ごとくぜんどうした。「くるしかろう。からだをくもがだきしめているの)
如く蠕動(ぜんどう)した。「苦しかろう。体を蜘蛛が抱きしめて居るの
(だから」こういわれてむすめはほそくむいみなめをひらいた。そのひとみはゆうづきのひかりをます)
だから」こう云われて娘は細く無意味な眼を開いた。其の瞳は夕月の光を増す
(ように、だんだんとかがやいておとこのかおにてった。「おやかた、はやくわたしにせなかの)
ように、だんだんと輝いて男の顔に照った。「親方、早く私に背(せなか)の
(ほりものをみせておくれ、おまえさんのいのちをもらったかわりに、わたしはさぞうつくしく)
刺青を見せておくれ、お前さんの命を貰った代りに、私は嘸(さぞ)美しく
(なったろうねえ」むすめのことばはゆめのようであったが、しかしそのちょうしにはどこか)
なったろうねえ」娘の言葉は夢のようであったが、しかし其の調子には何処か
(するどいちからがこもっていた。「まあ、これからゆどのへいっていろあげをするのだ。)
鋭い力がこもって居た。「まあ、これから湯殿へ行って色上げをするのだ。
(くるしかろうがちっとがまんをしな」と、せいきちはみみもとへくちをよせて、いたわるように)
苦しかろうがちッと我慢をしな」と、清吉は耳元へ口を寄せて、労わるように
(ささやいた。「うつくしくさえなるのなら、どんなにでもしんぼうしてみせましょうよ」と、)
囁いた。「美しくさえなるのなら、どんなにでも辛抱して見せましょうよ」と、
(むすめはみうちのいたみをおさえて、しいてほほえんだ。)
娘は身内の痛みを抑えて、強いて微笑んだ。
(「ああ、ゆがしみてくるしいこと。・・・おやかた、ごしょうだからわたしをうっちゃって)
「ああ、湯が滲みて苦しい事。・・・親方、後生だから私を打っ捨(ちゃ)って
(にかいへいってまっていておくれわたしはこんなみじめなざまをおとこに)
二階へ行って待って居てお呉れ
私はこんな悲惨(みじめ)な態(ざま)を男に
(みられるのがくやしいから」むすめはゆあがりのからだをぬぐいもあえず、いたわる)
見られるのが口惜(くや)しいから」娘は湯上りの体を拭いもあえず、いたわる
(せいきちのてをつきのけて、はげしいくつうにながしのいたのまへみをなげたまま、)
清吉の手をつきのけて、激しい苦痛に流しの板の間へ身を投げたまま、
(うなされるごとくにうめいた。きぐるいじみたかみがなやましげにそのほおへみだれた。)
魘(うな)される如くに呻いた。気狂じみた髪が悩ましげに其の頬へ乱れた。
(おんなのはいごにはきょうだいがたてかけてあった。まっしろなあしのうらがふたつ、そのおもてへうつって)
女の背後には鏡台が立てかけてあった。真っ白な足の裏が二つ、その面へ映って
(いた。きのうとはうってかわったおんなのたいどに、せいきちはひとかたならずおどろいたが、)
居た。昨日とは打って変った女の態度に、清吉は一と方ならず驚いたが、
(いわれるままにひとりにかいにまっていると、およそはんときばかりたって、おんなはあらいがみを)
云われるままに独り二階に待って居ると、凡そ半時ばかり経って、女は洗い髪を
(りょうかたへすべらせ、みじまいをととのえてあがってきた。そうしてくるしみの)
両肩へすべらせ、身じまいを整えて上って来た。そうして苦痛(くるしみ)の
(かげもとまらぬはれやかなまゆをはって、らんかんにもたれながらおぼろにかすむおおぞらを)
かげもとまらぬ晴れやかな眉を張って、欄干に靠れながらおぼろにかすむ大空を
(あおいだ。「このえはほりものといっしょにおまえにやるから、それをもってもうかえるが)
仰いだ。「この絵は刺青と一緒にお前にやるから、其れを持ってもう帰るが
(いい」こういってせいきちはまきものをおんなのまえにさしおいた。「おやかた、わたしはもういままでの)
いい」こう云って清吉は巻物を女の前にさし置いた。「親方、私はもう今迄の
(ようなおくびょうなこころを、さらりとすててしまいました。ーーおまえさんはまっさきにわたしの)
ような臆病な心を、さらりと捨ててしまいました。ーーお前さんは真先に私の
(こやしになったんだねえ」と、おんなはつるぎのようなひとみをかがやかした。)
肥料(こやし)になったんだねえ」と、女は剣のような瞳を輝かした。
(そのみみにはかちどきのこえがひびいていた。「かえるまえにもういっぺん、)
その耳には凱歌(かちどき)の声がひびいて居た。「帰る前にもう一遍、
(そのほりものをみせてくれ」せいきちはこういった。おんなはだまってうなずいてはだをぬいた。)
その刺青を見せてくれ」清吉はこう云った。女は黙って頷いて肌を脱いた。
(おりからあさひがほりもののおもてにさして、おんなのせなかはさんらんとした。)
折から朝日が刺青の面にさして、女の背(せなか)は燦爛とした。








