百物語1 岡本綺堂
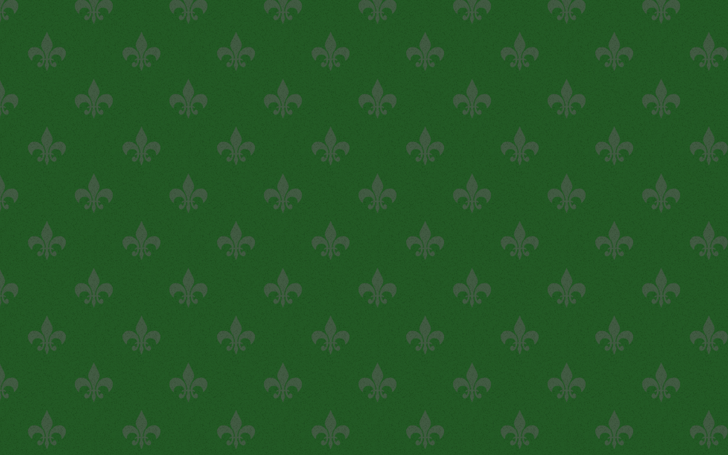
幕末の若侍たちの百物語。妖怪は出るか、出ないのか。
関連タイピング
-
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数15万 歌詞かな167打 -
テトリスのサビだけを30秒で打て!!!!!!!!!!
プレイ回数714 歌詞かな30秒 -
最後まで打てる人いる?
プレイ回数182 歌詞かな993打 -
マイクラの攻略チャートでタイピング
プレイ回数68 長文かな602打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数4.1万 歌詞かな200打 -
打ち切れたら天才だ
プレイ回数5853 歌詞540打 -
GReeeeNのキセキです。
プレイ回数3828 歌詞1426打 -
お話は「魔法の鉛筆」
プレイ回数245 長文434打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(いまから80ねんほどのむかしーーといいかけて、oくんはじぶんでもわらいだした。いや、)
今から八十年ほどの昔――と言いかけて、O君は自分でも笑い出した。いや、
(もっととおいむかしになるのかもしれない。なんでもこうかがんねんとか2ねんとかの9がつ、)
もっと遠い昔になるのかも知れない。なんでも弘化元年とか二年とかの九月、
(じょうしゅうのあるだいみょうのじょうないにおこったできごとである。
あきのよるにわかざむらいどもが)
上州の或る大名の城内に起った出来事である。
秋の夜に若侍どもが
(よづめをしていた。きのうからのあめのふりやまないで、ものすごいよるであった。)
夜詰めをしていた。きのうからの雨のふりやまないで、物すごい夜であった。
(いつのよもおなじことで、こういうよるにはかいだんのはじまるのがならいである。)
いつの世もおなじことで、こういう夜には怪談のはじまるのが習いである。
(そのなかで、いちざのせんぱいとあおがれているなかはらぶだゆうというおとこがいいだした。)
そのなかで、一座の先輩と仰がれている中原武太夫という男が言い出した。
(「むかしからよにばけものがあるといい、ないという。そのぎろんまちまちでたしかに)
「むかしから世に化け物があるといい、無いという。その議論まちまちで確かに
(わからない。こんやのようなばんはちょうどあつらえむきであるから、これからかのひゃくものがたり)
判らない。今夜のような晩は丁度あつらえ向きであるから、これからかの百物語
(というのをもよおして、ようかいがでるかでないかためしてみようではないか」)
というのを催して、妖怪が出るか出ないか試してみようではないか」
(「それはおもしろいことでござる」
いずれもけっきのわかざむらいばかりであるから、)
「それは面白いことでござる」
いずれも血気の若侍ばかりであるから、
(いちざのいけんすぐにいっちして、いよいよひゃくものがたりをはじめることになった。)
一座の意見すぐに一致して、いよいよ百物語をはじめることになった。
(まずあおいかみであんどうのくちをおおい、さだめのとおりにとうしんひゃくすじをいれていつまほど)
まず青い紙で行燈の口をおおい、定めの通りに燈心百すじを入れて五間ほど
(はなれているおくのしょいんにすえた。そのそばにはいちめんのかがみをおいて、とうしんを)
距れている奥の書院に据えた。そのそばには一面の鏡を置いて、燈心を
(ひとすじずつけしにゆくたびに、かならずそのかがみのおもてをのぞいてみることという)
ひと筋ずつ消しにゆくたびに、必ずその鏡のおもてを覗いてみることという
(やくそくであった。もちろん、そのあいだのいつまにはともしびをおかないで、とちゅうは)
約束であった。勿論、そのあいだの五間にはともしびを置かないで、途中は
(すべてくらがりのなかをさぐりあしでゆくことになっていた。
「いったい、ひゃくものがたり)
すべて暗がりのなかを探り足でゆくことになっていた。
「一体、百ものがたり
(といういじょう、100にんがかわるがわるにはなさなければならないのか」)
という以上、百人が代るがわるに話さなければならないのか」
(それについてもしゅじゅのぎろんがでたが、ひゃくものがたりというのはいっしゅのけいしきで、)
それについても種々の議論が出たが、百物語というのは一種の形式で、
(かならず100にんにかぎったことではあるまいといういけんがおおかった。じっさいそこには)
かならず百人にかぎったことではあるまいという意見が多かった。実際そこには
(100にんのあたまかずがそろっていなかった。しかしものがたりのかずだけは100かじょうを)
百人のあたま数が揃っていなかった。しかし物語の数だけは百箇条を
など
(そろえなければならないというので、くじびきのうえでひとりが3つ4つのはなしをうけもつ)
揃えなければならないというので、くじ引きの上で一人が三つ四つの話を受持つ
(ことになった。それでもなるべくはにんずうがおおいほうがいいというので、いやがる)
ことになった。それでもなるべくは人数が多い方がいいというので、いやがる
(ちゃぼうずどもまでをかりあつめてきて、よるのいつつ(ごご8じ)ころからだい1ばんの)
茶坊主どもまでを狩りあつめて来て、夜の五つ(午後八時)頃から第一番の
(うらべしろうしちというわかざむらいが、まずかいだんのくちをきった。
なにしろ100かじょうのはなしを)
浦辺四郎七という若侍が、まず怪談の口を切った。
なにしろ百箇条の話を
(するのであるから、ひとつのはなしはなるべくみじかいのをえらむというやくそくであったが、)
するのであるから、一つの話はなるべく短いのを選むという約束であったが、
(それでもあんがいにときがうつって、かのなかはらぶだゆうがだい83ばんのざになおったのは、)
それでも案外に時が移って、かの中原武太夫が第八十三番の座に直ったのは、
(そのよるももうやっつ(ごぜん2じ)にちかいころであった。なかはらはこんどで3ばんめ)
その夜ももう八つ(午前二時)に近い頃であった。中原は今度で三番目
(であるから、もちあわせのかいだんもたねぎれになってしまって、あるやまでらのにそうと)
であるから、持ちあわせの怪談も種切れになってしまって、ある山寺の尼僧と
(こしょうとがみっつうして、ふたりともにおにになったとかいうもんきりがたのかいだんをみじかくはなして)
小姓とが密通して、ふたりともに鬼になったとかいう紋切形の怪談を短く話して
(おくのあんどうのひをけしにいった。)
奥の行燈の火を消しに行った。
(まえにもいうとおり、あんどうのあるしょいんまでゆきつくには、くらいひろいざしきを)
前にもいう通り、行燈のある書院までゆき着くには、暗い広い座敷を
(いつまとおりぬけなければならないのであるが、なかはらはさいしょから2どもとおって)
五間通りぬけなければならないのであるが、中原は最初から二度も通って
(いるので、くらいなかでもたいていのけんとうはついていた。かれはへいきでざをたって、)
いるので、暗いなかでも大抵の見当は付いていた。彼は平気で座を起って、
(つぎのまのふすまをあけた。くらいざしきをつぎからつぎへとまっすぐにとおって、あんどうの)
次の間の襖をあけた。暗い座敷を次から次へと真っ直ぐに通って、行燈の
(すえてあるしょいんにゆきついたときに、ふとみかえると、いまとおってきたうしろの)
据えてある書院にゆき着いたときに、ふと見かえると、今通って来たうしろの
(ざしきのみぎのかべになにやらしろいものがかかっているようにぼんやりとみえた。)
座敷の右の壁に何やら白いものが懸かっているようにぼんやりと見えた。








