筆記試験対策!7
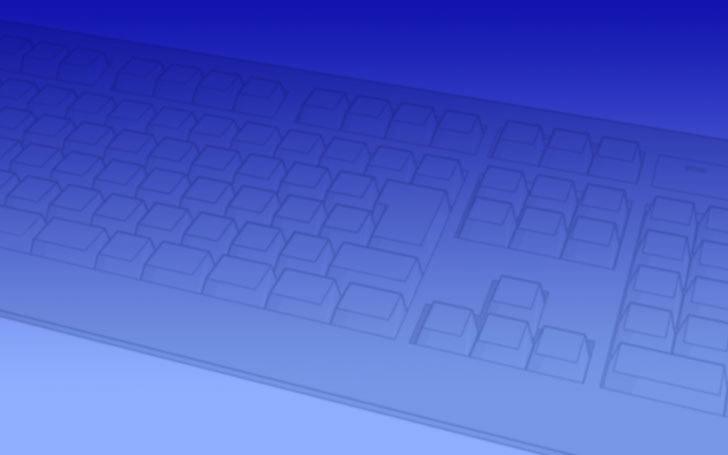
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 5329 | B++ | 5.4 | 97.3% | 151.8 | 832 | 23 | 12 | 2026/01/12 |
| 2 | のび | 5268 | B++ | 5.3 | 97.7% | 152.8 | 824 | 19 | 12 | 2026/02/14 |
| 3 | びび | 5249 | B+ | 5.3 | 98.1% | 156.6 | 838 | 16 | 12 | 2026/01/23 |
| 4 | のび | 5018 | B+ | 5.0 | 98.6% | 162.4 | 826 | 11 | 12 | 2026/02/13 |
| 5 | mimi | 4822 | B | 5.1 | 94.3% | 163.2 | 837 | 50 | 12 | 2026/01/16 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(ほゆうするちょうかくのかつよう、しかくじょうほうのかつよう、とーたるこみゅにけーしょん。)
保有する聴覚の活用、視覚情報の活用、トータルコミュニケーション。
(ほゆうするちょうかくのかつようは、ほちょうき、じんこうないじ、ほちょうえんじょしすてむがある。)
保有する聴覚の活用は、補聴器、人工内耳、補聴援助システムがある。
(はうりんぐとは、ほちょうきのみみせんからもれるぴーぴーというはっしんおん。)
ハウリングとは、補聴器の耳栓から漏れるピーピーという発信音。
(ほちょうきは、はこがた、みみかけがた、みみあながたがある。)
補聴器は、箱型、耳かけ型、耳あな型がある。
(はこがたは、おおきくてうんどうにふむきだが、そうさがよういでそうおんかでもつかいやすい。)
箱型は、大きくて運動に不向きだが、操作が容易で騒音下でも使いやすい。
(みみかけがたは、じかいにかけてしようする。こうれいしゃはそうちゃくにいわかんをおぼえることも。)
耳かけ型は、耳介にかけて使用する。高齢者は装着に違和感を覚えることも。
(みみあながたは、しぜんなきこえにちかいが、ほかのたいぷよりりとくがえにくい。)
耳あな型は、自然な聞こえに近いが、他のタイプより利得が得にくい。
(じんこうないじは、ないじにうめこまれたでんきょくでちょうしんけいをしげきしじょうほうをちゅうすうにとどける。)
人工内耳は、内耳に埋め込まれた電極で聴神経を刺激し情報を中枢に届ける。
(じんこうないじのおといれは、しゅじゅつから1から3しゅうかんごにおこなう。)
人工内耳の音入れは、手術から1~3週間後に行う。
(まっぴんぐとは、ひとりひとりにあわせてでんきょくをしげきするためのじょうほうをきめること。)
マッピングとは、一人一人に合わせて電極を刺激するための情報を決めること。
(じんこうないじはおといれによってはじめておとやこえがきこえるようになる。)
人工内耳は音入れによって初めて音や声が聞こえるようになる。
(じんこうないじは、ちょうりょくを30でしべるだいまでかいぜんさせる。)
人工内耳は、聴力を30dB台まで改善させる。


