谷崎潤一郎 刺青①
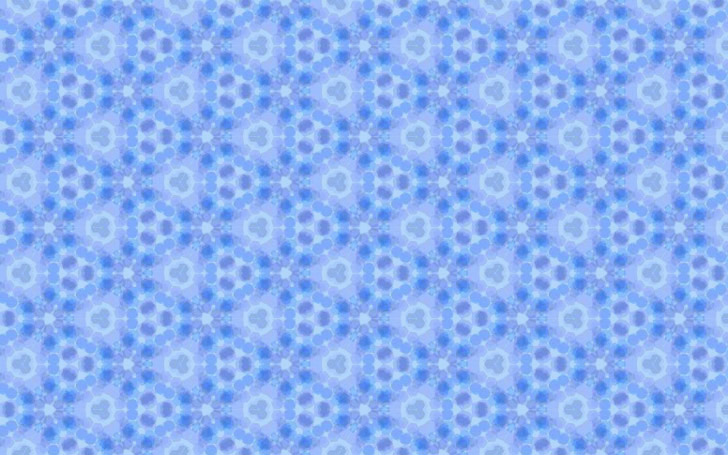
関連タイピング
-
かなりの難しさ
プレイ回数2363 長文864打 -
ヨルシカさんのただ君に晴れです!
プレイ回数1432 歌詞かな879打 -
打ち切れたらギネス記録!?が好評だったのでつくりました!!
プレイ回数4940 歌詞444打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数14万 歌詞かな167打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数3.5万 歌詞かな200打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数16万 歌詞1030打 -
AIが書いた文章です。
プレイ回数8611 長文1554打 -
5分間の速度部門の模擬試験です。打つ速度で級が決まります
プレイ回数94万 長文300秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(それはまだひとびとが「おろか」というたっといとくをもっていて、よのなかがいまのように)
其れはまだ人々が「愚」と云う貴い徳を持って居て、世の中が今のように
(はげしくきしみあわないじぶんであった。とのさまやわかだんなののどかなかおがくもらぬように、)
激しく軋み合わない時分であった。殿様や若旦那の長閑な顔が曇らぬように、
(ごてんじょちゅうやおいらんのわらいのたねがつきぬようにと、じょうぜつをうるおちゃぼうずだの)
御殿女中や華魁の笑いの種が盡きぬようにと、饒舌を売るお茶坊主だの
(ほうかんだのというしょくぎょうが、りっぱにそんざいしていけたほど、せけんがのんびりしていた)
幇間だのと云う職業が、立派に存在して行けた程、世間がのんびりして居た
(じぶんであった。おんなさだくろう、おんなじらいや、おんななるかみ、ーーとうじのしばいでもくさぞうしでも、)
時分であった。女定九郎、女自雷也、女鳴神、ーー当時の芝居でも草双紙でも、
(すべてうつくしいものはきょうしゃであり、みにくいものはじゃくしゃであった。だれもかれもこぞって)
すべて美しいものは強者であり、醜いものは弱者であった。誰も彼も挙って
(うつくしからんとつとめたあげくは、てんぴんのからだへえのぐをそそぎこむまでになった。)
美しからんと努めた揚句は、天稟の体へ絵の具を注ぎ込む迄になった。
(ほうれつな、あるいはけんらんな、せんといろとがそのころのひとびとのはだにおどった。)
芳烈な、或は絢爛な、線と色とが其の頃の人々の肌に躍った。
(うまみちをかようおきゃくは、みごとなほりもののあるかごかきをえらんで)
馬道を通うお客は、見事な刺青(ほりもの)のある駕籠舁(かごかき)を選んで
(のった。よしわら、たつみのおんなもうつくしいほりもののおとこにほれた。ばくと、とびのものはもとより、)
乗った。吉原、辰巳の女も美しい刺青の男に惚れた。博徒、鳶の者はもとより、
(ちょうにんからまれにはさむらいなどもいれずみをした。ときどきりょうごくでもよおされるしせいかいでは)
町人から稀には侍なども入墨をした。時々両国で催される刺青会では
(さんかしゃおのおのはだをたたいて、たがいにきばつないしょうをほこりあい、ひょうしあった。)
参加者おのおの肌を叩いて、互に奇抜な意匠を誇り合い、評しあった。
(せいきちというわかいほりものしのうでききがあった。あさくさのちゃりぶん、)
清吉と云う若い刺青師(ほりものし)の腕ききがあった。浅草のちゃり文、
(まつしまちょうのやつへい、こんこんじろうなどにもおとらぬめいしゅであると)
松島町の奴平(やつへい)、こんこん次郎などにも劣らぬ名手であると
(もてはやされて、なんじゅうにんのひとのはだは、かれのえふでのしたにぬめじとなって)
持て囃されて、何十人の人の肌は、彼の絵筆の下に絖地(ぬめじ)となって
(ひろげられた。しせいかいでこうひょうをはくすほりもののおおくはかれのてになったものであった。)
擴げられた。刺青会で好評を博す刺青の多くは彼の手になったものであった。
(だるまきんはぼかしぼりがとくいといわれ、からくさごんたはしゅぼりの)
達磨金はぼかし刺(ぼり)が得意と云われ、唐草権太は朱刺(しゅぼり)の
(めいしゅとたたえられ、せいきちはまたきけいなこうずとようえんなせんとでなをしられた。)
名手と讃えられ、清吉は又奇警な構図と妖艶な線とで名を知られた。
(もととよくにくにさだのかぜをしたって、うきよえしのとせいをしていただけに、)
もと豊国国貞の風を慕って、浮世絵師の
渡世(とせい)をして居ただけに、
(ほりものしにだらくしてからのせいきちにもさすがえかきらしいりょうしんと、えいかんとが)
刺青師に堕落してからの清吉にも流石
畫工(えかき)らしい良心と、鋭感とが
など
(のこっていた。かれのこころをひきつけるほどのひふとほねぐみとをもつひとでなければ、かれの)
残って居た。彼の心を惹きつける程の皮膚と骨組みとを持つ人でなければ、彼の
(ほりものをあがなうわけにはいかなかった。たまたまえがいてもらえるとしても、)
刺青を購(あがな)う訳には行かなかった。たまたま描いて貰えるとしても、
(いっさいのこうずとひようとをかれののぞむがままにして、そのうえたえがたいはりさきのくつうを、)
一切の構図と費用とを彼の望むがままにして、其の上堪え難い針先の苦痛を、
(ひとつきもふたつきもこらえねばならなかった。)
一と月も二た月もこらえねばならなかった。
(このわかいほりものしのこころには、ひとしらぬかいらくとしゅくがんとがひそんでいた。かれがひとびとのはだを)
この若い刺青師の心には、人知らぬ快楽と宿願とが潜んで居た。彼が人々の肌を
(はりでつきさすとき、しんくにちをふくんではれあがるにくのうずきにたえかねて、たいていのおとこは)
針で突き刺す時、真紅に血を含んで腫れ上る肉の疼きに堪えかねて、大抵の男は
(くるしきうめきごえをはっしたが、そのうめきごえがはげしければはげしいほど、かれはふしぎに)
苦しき呻き声を発したが、其の呻き声が激しければ激しい程、彼は不思議に
(いいがたきゆかいをかんじるのであった。ほりもののうちでもことにいたいといわれるしゅぼり、)
云い難き愉快を感じるのであった。刺青のうちでも殊に痛いと云われる朱刺、
(ぼかしぼり、ーーそれをもちうることをかれはことさらよろこんだ。いちにちへいきんごろっぴゃくほんのはりに)
ぼかし刺、ーー其れを用うる事を彼は殊更喜んだ。一日平均五六百本の針に
(さされて、いろあげをよくするためゆへつかってでてくるひとは、みな)
刺されて、色上げを良くするため湯へ浴(つか)って出て来る人は、皆
(はんしはんしょうのていでせいきちのあしもとにうちたおれたまま、しばらくはみうごきさえも)
半死半生の体(てい)で清吉の足下に打ち倒れたまま、暫くは身動きさえも
(できなかった。そのむざんなすがたをいつもせいきちはひややかにながめて、)
出来なかった。その無残な姿をいつも清吉は冷やかに眺めて、
(「さぞおいたみでがしょうなあ」といいながら、こころよさそうにわらっている。)
「嘸(さぞ)お痛みでがしょうなあ」と云いながら、快さそうに笑って居る。
(いくじのないおとこなどが、まるでちしごのくるしみのようにくちをゆがめ)
意気地のない男などが、まるで知死期(ちしご)の苦しみのように口を歪め
(はをくいしばり、ひいひいとひめいをあげることがあると、かれは、「おまえさんも)
歯を喰いしばり、ひいひいと悲鳴をあげる事があると、彼は、「お前さんも
(えどっこだ。しんぼうしなさい。ーーこのせいきちのはりはとびきりにいてえの)
江戸っ児だ。辛抱しなさい。ーーこの清吉の針は飛び切りに痛(いて)えの
(だから」こういって、なみだにうるむおとこのかおをよこめでみながら、かまわず)
だから」こう云って、涙にうるむ男の顔を横目で見ながら、かまわず
(ほっていった。またがまんづよいものがぐっときもをすえて、まゆひとつしかめず)
刺(ほ)って行った。また我慢づよい者がグッと胆を据えて、眉一つしかめず
(こらえていると、「ふむ、おまえさんはみかけによらねえつっぱりものだ。ーーだが)
怺えて居ると、「ふむ、お前さんは見掛けによらねえ突っ張者だ。ーーだが
(みなさい、いまにそろそろうずきだして、どうにもこうにもたまらないように)
見なさい、今にそろそろ疼き出して、どうにもこうにもたまらないように
(なろうから」と、しろいはをみせてわらった。)
なろうから」と、白い歯を見せて笑った。
(かれのねんらいのしゅくがんは、こうきあるびじょのはだをえて、それへおのれのたましいをほりこむことで)
彼の年来の宿願は、光輝ある美女の肌を得て、それへ己れの魂を刺り込む事で
(あった。そのおんなのそしつとようぼうとについては、いろいろのちゅうもんがあった。)
あった。その女の素質と容貌とに就いては、いろいろの注文があった。
(ただにうつくしいかお、うつくしいはだとのみでは、かれはなかなかまんぞくすることが)
啻(ただ)に美しい顔、美しい肌とのみでは、彼は中々満足する事が
(できなかった。えどじゅうのいろまちになをひびかせたおんなというおんなをしらべても、かれのきぶんに)
出来なかった。江戸中の色町に名を響かせた女と云う女を調べても、彼の気分に
(かなったあじわいとちょうしとはよういにみつからなかった。まだみぬひとのすがたかたちをこころに)
適った味わいと調子とは容易に見つからなかった。まだ見ぬ人の姿かたちを心に
(えがいて、さんねんよねんはむなしくあこがれながらも、かれはなおそのねがいをすてずにいた。)
描いて、三年四年は空しく憧れながらも、彼はなお其の願いを捨てずに居た。
(ちょうどよねんめのなつのとあるゆうべ、ふかがわのりょうりやひらせいのまえをとおり)
丁度四年目の夏のとあるゆうべ、深川の料理屋平清(ひらせい)の前を通り
(かかったとき、かれはふとかどぐちにまっているかごのすだれのかげから、まっしろなおんなの)
かかった時、彼はふと門口に待って居る駕籠の簾のかげから、真っ白な女の
(すあしのこぼれているのにきがついた。するどいかれのめには、にんげんのあしはそのかおと)
素足のこぼれて居るのに気がついた。鋭い彼の眼には、人間の足はその顔と
(おなじようにふくざつなひょうじょうをもってうつった。そのおんなのあしは、かれにとってはたっときにくの)
同じように複雑な表情を持って映った。その女の足は、彼に取っては貴き肉の
(ほうぎょくであった。おやゆびからおこってこゆびにおわるせんさいなごほんのゆびの)
宝玉であった。拇指(おやゆび)から起って小指に終る繊細な五本の指の
(ととのいかた、えのしまのうみべでとれるうすべにいろのかいにもおとらぬつめのいろあい、)
整い方、絵の島の海辺で獲れるうすべに色の貝にも劣らぬ爪の色合い、
(たまのようなきびすのまるみ、せいれつないわまのみずがたえずあしもとをあらうかと)
珠のような踵(きびす)のまる味、清冽な岩間の水が絶えず足下を洗うかと
(うたがわれるひふのじゅんたく。このあしこそは、やがておとこのいきちにこえふとり、おとこのむくろを)
疑われる皮膚の潤沢。この足こそは、やがて男の生血に肥え太り、男のむくろを
(ふみつけるあしであった。このあしをもつおんなこそは、かれがながねんたずねあぐんだ、)
蹈みつける足であった。この足を持つ女こそは、彼が永年たずねあぐんだ、
(おんなのなかのおんなであろうとおもわれた。せいきちはおどりたつむねをおさえて、そのひとのかおが)
女の中の女であろうと思われた。清吉は躍りたつ胸をおさえて、その人の顔が
(みたさにかごのあとをおいかけたが、にさんちょういくと、もうそのかげはみえなかった。)
見たさに駕籠の後を追いかけたが、二三町行くと、もう其の影は見えなかった。
(せいきちのあこがれごこちが、はげしきこいにかわってそのとしもくれ、ごねんめのはるもなかば)
清吉の憧れごこちが、激しき恋に変って其の年も暮れ、五年目の春も半ば
(おいこんだあるひのあさであった。かれはふかがわさがちょうのぐうきょで、ふさようじをくわえ)
老い込んだ或る日の朝であった。彼は深川佐賀町の寓居で、房楊枝をくわえ
(ながら、さびだけのぬれえんにおもとのはちをながめていると、にわのうらきどを)
ながら、錆竹の濡れ縁に萬年青(おもと)の鉢を眺めて居ると、庭の裏木戸を
(おとなうけはいがして、そでがきのかげから、ついぞみなれぬこむすめがはいって)
訪(おとな)うけはいがして、袖垣のかげから、ついぞ見馴れぬ小娘が這入って
(きた。それはせいきちがなじみのたつみのはおりからよこされたつかいのもので)
来た。それは清吉が馴染の辰巳の藝妓(はおり)から寄こされた使の者で
(あった。「ねえさんからこのはおりをおやかたへおてわたしして、なにかうらじへえもようを)
あった。「姐さんからこの羽織を親方へお手渡しして、何か裏地へ絵模様を
(かいてくださるようにおたのみもうせって・・・」と、むすめはうこんのふろしきを)
書いて下さるようにお頼み申せって・・・」と、娘は鬱金(うこん)の風呂敷を
(ほどいて、なかからいわいとじゃくのにがおえのたとうにつつまれたおんなばおりと、)
ほどいて、中から岩井杜若(とじゃく)の似顔畫のたとうに包まれた女羽織と、
(いっつうのてがみとをとりだした。そのてがみにははおりのことをくれぐれもたのんだすえに、)
一通の手紙とを取り出した。その手紙には羽織のことをくれぐれも頼んだ末に、
(つかいのむすめはちかぢかにわたしのいもうとぶんとしておざしきへでるはずゆえ、わたしのこともわすれずに、)
使の娘は近々に私の妹分として御座敷へ出る筈故、私の事も忘れずに、
(このこもひきたててやってくださいとしたためてあった。)
この娘(こ)も引き立ててやって下さいと認(したた)めてあった。
(「どうもみおぼえのないかおだとおもったが、それじゃおまえはこのごろこっちへ)
「どうも見覚えのない顔だと思ったが、それじゃお前は此の頃此方(こっち)へ
(きなすったのか」こういってせいきちは、しげしげとむすめのすがたをみまもった。としごろは)
来なすったのか」こう云って清吉は、しげしげと娘の姿を見守った。年頃は
(ようようじゅうろくかしちかとおもわれたが、そのむすめのかおは、ふしぎにもながいつきひをいろざとに)
漸う十六か七かと思われたが、その娘の顔は、不思議にも長い月日を色里に
(くらして、いくじゅうにんのおとこのたましいをもてあそんだとしまのようにものすごくととのっていた。それは)
暮らして、幾十人の男の魂を弄んだ年増のように物凄く整って居た。それは
(くにじゅうのつみとたからとのながれこむみやこのなかで、なんじゅうねんのむかしからいきかわり)
国中の罪と財(たから)との流れ込む都の中で、何十年の昔から生き代り
(しにかわったみめうるわしいおおくのだんじょの、ゆめのかずかずからうまれいづべききりょうであった。)
死に代ったみめ麗しい多くの男女の、夢の数々から生れ出づべき器量であった。
(「おまえはきょねんのろくがつごろ、ひらせいからかごでかえったことがあろうがな」こうたずね)
「お前は去年の六月ごろ、平清から駕籠で帰ったことがあろうがな」こう訊ね
(ながら、せいきちはむすめをえんへかけさせて、びんごおもてのだいにのったこうちなすあしをしさいに)
ながら、清吉は娘を縁へかけさせて、備後表の台に乗った巧緻な素足を仔細に
(ながめた。「ええ、あのじぶんなら、まだおとうさんがいきていたから、ひらせいへも)
眺めた。「ええ、あの時分なら、まだお父さんが生きて居たから、平清へも
(たびたびまいりましたのさ」と、むすめはみょうなしつもんにわらってこたえた。「ちょうどこれで)
たびたびまいりましたのさ」と、娘は妙な質問に笑って答えた。「丁度これで
(あしかけごねん、おれはおまえをまっていた。かおをみるのははじめてだが、おまえのあしには)
足かけ五年、己はお前を待って居た。顔を見るのは始めてだが、お前の足には
(おぼえがある。ーーおまえにみせてやりたいものがあるから、あがってゆっくりあそんで)
覚えがある。ーーお前に見せてやりたいものがあるから、上ってゆっくり遊んで
(いくがいい」と、せいきちはいとまをつげてかえろうとするむすめのてをとって、おおかわのみずに)
行くがいい」と、清吉は暇を告げて帰ろうとする娘の手を取って、大川の水に
(のぞむにかいざしきへあんないしたあと、まきものをにほんとりだして、まずそのひとつをむすめのまえに)
臨む二階座敷へ案内した後、巻物を二本とり出して、先ず其の一つを娘の前に
(くりひろげた。それはいにしえのぼうくんちゅうおうのちょうひ、)
繰り展(ひろ)げた。それは古の暴君紂王(ちゅうおう)の寵妃(ちょうひ)、
(ばっきをえがいたえであった。るりさんごをちりばめたきんかんのおもさにえたえぬ)
末喜(ばっき)を描いた絵であった。瑠璃珊瑚を鏤めた金冠の重さに得堪えぬ
(なよやかなからだを、ぐったりこうらんにもたれて、らりょうのもすそをきざはしのちゅうだんに)
なよやかな体を、ぐったり勾欄に靠れて、羅綾の裳裾を階(きざはし)の中段に
(ひるがえし、みぎてにおおさかずきをかたむけながら、いましもていぜんにけいせられんとする)
ひるがえし、右手に大杯を傾けながら、今しも庭前に刑せられんとする
(いけにえのおとこをながめているきさきのふぜいといい、てつのくさりでししをどうばしらへ)
犠牲(いけにえ)の男を眺めて居る妃の風情と云い、鉄の鎖で四肢を銅柱へ
(ゆいつけられ、さいごのうんめいをまちかまえつつ、きさきのまえにあたまをうなだれ、めを)
縛(ゆ)いつけられ、最後の運命を待ち構えつつ、妃の前に頭をうなだれ、眼を
(とじたおとこのかおいろといい、ものすごいまでにたくみにえがかれていた。むすめはしばらくこのきかいなえの)
閉じた男の顔色と云い、物凄い迄に巧に描かれて居た。娘は暫くこの奇怪な絵の
(おもてをみいっていたが、しらずしらずそのひとみはかがやきそのくちびるはふるえた。あやしくも)
面を見入って居たが、知らず識らず其の瞳は輝き其の唇は顫えた。怪しくも
(そのかおはだんだんときさきのかおににかよってきた。)
その顔はだんだんと妃の顔に似通って来た。
(むすめはそこにかくれたるしんの「おのれ」をみいだした。)
娘は其処に隠れたる真の「己」を見出した。








