【第122回 検定試験】4級
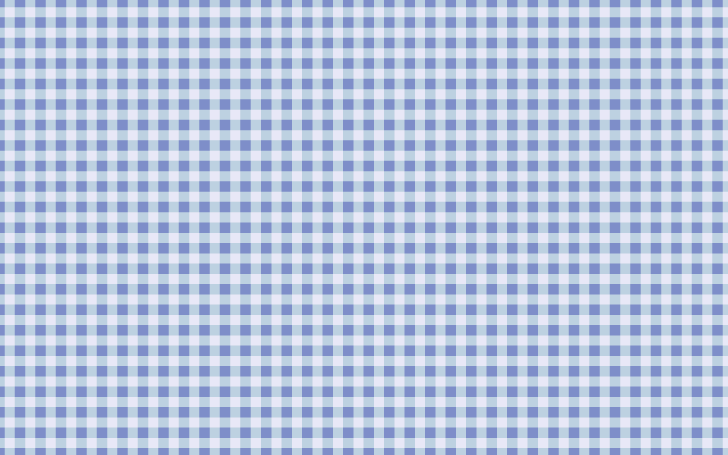
日本語ワープロ検定試験
第122回(令和2年2月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6661 | S+ | 7.0 | 94.4% | 139.6 | 988 | 58 | 20 | 2025/12/23 |
| 2 | ビッグマム | 6181 | A++ | 6.4 | 96.3% | 153.2 | 984 | 37 | 20 | 2026/02/14 |
| 3 | sss | 6117 | A++ | 6.4 | 95.7% | 154.3 | 988 | 44 | 20 | 2026/01/28 |
| 4 | nao@koya | 5231 | B+ | 5.3 | 97.1% | 183.3 | 988 | 29 | 20 | 2025/12/31 |
関連タイピング
-
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9637 長文かな490打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9643 長文かな694打 -
基礎練習にどうぞ!
プレイ回数4527 長文60秒 -
DREAMS COME TRUE
プレイ回数1345 歌詞801打 -
DREAMS COME TRUE
プレイ回数2710 歌詞736打 -
スピッツ
プレイ回数1974 歌詞かな761打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数8567 長文1009打 -
基礎練習にどうぞ!
プレイ回数3518 長文60秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(はさみは、かならずといっていいほどかくかていにあるみぢかなどうぐのひとつでしょう。)
ハサミは、必ずといっていいほど各家庭にある身近な道具の一つでしょう。
(そのれきしはふるく、いまから3000ねんほどまえのぎりしあでは、)
その歴史は古く、今から3000年ほど前のギリシアでは、
(ようもうをきりとるためにもちいられていたようです。)
羊毛を切り取るために用いられていたようです。
(これはいとをきるときにつかうような、にぎってつかうたいぷでした。)
これは糸を切る時に使うような、握って使うタイプでした。
(げんざいわたしたちがつかっている2まいのはをねじでとめたかたちのはさみについては、)
現在わたしたちが使っている2枚の刃をネジで留めた形のハサミについては、
(こだいろーまじだいにかんがえられたといわれています。)
古代ローマ時代に考えられたといわれています。
(にほんでもっともふるいはさみは、ぎりしあがたのもので、)
日本で最も古いハサミは、ギリシア型のもので、
(ならにある7せいきのこふんからしゅつどしています。)
奈良にある7世紀の古墳から出土しています。
(そして、ろーまのようなたいぷのはさみは)
そして、ローマのようなタイプのハサミは
(しょうそういんにせいどうでつくられたものがあります。)
正倉院に青銅で作られたものがあります。
(とうじ、わがくにではかみやぬのをきるのにはこがたなをりようしていました。)
当時、わが国では紙や布を切るのには小刀を利用していました。
(そのためようとはかぎられていたようです。)
そのため用途は限られていたようです。
(めいじじだいになって、ようふくがつくられるようになると、)
明治時代になって、洋服が作られるようになると、
(いまつかっているようなようばさみがゆにゅうされ、)
今使っているような洋バサミが輸入され、
(こくないでもせいぞうされるようになっていきます。)
国内でも製造されるようになっていきます。
(なぜはさみは、ものをきることができるのでしょうか。)
なぜハサミは、ものを切ることができるのでしょうか。
(じつは、てこのげんりをりようしています。)
実は、テコの原理を利用しています。
(もちてのぶぶんがりきてんに、ねじがしてんとなり、そのさきがさようてんにあたります。)
持ち手の部分が力点に、ネジが支点となり、その先が作用点にあたります。
(このこうぞうによってよわいちからでも、)
この構造によって弱い力でも、
(かんたんにきることができるようになっているのです。)
簡単に切ることができるようになっているのです。







