【第116回 検定試験】1級
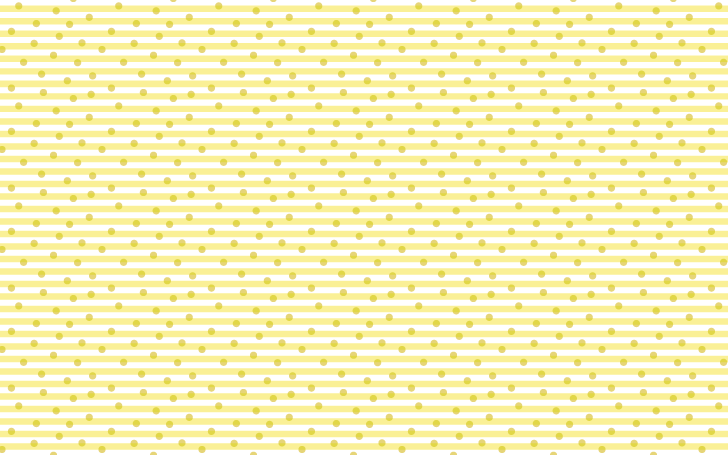
日本語ワープロ検定
第116回(平成30年10月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiga | 6368 | S | 6.5 | 97.2% | 323.8 | 2121 | 59 | 45 | 2026/01/02 |
| 2 | PLMKJNB4 | 6194 | A++ | 6.7 | 92.1% | 313.0 | 2120 | 181 | 45 | 2026/01/17 |
| 3 | sss | 5804 | A+ | 6.1 | 95.1% | 346.6 | 2119 | 107 | 45 | 2026/01/27 |
| 4 | nao@koya | 4953 | B | 5.1 | 96.4% | 412.4 | 2120 | 77 | 45 | 2026/01/04 |
| 5 | nadesico | 4847 | B | 5.0 | 96.9% | 423.9 | 2122 | 67 | 45 | 2026/01/28 |
関連タイピング
-
プレイ回数6230 長文1591打
-
プレイ回数6122 長文1314打
-
プレイ回数4731 長文1140打
-
プレイ回数3663 長文かな1301打
-
プレイ回数8204 長文1007打
-
プレイ回数4343 長文2623打
-
プレイ回数4.4万 長文1048打
-
プレイ回数1万 長文1027打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(うだつということばをきいて、なにをさしているのか、)
うだつという言葉を聞いて、何を指しているのか、
(すぐにわかるでしょうか。)
すぐにわかるでしょうか。
(これはふるくからにほんかおくのけいしきで、)
これは古くから日本家屋の形式で、
(とうしょはやねのてっぺんにあるきをささえるはしらのことをいいました。)
当初は屋根のてっぺんにある木を支える柱のことをいいました。
(ちいきによっては、ちゅうせいいこう、)
地域によっては、中世以降、
(これをさらにいちだんたかくして)
これをさらに一段高くして
(ちいさなやねをつけたこうぞうぶつがもうけられるようになります。)
小さな屋根を付けた構造物が設けられるようになります。
(じたくととなりのいえのあいだがすこしもちあがったようにみえるところで、)
自宅と隣の家の間が少し持ち上がったように見える所で、
(これもうだつとよばれるようです。)
これもうだつと呼ばれるようです。
(へいあんじだいには、うだちとよんだそうですが、)
平安時代には、うだちと呼んだそうですが、
(むろまちじだいいこうにこれがてんじて、)
室町時代以降にこれが転じて、
(うだつとしょうされるようになりました。)
うだつと称されるようになりました。
(そのご、まちやがれんぞくしてたてられたばあいに、)
その後、町屋が連続して建てられた場合に、
(かさいなどのひがいがひろがらないための)
火災などの被害が広がらないための
(ぼうかへきとしてのやくわりもはたすようになります。)
防火壁としての役割も果たすようになります。
(これをけんちくするには、それなりのひようがはっせいするため、)
これを建築するには、それなりの費用が発生するため、
(いえのざいりょくをしめすしんぼるとしてのいみあいももっていたようです。)
家の財力を示すシンボルとしての意味合いも持っていたようです。
(あきないをしているひとびとをちゅうしんにして、)
商いをしている人々を中心にして、
(とおくからみてもわかるようにりっぱなかたちのものがつくられました。)
遠くから見ても分かるように立派な形のものが造られました。
(そのいしょうには、)
その意匠には、
など
(かもんやとりひきしているしなをもしたでざいんがさいようされることもあったようです。)
家紋や取引している品を模したデザインが採用されることもあったようです。
(げんざいでももちいられる「うだつがあがらない」というかんようくのごげんは、)
現在でも用いられる「うだつが上がらない」という慣用句の語源は、
(まさにここにあるといわれています。)
まさにここにあるといわれています。
(しゅっせできない、せいかつがよくならないことをこうひょうげんするのです。)
出世できない、生活が良くならないことをこう表現するのです。
(このうだつですが、げんざいまでのこされているものは、あまりおおくありません。)
このうだつですが、現在まで残されているものは、あまり多くありません。
(ほぞんされているちいきは、)
保存されている地域は、
(とくしまのみましやつるぎちょう、ぎふけんみのしなどがゆうめいだといいます。)
徳島の美馬市やつるぎ町、岐阜県美濃市などが有名だといいます。
(それぞれのいえがきそうようにして、ごうかなさいくをほどこしているので、)
それぞれの家が競うようにして、豪華なサイクを施しているので、
(げいじゅつひんといえるほどみごとなつくりになっています。)
芸術品といえるほど見事な造りになっています。
(ふるくからのりっぱなにほんかおくがたちならぶそのうつくしいまちなみは、)
古くからの立派な日本家屋が立ち並ぶその美しい町並みは、
(かんこうすぽっととしてもにんきのようです。)
観光スポットとしても人気のようです。
(このほかにも、にほんかおくにほどこされるけんちくいしょうには、)
この他にも、日本家屋に施される建築意匠には、
(でざいんせいのたかいものがかずおおくそんざいしているようです。)
デザイン性の高いものが数多く存在しているようです。
(たとえば、むしかごのようにめのこまかいたてのこうしがとうかんかくにならんでいるまどがあります。)
例えば、虫籠のように目の細かい縦の格子が等間隔に並んでいる窓があります。
(うるしやづくりとよばれるたてものの2かいに、)
漆屋造りと呼ばれる建物の2階に、
(たてにかいこうぶをもうけたこていまどのことで、)
縦に開口部を設けた固定窓のことで、
(かぜとおしやあかりとりのためにつけられています。)
風通しや明かり取りのために付けられています。
(これも、えどじだいのものはちょうえんけいでちいさいものがおおかったのですが、)
これも、江戸時代のものは長円形で小さいものが多かったのですが、
(ときとともにおおがたかしたようで、)
時とともに大型化したようで、
(そのかたちからけんちくねんだいがわかるとされています。)
その形から建築年代が分かるとされています。
(かいがいからのかんこうきゃくがぞうかけいこうにあり、)
海外からの観光客が増加傾向にあり、
(にほんのでんとうやびがくがこくがいでもみとめられています。)
日本の伝統や美学が国外でも認められています。
(わたしはじこくのぞうけいぶつについて、)
わたしは自国の造形物について、
(まだまだしらないことがかずおおくあるので、)
まだまだ知らないことが数多くあるので、
(じっさいにじぶんのめでみてそのかちをたしかめにいきたいとかんがえています。)
実際に自分の目で見てその価値を確かめにいきたいと考えています。







