【第119回 検定試験】1級
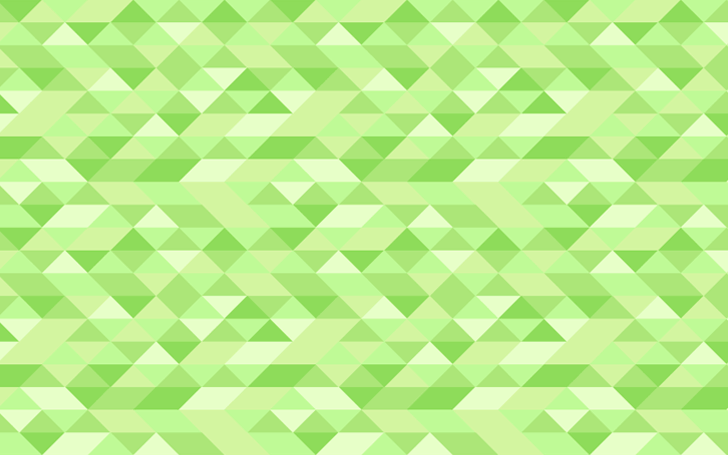
日本語ワープロ検定試験
第119回(令和元年7月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6224 | A++ | 6.9 | 90.8% | 308.8 | 2136 | 214 | 41 | 2026/01/20 |
| 2 | sss | 6095 | A++ | 6.3 | 95.5% | 334.7 | 2139 | 99 | 41 | 2026/01/27 |
| 3 | Tak | 5337 | B++ | 5.4 | 97.1% | 388.2 | 2135 | 63 | 41 | 2026/02/05 |
| 4 | nao@koya | 5206 | B+ | 5.3 | 96.7% | 397.6 | 2142 | 72 | 41 | 2026/01/01 |
| 5 | ひろし | 4962 | B | 5.1 | 97.0% | 418.3 | 2142 | 66 | 41 | 2026/02/04 |
関連タイピング
-
プレイ回数3850 長文1668打
-
プレイ回数6230 長文1591打
-
プレイ回数3663 長文かな1301打
-
プレイ回数8177 長文かな1045打
-
プレイ回数1.2万 長文かな1009打
-
プレイ回数6122 長文1314打
-
プレイ回数4.4万 長文1048打
-
プレイ回数4343 長文2623打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(りょうりをするさい、よくつかわれるどうぐにはしがあります。)
料理をする際、よく使われる道具に箸があります。
(もちろんたべるときにもちいられることがおおいものですが、)
もちろん食べるときに用いられることが多いものですが、
(これはりょうりようとしてもふるくからしようされています。)
これは料理用としても古くから使用されています。
(しょくざいをつかんだりまぜたり、もりつけたりと、)
食材をつかんだり混ぜたり、盛り付けたりと、
(ひじょうにつかいがってのよいどうぐです。)
非常に使い勝手の良い道具です。
(ようとべつにさまざまなしゅるいがあるようですが、)
用途別にさまざまな種類があるようですが、
(そのなかに「まなばし」というものがあります。)
その中に「まなばし」というものがあります。
(せんたんがほそくなったきんぞくせいのながい2ほんのぼうで、)
先端が細くなった金属製の長い2本の棒で、
(てでにぎるぶぶんにはすべらないようきのえがついており、すべりにくくなっています。)
手で握る部分には滑らないよう木の柄がついており、滑りにくくなっています。
(いっぱんかていでめにするきかいは、すくないかもしれません。)
一般家庭で目にする機会は、少ないかもしれません。
(かたちはさいばしににていますがそのようとはことなります。)
形は菜箸に似ていますがその用途は異なります。
(2ほんをききてではないほうでもち、まないたにのせたにくやさかなをおさえるのです。)
2本を利き手ではない方で持ち、まな板に載せた肉や魚を押さえるのです。
(そしてほうちょうでさばくことで、ちょくせつてをふれなくてすむのです。)
そして包丁でさばくことで、直接手を触れなくて済むのです。
(さいばしでためしてみましたが、ぶきようなわたしはとてもくせんしました。)
菜箸で試してみましたが、不器用なわたしはとても苦戦しました。
(なまのにくやさかなはすべりやすいので、)
生の肉や魚は滑りやすいので、
(やはりよいどうぐとぷろのわざがひつようだとかんじました。)
やはり良い道具とプロの技が必要だと感じました。
(てをつかったほうがかんたんのようにおもいますが、なにかりゆうがあるのでしょうか。)
手を使った方が簡単のように思いますが、何か理由があるのでしょうか。
(このはしのきげんをみていくと、)
この箸の起源を見ていくと、
(むろまちじだいのぶんけんにそのそんざいがしめされています。)
室町時代の文献にその存在が示されています。
(そのいっぽうで、あるけんきゅうしゃは)
その一方で、ある研究者は
など
(それよりもはるかにむかしからつかわれていたとすいそくしており、)
それよりもはるかに昔から使われていたと推測しており、
(さいれいでくもつをよういするかかりがそざいにてをふれてよごさないために)
祭礼で供物を用意する係が素材に手を触れて汚さないために
(かんがえだしたといいます。)
考え出したといいます。
(これがじだいとともにいっしゅのしょーとしてへんかしていったとものべています。)
これが時代とともに一種のショーとして変化していったとも述べています。
(ふるくからしんじではにくもさかなもなまのまましょくされていました。)
古くから神事では肉も魚も生のまま食されていました。
(そして、そうしたもよおしのふんいきをもりあげるためのだしもののいっかんとして、)
そして、そうした催しの雰囲気を盛り上げるための出し物の一環として、
(きゃくじんのまえでほうちょうさばきをひろうしたのです。)
客人の前で包丁さばきを披露したのです。
(やがてむろまちじだいになると、そのみちのぷろがしゅつげんし、)
やがて室町時代になると、その道のプロが出現し、
(まなばしをたずさえたかれらはばくふやだいみょうにつかえるしょくぎょうとなり、)
まなばしを携えた彼らは幕府や大名に仕える職業となり、
(いえもとせいどもかくりつされたようです。)
家元制度も確立されたようです。
(ところが、19せいきにはいると、まなばしのでばんはへっていきます。)
ところが、19世紀に入ると、まなばしの出番は減っていきます。
(よういんのひとつはこんだてのへんかだといわれています。)
要因の一つは献立の変化だといわれています。
(なんばんからあげものがしょうかいされ、)
南蛮から揚げ物が紹介され、
(ちゃのゆのりゅうこうによってかいせきりょうりがはったつするなど、こんだてはたようかします。)
茶の湯の流行によって懐石料理が発達するなど、献立は多様化します。
(さらに、ちゅうごくからさまざまなしょくざいやちょうりほうなどがつたわって、)
さらに、中国からさまざまな食材や調理法などが伝わって、
(にほんのしょくたくはへんぼうをとげます。)
日本の食卓は変貌を遂げます。
(あじやもりつけがはなやいだため、)
味や盛り付けが華やいだため、
(えんかいのだしものとしてたようされることはすくなくなりましたが、)
宴会の出し物として多用されることは少なくなりましたが、
(いまでもしんじなどでは、ほんらいのつかわれかたをしています。)
今でも神事などでは、本来の使われ方をしています。
(さらに、ぷろのりょうりにんはそれをもりつけたときにしようしていますが、)
さらに、プロの料理人はそれを盛り付けた時に使用していますが、
(しょくざいにちょくせつてをふれないといういみではおなじようとだといえるでしょう。)
食材に直接手を触れないという意味では同じ用途だといえるでしょう。







