【第119回 検定試験】準1級
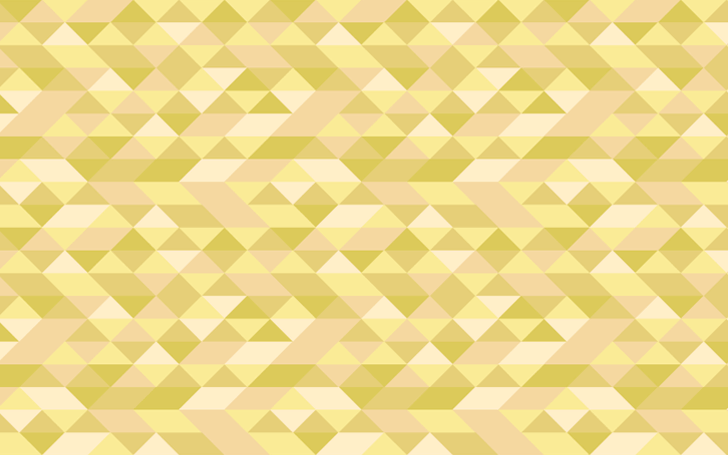
日本語ワープロ検定試験
第119回(令和元年7月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sss | 5769 | A+ | 6.0 | 95.6% | 293.8 | 1776 | 81 | 31 | 2026/01/27 |
| 2 | PLMKJNB4 | 5656 | A | 6.3 | 90.4% | 280.2 | 1772 | 187 | 31 | 2025/12/22 |
| 3 | nao@koya | 5152 | B+ | 5.3 | 95.7% | 330.3 | 1781 | 79 | 31 | 2026/01/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数8204 長文1007打
-
プレイ回数6230 長文1591打
-
プレイ回数3663 長文かな1301打
-
プレイ回数6122 長文1314打
-
プレイ回数9449 長文1025打
-
プレイ回数4343 長文2623打
-
プレイ回数4731 長文1140打
-
プレイ回数4.4万 長文1048打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しょうわちゅうきという、げんだいのようにかんたんにじょうほうをきょうゆうするほうほうがすくないじだいに、)
昭和中期という、現代のように簡単に情報を共有する方法が少ない時代に、
(にほんじゅうでだいひっとしたおもちゃがあります。)
日本中で大ヒットしたおもちゃがあります。
(それはとうじ「みずのみどり」とよばれたしょうひんです。)
それは当時「水飲み鳥」と呼ばれた商品です。
(わがやではものもちのよいははがだれかからゆずりうけ、)
わが家では物持の良い母が誰かから譲り受け、
(いちどもつかわずにしまいこんでいたのですが、)
一度も使わずにしまい込んでいたのですが、
(りゅうこうがすぎさってからおしいれからだしてきたことがありました。)
流行が過ぎ去ってから押し入れから出してきたことがありました。
(むかしひっとしたときかされてもぴんとこなかったのですが、)
昔ヒットしたと聞かされてもピンと来なかったのですが、
(うごきがおもしろいのであきずにながめていたきおくがあります。)
動きが面白いので飽きずに眺めていた記憶があります。
(そのとりは、なぜかしるくはっとできかざっており、)
その鳥は、なぜかシルクハットで着飾っており、
(どうのぶぶんはほそながいがらすかんで、なかにはちゃくしょくしたえきたいがはいっていました。)
胴の部分は細長いガラス管で、中には着色した液体が入っていました。
(あたまにはめとくちばしがあり、たまごがたのおしりにはみどりのはねがついています。)
頭には目とくちばしがあり、卵形のお尻には緑の羽根が付いています。
(みずをいれたこっぷをまえにおいて、さいしょだけすこしあたまをおすと、)
水を入れたコップを前に置いて、最初だけ少し頭を押すと、
(なかのみずにくちばしをひたすので、まるでそれをのんでいるかのようにみえます。)
中の水にくちばしを浸すので、まるでそれを飲んでいるかのように見えます。
(そのご、すぐにあたまをあげてしばらくはぜんごにゆれていますが、)
その後、すぐに頭を上げてしばらくは前後に揺れていますが、
(やがてがらすかんのなかのえきたいがいどうすると、またみずのなかにくちのさきをひたします。)
やがてガラス管の中の液体が移動すると、また水の中に口の先を浸します。
(こうしてなんどもどうようのことをくりかえすのです。)
こうして何度も同様のことを繰り返すのです。
(こどものころは、ぜんまいもなくでんちもいれてないのに、)
子供のころは、ゼンマイもなく電池も入れてないのに、
(いっていのどうさをけいぞくするということがふしぎでなりませんでした。)
一定の動作を継続するということが不思議でなりませんでした。
(こうぞうをしらべてみると、きかねつによってしょうじる)
構造を調べてみると、気化熱によって生じる
(わずかなおんどさによってうごいていたということがわかりました。)
わずかな温度差によって動いていたということがわかりました。
など
(おしりのぶぶんにはあかやあおなどにちゃくしょくされたえきたいがはいっていますが、)
お尻の部分には赤や青などに着色された液体が入っていますが、
(これはしつおんでへんか、きかするものです。)
これは室温で変化、気化するものです。
(そのうごきをめでおえるようにいろをつけているのでしょう。)
その動きを目で追えるように色を付けているのでしょう。
(とりのがらすのなかは、このえきたいときたいでみたされています。)
鳥のガラスの中は、この液体と気体で満たされています。
(まずとうぶがぬらされると、それがじょうはつしてきかねつによってひえます。)
まず頭部がぬらされると、それが蒸発して気化熱によって冷えます。
(するとじょうぶのきあつがさがるため、どうたいとのきあつさによってえきめんがじょうしょうします。)
すると上部の気圧が下がるため、胴体との気圧差によって液面が上昇します。
(そしてえきたいがとうぶへながれこんでおもくなってさがり、とりががらすかんをとおって、)
そして液体が頭部へ流れ込んで重くなって下がり、鳥がガラス管を通って、
(おしりのほうにいどうし、おもくなるので、とりはおきあがります。)
お尻の方に移動し、重くなるので、鳥は起き上がります。
(そのごは、あたまをひやすみずがなくなるまでこのどうさをくりかえします。)
その後は、頭を冷やす水がなくなるまでこの動作を繰り返します。
(こどもだけでなくおとなまでもがたんきゅうしんをくすぐられる、)
子供だけでなく大人までもが探究心をくすぐられる、
(たいへんよくかんがえられたおもちゃなのです。)
大変よく考えられたおもちゃなのです。







