【第122回 検定試験】準2級
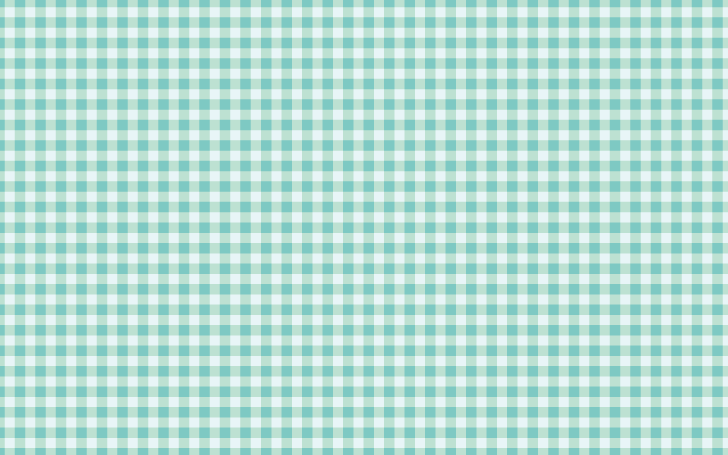
日本語ワープロ検定試験
第122回(令和2年2月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6124 | A++ | 6.6 | 92.6% | 214.7 | 1429 | 114 | 27 | 2025/12/23 |
| 2 | sss | 5771 | A+ | 6.0 | 96.2% | 237.9 | 1428 | 55 | 27 | 2026/01/28 |
| 3 | nao@koya | 5333 | B++ | 5.4 | 98.2% | 263.6 | 1431 | 25 | 27 | 2025/11/05 |
| 4 | か1 | 4421 | C+ | 4.6 | 95.7% | 309.6 | 1432 | 63 | 27 | 2026/01/07 |
関連タイピング
-
プレイ回数1583 長文1788打
-
プレイ回数1764 長文2018打
-
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9633 長文かな490打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9634 長文かな694打 -
倖田來未
プレイ回数812 歌詞748打 -
スピッツ
プレイ回数1970 歌詞かな761打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数8560 長文1009打 -
プレイ回数1309 長文2331打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(われわれじんるいが、じかんというがいねんを)
われわれ人類が、時間という概念を
(かんがえるようになったのはいつのことでしょう。)
考えるようになったのはいつのことでしょう。
(でんきなどもなくしぜんとともにくらしていたむかしのひとびとにとって、)
電気などもなく自然と共に暮らしていた昔の人々にとって、
(よあけとしょうご、ひぐれはせいかつのおおきなくぎりでした。)
夜明けと正午、日暮れは生活の大きな区切りでした。
(たとえば、にちぼつまであとどれくらいあるかがわかれば、のこりどれだけはたらけるか、)
例えば、日没まであとどれくらいあるかが分かれば、残りどれだけ働けるか、
(けんとうをつけることができます。)
見当をつけることができます。
(そこでかれらはたいようのたかさをみておおよそのじかんをしったのではないでしょうか。)
そこで彼らは太陽の高さを見ておおよその時間を知ったのではないでしょうか。
(そのうち、かげのながさやいちをかくにんすればよいことをおもいつきます。)
そのうち、影の長さや位置を確認すればよいことを思い付きます。
(そして、じめんにぼうをたててめもりをつけたにちじどけいが)
そして、地面に棒を立てて目盛りを付けた日時時計が
(つくられるようになっていくのです。)
作られるようになっていくのです。
(これは、いまからおよそ5せんねんから6せんねんまえの)
これは、今からおよそ5千年から6千年前の
(こだいえじぷとでつくられたのがさいしょだといわれています。)
古代エジプトで作られたのが最初だといわれています。
(たいようがほとんどいつもあたまのまうえをとおるこのちでは、)
太陽がほとんどいつも頭の真上を通るこの地では、
(ぼうをすいへいのいたにとりつけたもちはこびのできるにちじどけいがつかわれていました。)
棒を水平の板に取り付けた持ち運びのできる日時時計が使われていました。
(ごぜんちゅうはそれをひがしにむけ、ごごになるとにしにむけてしようしていたようです。)
午前中はそれを東に向け、午後になると西に向けて使用していたようです。
(では、1にちはなぜ24じかんになったのでしょう。)
では、1日はなぜ24時間になったのでしょう。
(こだいえじぷとのひとびとは、ひるとよるをわけて、)
古代エジプトの人々は、昼と夜を分けて、
(それぞれを12とうぶんしてときをしるほうほうをもちいていました。)
それぞれを12等分して時を知る方法を用いていました。
(しかし、このほうほうではきせつによってひるとよるのじかんのながさがかわってしまうため、)
しかし、この方法では季節によって昼と夜の時間の長さが変わってしまうため、
(1たんいあたりのながさもいっていではありません。)
1単位あたりの長さも一定ではありません。
など
(そのため、1にちをきんとうに24ぶんかつするていじほうがていしょうされ、)
そのため、1日を均等に24分割する定時法が提唱され、
(げんざいにいたるとされています。)
現在に至るとされています。
(にほんでも、1872ねんまではりょうほうともつかわれており、)
日本でも、1872年までは両方とも使われており、
(このとしにくにのこよみがたいようれきにかわったことにともない、)
この年に国の暦が太陽暦に変わったことに伴い、
(ていじほうがさいようされるようになります。)
定時法が採用されるようになります。
(あたりまえのようににんしきしているときのがいねんにもこのようなれきしがあり、)
当たり前のように認識している時の概念にもこのような歴史があり、
(もしかすると、これもまたへんかしていくものなのかもしれません。)
もしかすると、これもまた変化していくものなのかもしれません。







