宅建(相続)
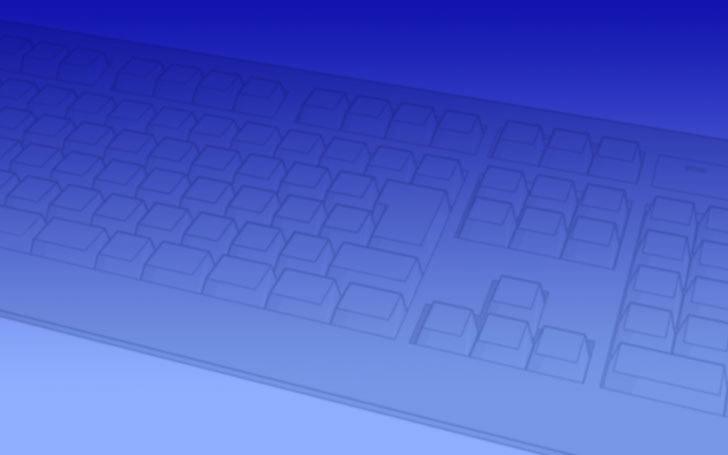
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subaru | 7581 | 神 | 7.8 | 96.3% | 223.7 | 1763 | 67 | 27 | 2025/10/02 |
関連タイピング
-
宅建試験に向けて
プレイ回数168長文1142打 -
宅建 業務上の規則
プレイ回数3582長文2484打 -
プレイ回数25長文かな1709打
-
プレイ回数46長文2217打
-
プレイ回数46長文4578打
-
宅建合格したい!
プレイ回数760長文1977打 -
プレイ回数29長文1186打
-
プレイ回数28長文4144打
問題文
(そうぞくにんとなるのは、ひそうぞくにんのはいぐうしゃとけつぞくである。)
相続人となるのは、被相続人の配偶者と血族である。
(けつぞくのなかでそうぞくじゅんいがだいいちじゅんい、だいにじゅんい、だいさんじゅんいとなるのは)
血族の中で相続順位が第一順位、第二順位、第三順位となるのは
(それぞれこ、ちょっけいそんぞく、きょうだいしまいである。)
それぞれ子、直系尊属、兄弟姉妹である。
(はいぐうしゃとこがそうぞくにんのばあい、そうぞくぶんははいぐうしゃがにぶんのいち、こがにぶんのいち。)
配偶者と子が相続人の場合、相続分は配偶者が二分の一、子が二分の一。
(はいぐうしゃとちょっけいそんぞくがそうぞくにんのばあい、)
配偶者と直系尊属が相続人の場合、
(そうぞくぶんは、はいぐうしゃがさんぶんのに、ちょっけいそんぞくがさんぶんのいち。)
相続分は、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一。
(はいぐうしゃときょうだいしまいがそうぞくにんのばあい、)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、
(そうぞくぶんは、はいぐうしゃがよんぶんのさん、きょうだいしまいがよんぶんのいち。)
相続分は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一。
(だいしゅうそうぞくのはっせいげんいんは、そうぞくにんとなるべきものが、)
代襲相続の発生原因は、相続人となるべきものが、
(そうぞくかいしまえにしぼう、けっかく、はいじょによってそうぞくにんでなくなっていたこと。)
相続開始前に死亡、欠格、廃除によって相続人でなくなっていたこと。
(いさんぶんかつのこうりょくがはっせいするのはそうぞくかいしのとき。)
遺産分割の効力が発生するのは相続開始の時。
(そうぞくによりけんりのしょうけいは、ほうていそうぞくぶんをこえるぶぶんについて、)
相続により権利の承継は、法定相続分を超える部分について、
(だいさんしゃにたいこうするためにはたいこうようけんをそなえることがひつよう。)
第三者に対抗するためには対抗要件を備えることが必要。
(そうぞくにんがそうぞくのたんじゅんしょうにん、げんていしょうにん、ほうきをしなければならないのは)
相続人が相続の単純承認、限定承認、放棄をしなければならないのは
(じこのためにそうぞくのかいしがあったことをしったときから3かげついない。)
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。
(そうぞくにんがそうぞくのたんじゅんしょうにん、げんていしょうにん、ほうきをしなければならないきかんを)
相続人が相続の単純承認、限定承認、放棄をしなければならない期間を
(けいかしたばあい、たんじゅんしょうにんをしたものとみなされる。)
経過した場合、単純承認をしたものとみなされる。
(はいぐうしゃじゅうきょけんのようけんは、はいぐうしゃが、ひそうぞくにんがなくなったときに、)
配偶者住居権の要件は、配偶者が、被相続人がなくなった時に、
(そのもののしょゆうするたてものにじゅうきょしていたこと。)
そのものの所有する建物に住居していたこと。
(いさんぶんかつなどによりはいぐうしゃじゅうきょけんをしゅとくすることである。)
遺産分割などにより配偶者住居権を取得することである。
(はいぐうしゃじゅうきょけんのそんぞくきかんはげんそくとしてはいぐうしゃのしゅうしんのあいだである。)
配偶者住居権の存続期間は原則として配偶者の終身の間である。
(はいぐうしゃじゅうきょけんをだいさんしゃにたいこうするには、たいこうようけんがひつようである。)
配偶者住居権を第三者に対抗するには、対抗要件が必要である。
(じひつしょうしょゆいごんがゆうこうにせいりつするためのようけんは)
自筆証書遺言が有効に成立するための要件は
(いごんしゃほんにんがゆいごんしょをかき、かついんかんをおしたことがひつようである。)
遺言者本人が遺言書を書き、かつ印鑑を押したことが必要である。
(いりゅうぶんはそうぞくにんできょうだいしまいいがいのものにしょうじる。)
遺留分は相続人で兄弟姉妹以外のものに生じる。
(そうぞくかいしまえにそうぞくにんがいりゅうぶんをほうきするためにはかていさいばんしょのきょかがひつよう。)
相続開始前に相続人が遺留分を放棄するためには家庭裁判所の許可が必要。
(そうぞくかいしごにそうぞくにんがいりゅうぶんをほうきするのはほうきのひょうじのみでかのう。)
相続開始後に相続人が遺留分を放棄するのは放棄の表示のみで可能。



