【第119回 検定試験】2級
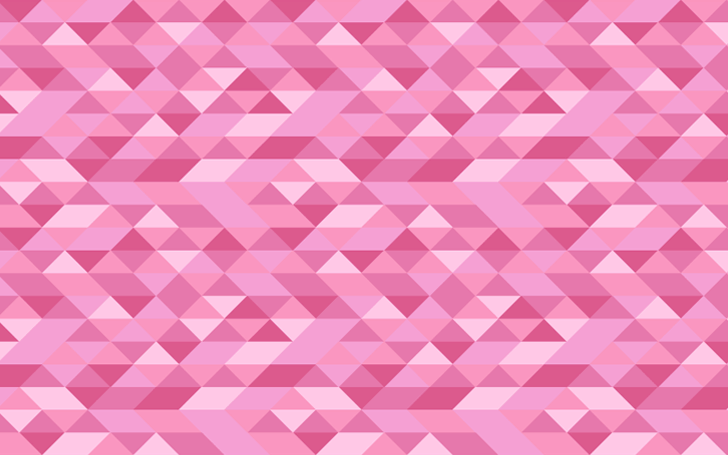
日本語ワープロ検定試験
第119回(令和元年7月)速度問題
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 6336 | S | 6.9 | 91.5% | 246.2 | 1719 | 159 | 35 | 2026/01/20 |
| 2 | sss | 5954 | A+ | 6.2 | 95.3% | 274.6 | 1719 | 84 | 35 | 2026/01/27 |
| 3 | nao@koya | 5598 | A | 5.7 | 97.7% | 301.0 | 1724 | 39 | 35 | 2026/01/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数3850 長文1668打
-
プレイ回数4343 長文2623打
-
プレイ回数8177 長文かな1045打
-
プレイ回数6230 長文1591打
-
プレイ回数2250 長文1186打
-
プレイ回数6122 長文1314打
-
プレイ回数4.4万 長文1048打
-
プレイ回数3663 長文かな1301打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(しょくひんとれーやおかしのふくろなど、)
食品トレーやお菓子の袋など、
(わたしたちのまわりはぷらすちっくのようきやほうそうであふれています。)
わたしたちの周りはプラスチックの容器や包装であふれています。
(このげんじょうをなんとかしようと、)
この現状を何とかしようと、
(おうしゅうれんごうでは2030ねんまでにこれらのつかいすてようきをやめ、)
欧州連合では2030年までにこれらの使い捨て容器をやめ、
(すべてさいしようまたはさいせいりようかのうなものにすることをはっぴょうしました。)
すべて再使用または再生利用可能なものにすることを発表しました。
(これをきいておもいだしたのが、)
これを聞いて思い出したのが、
(50ねんほどまえまであったにほんのくらしです。)
50年ほど前まであった日本の暮らしです。
(そのころ、たべものをつつむにはくさきがつかわれてました。)
そのころ、食べ物を包むには草木が使われてました。
(たとえば、にくやでかいものをすると)
例えば、肉屋で買い物をすると
(しょうひんはたけかわとそのはしをほそくきったものでほうそうされていました。)
商品は竹皮とその端を細く切ったもので包装されていました。
(ちゅうかりょうりのちまきをおもいうかべてみましょう。)
中華料理のちまきを思い浮かべてみましょう。
(これは、たけのこのそとがわをうろこじょうにくるんでいるかわで、)
これは、タケノコの外側をうろこ状にくるんでいる皮で、
(せいちょうするとしぜんにおちます。)
成長すると自然に落ちます。
(さっきんりょくがあってかんそうしにくいので、)
殺菌力があって乾燥しにくいので、
(にくやおにぎりをつつむにはさいてきだったのです。)
肉やおにぎりを包むには最適だったのです。
(もうひとつよくつかわれたのがうすいきのいたです。)
もう一つよく使われたのが薄い木の板です。
(これはすぎやひのきなどのもくざいをかみのようにけずったものです。)
これはスギやヒノキなどの木材を紙のように削ったものです。
(むかしはこれにおきょうをかいていたので、)
昔はこれにお経を書いていたので、
(めいしょうにはそのじがもちいられています。)
名称にはその字が用いられています。
(わたしがちいさいころには、さかなやでさしみをかうとこれにくるみ、)
私が小さいころには、魚屋で刺身を買うとこれにくるみ、
など
(それをさらにしんぶんでまいてわたしてくれました。)
それをさらに新聞で巻いて渡してくれました。
(げんざいではなかなかみかけるきかいがなく、さみしくおもっていましたが、)
現在ではなかなか見掛ける機会がなく、さみしく思っていましたが、
(ふだんよくくちにするものにつかわれていることにきがつきました。)
普段よく口にするものに使われていることに気が付きました。
(それは、たこやきです。)
それは、たこ焼きです。
(ふねのかたちをしたようきにもられたすがたをみたことがあるひとはすくなくないはずです。)
船の形をした容器に盛られた姿を見たことがある人は少なくないはずです。
(ほかにも、すこしあつめのいたをつかってはこにしたおりばことよばれるようきがあります。)
他にも、少し厚めの板を使って箱にした折り箱と呼ばれる容器があります。
(このいれもののれきしはふるく、ぶっきょうでんらいとともににほんにもたらされ、)
この入れ物の歴史は古く、仏教伝来と共に日本にもたらされ、
(ちょうていへのけんじょうひんをほうそうしたことがそのきげんだといわれています。)
朝廷への献上品を包装したことがその起源だといわれています。
(そのごは、めいじこうはんからたいしょうにかけてえきべんのようきとしてもちいられ、)
その後は、明治後半から大正にかけて駅弁の容器として用いられ、
(いっぱんのひとびとにもふきゅうしました。)
一般の人々にも普及しました。
(だいにじせかいたいせんちゅうには、)
第二次世界大戦中には、
(せんちにじさんするべんとうばことしてもつかわれたそうです。)
戦地に持参する弁当箱としても使われたそうです。
(そして、これらはいちどしようしてすてるのではなく、)
そして、これらは一度使用して捨てるのではなく、
(なんどもさいりようされていました。)
何度も再利用されていました。
(むかしのくらしには、しげんをたいせつにするこころがねづいていたのです。)
昔の暮らしには、資源を大切にする心が根付いていたのです。







