【第123回】検定試験 4級
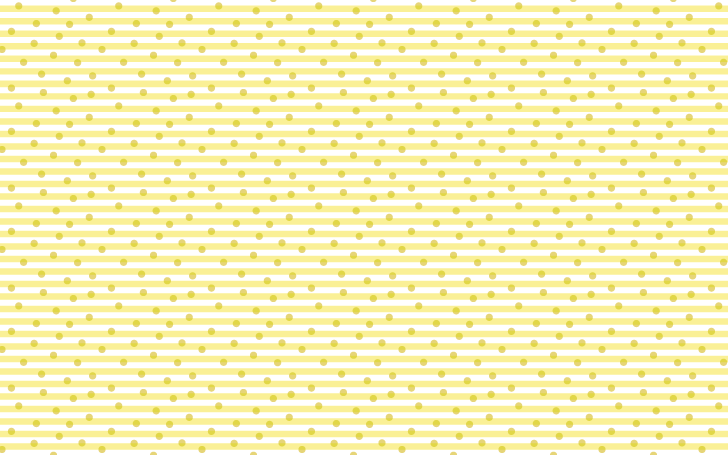
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLMKJNB4 | 5952 | A+ | 6.6 | 90.9% | 155.4 | 1027 | 102 | 25 | 2025/12/25 |
関連タイピング
-
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9553長文かな490打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数9526長文かな694打 -
第58回(令和元年10月)スピード検定試験
プレイ回数1.6万長文2659打 -
第36回 ワープロ実務検定試験
プレイ回数8495長文1009打 -
第57回(令和元年7月)スピード検定試験
プレイ回数1.2万長文2453打 -
コブクロ
プレイ回数280歌詞1173打 -
浜崎あゆみ
プレイ回数1175歌詞779打 -
第54回(平成30年10月)スピード検定試験
プレイ回数8174長文3693打
問題文
(わたしたちにほんじんにとってはあたりまえともいえるさーびすのひとつに、)
私たち日本人にとっては当たり前ともいえるサービスの一つに、
(おしぼりがあげられます。)
おしぼりが挙げられます。
(これは、いつごろからはじまったのでしょうか。)
これは、いつ頃から始まったのでしょうか。
(しょせつありますが、)
諸説ありますが、
(へいあんじだいにとうじのくげがいえにまねいたきゃくをもてなすときに、)
平安時代に当時の公家が家に招いた客をもてなす時に、
(ぬれたぬのをていきょうしたことがはじまりだといわれています。)
濡れた布を提供したことが始まりだといわれています。
(ほかには、えどじだいにちゃやでのさーびすがきげんとなったというせつもあります。)
他には、江戸時代に茶屋でのサービスが起源となったという説もあります。
(これは、たいへんなおもいをして、)
これは、大変な思いをして、
(やまみちをのぼってきたたびびとたちへのきづかいからうまれたものだったようです。)
山道を登ってきた旅人たちへの気遣いから生まれたものだったようです。
(いずれにしても、おもてなしのこころからたんじょうしたことに)
いずれにしても、おもてなしの心から誕生したことに
(かわりはないでしょう。)
変わりはないでしょう。
(また、むろまちじだいになると、)
また、室町時代になると、
(げんかんさきでみずをいれたおけとてぬぐいをていきょうするやどやがとうじょうします。)
玄関先で水を入れた桶と手ぬぐいを提供する宿屋が登場します。
(おとずれたひとは、)
訪れた人は、
(よごれたてあしをきれいにしてたびのつかれをいやしていたそうです。)
汚れた手足をきれいにして旅の疲れを癒やしていたそうです。
(このときのぬれたてぬぐいをしぼるこういが、)
このときの濡れた手ぬぐいを絞る行為が、
(おしぼりというなまえのゆらいになったといわれています。)
おしぼりという名前の由来になったといわれています。
(ときはすぎ、)
時は過ぎ、
(めんのたおるをふたつおりにしてまいたものがれんたるされ、)
綿のタオルを二つ折りにして巻いたものがレンタルされ、
(いんしょくてんなどでていきょうされるようになったのは、)
飲食店などで提供されるようになったのは、
(しょうわ30ねんだいのことです。)
昭和30年代のことです。
(そのあと、がいしょくさんぎょうのしじょうかくだいにともなって、)
その後、外食産業の市場拡大に伴って、
(てがるなかみのおしぼりがとうじょうしますが、)
手軽な紙のおしぼりが登場しますが、
(きんねんはえこのかんてんから、)
近年はエコの観点から、
(れんたるがみなおされているようです。)
レンタルが見直されているようです。








