道徳経(老子)第四十一章
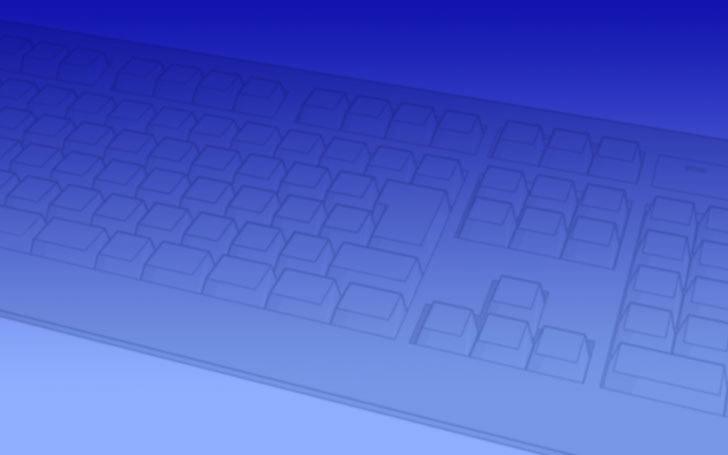
関連タイピング
-
禅語(毎回ランダム出題)
プレイ回数209かな807打 -
プレイ回数4長文かな481打
-
プレイ回数2長文かな593打
-
プレイ回数2長文かな348打
-
プレイ回数4長文かな927打
-
プレイ回数3長文かな236打
-
プレイ回数3長文かな462打
-
プレイ回数3長文かな338打
問題文
(だいよんじゅういっしょう)
第四十一章
(すぐれたさいのうをもってるひとがみちにみみをかたむけたとき、)
優れた才能をもってる人が「道」に耳をかたむけたとき、
(ねっしんにそれをおこなう。)
熱心にそれを行う。
(ふつうのひとがみちにみみをかたむけたとき、)
普通の人が「道」に耳をかたむけたとき、
(それをしんじるようにみえるがしんじていない。)
それを信じるように見えるが信じていない。
(もっともおとったひとがみちにみみをかたむけたとき、おおごえでわらう。)
最も劣った人が「道」に耳をかたむけたとき、大声で笑う。
(わらわなかったら、それはみちでないかもしれない。)
笑わなかったら、それは「道」でないかもしれない。
(だから、けんげんにある。)
だから、「建言」にある。
(りかいしないようにみちをりかいせよ。)
理解しないように「道」を理解せよ。
(そこからでてくるようにみちのなかにいれ。)
そこから出てくるように「道」の中に入れ。
(こんなんがあるかのようになめらかにみちとともにうごけ。)
困難があるかのようになめらかに「道」とともに動け。
(さいこうのとくは、とくでないかのようである。)
最高の徳は、徳でないかのようである。
(すべてをつつむとくは、とくをかいているかのようである。)
すべてを包む徳は、徳を欠いているかのようである。
(きびしいとくはなまけたぶらつきのようである。)
厳しい徳は怠けたぶらつきのようである。
(しんのほんしつはくうであるかのようである。)
真の本質は空であるかのようである。
(おおいなるしろはくろであるかのようである。)
大いなる白は黒であるかのようである。
(おおいなるほうけいにはすみがない。)
大いなる方形には隅がない。
(おおいなるようきはできあがるのがおそい。)
大いなる容器はできあがるのがおそい。
(おおいなるおんがくはおとがない。)
大いなる音楽は音がない。
(おおいなるぞうはかたちがない。)
大いなる象は形がない。
(みちはかくれたもので、なまえがない。)
「道」は隠れたもので、名前がない。
(しかし、みちはあらゆるものにえんじょをあたえ、)
しかし、「道」はあらゆるものに援助を与え、
(なしとげるようさせるものである。)
成しとげるようさせるものである。




