半七捕物帳 奥女中7
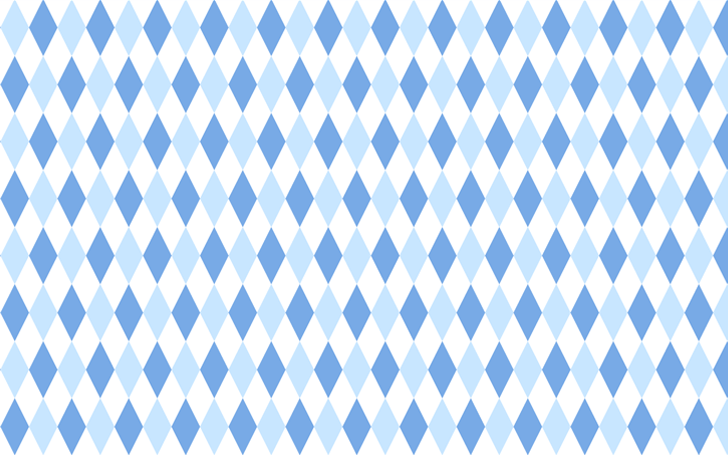
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第七話
関連タイピング
-
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数104 長文3422打 -
YOASOBIのハルカです!!いい曲だよね〜!!
プレイ回数149 歌詞かな30秒 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数350 長文3869打 -
小説作ってみたのでやってみてね! 練習!長文タイピング!
プレイ回数1.7万 長文1069打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数227 長文1737打 -
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
短編名作を数多くのこした、芥川龍之介の「羅生門」の前編です。
プレイ回数1万 長文かな6052打 -
好評だった小説の続きです
プレイ回数7729 長文797打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(「そりゃあしんぱいだろうね。いまのはなしのようすじゃああいてはいずれおおきい)
三
「そりゃあ心配だろうね。今の話の様子じゃあ相手はいずれ大きい
(おはたもとかおだいみょうだろうが、なぜそんなことをするんだろう。)
御旗本か御大名だろうが、なぜそんなことをするんだろう。
(ちゃみせのむすめだってきりょうのぞみでだいみょうのおへやさまにも)
茶店の娘だって容貌(きりょう)のぞみで大名の御部屋様にも
(なれねえでもかぎらねえが、それならまたそのようにうちあけて)
なれねえでも限らねえが、それなら又そのように打ち明けて
(めしかかえのそうだんもありそうなもんだが、すこしりくつが)
召し抱えの相談もありそうなもんだが、少し理窟が
(のみこめねえな」と、はんしちはしばらくかんがえていた。)
吞み込めねえな」と、半七はしばらく考えていた。
(「それになにしろかんじんのたまがむこうにひきあげられているんじゃあ、)
「それになにしろ肝腎の玉が向うに引き揚げられているんじゃあ、
(どうにもならねえ。おまけにそのやしきもどこだかわからねえじゃ)
どうにもならねえ。おまけにその屋敷もどこだか判らねえじゃ
(てのつけようがねえ。こまったもんだ」)
手の着けようがねえ。困ったもんだ」
(はんしちにうでをくまれて、おかめはいよいよたよりのないようなかおをしていた。)
半七に腕を組まれて、お亀はいよいよ頼りのないような顔をしていた。
(「むすめがこれぎりかえってきませんようだったら、どうしましょう」と、)
「娘がこれぎり帰って来ませんようだったら、どうしましょう」と、
(かのじょはに、さんどもみずをくぐったらしいちょうしちぢみのそででめをふいていた。)
彼女は二、三度も水をくぐったらしい銚子縮の袖で眼を拭いていた。
(「だが、そのごしゅでんふうのおんなとかいうのが、いずれいちにちふつかのうちに)
「だが、その御守殿風の女とかいうのが、いずれ一日二日のうちに
(またでなおしてくるだろうから、ともかくもおれがいって、)
また出直して来るだろうから、ともかくも俺が行って、
(それとなくようすをみてあげよう。そのうえでまたなんとか)
それとなく様子を見てあげよう。その上で又なんとか
(いいちえもでようじゃねえか」と、はんしちはなぐさめるようにいった。)
好い知恵も出ようじゃねえか」と、半七は慰めるように云った。
(「おやぶんがいらしってくだされば、わたくしもどんなにきじょうぶだか)
「親分がいらしって下されば、わたくしもどんなに気丈夫だか
(わかりません。では、まことにかってがましゅうございますが、)
判りません。では、まことに勝手がましゅうございますが、
(あしたにもちょいとおいでをねがいとうございます」)
あしたにもちょいとお出でを願いとうございます」
(おかめはしきりにねんをおしてたのんでかえった。あくるひはじゅうごやで、)
お亀はしきりに念を押して頼んで帰った。あくる日は十五夜で、
など
(はれたそらにはあきかぜがたかくふいていた。あさはやくからすすきをうるこえが)
晴れた空には秋風が高く吹いていた。朝早くから薄(すすき)を売る声が
(きこえた。はんしちはひるまえにほかのようをかたづけて、)
きこえた。半七は午前(ひるまえ)にほかの用を片付けて、
(やっつ(ごごにじ)ごろからおかめのうちをたずねた。おかめのうちは)
八ツ(午後二時)頃からお亀の家をたずねた。お亀の家は
(はまちょうがしにちかいろじのおくで、いりぐちのやおやにもすすきやえだまめが)
浜町河岸に近い路地の奥で、入口の八百屋にも薄や枝豆が
(たくさんつんであった。きんじょのおおきいやしきのなかではあきのせみがないていた。)
たくさん積んであった。近所の大きい屋敷のなかでは秋の蝉が鳴いていた。
(「おや、おやぶんさん。どうもおそれいりました」と、おかめは)
「おや、親分さん。どうも恐れ入りました」と、お亀は
(まちかねたようにはんしちをむかえた。「さっそくでございますが、)
待ち兼ねたように半七を迎えた。「早速でございますが、
(むすめがゆうべもどってまいりましてね」)
娘がゆうべ戻ってまいりましてね」
(ゆうべおかめがはんしちをたずねているるすに、おちょうはいつものとおりの)
ゆうべお亀が半七をたずねている留守に、お蝶はいつもの通りの
(のりものにのせられてかしのいしおきばまでおくりかえされていた。)
乗物にのせられて河岸の石置き場まで送りかえされていた。
(くわしいことはおっかさんにはなしてあるから、おまえもうちへ)
詳しいことは阿母(おっか)さんに話してあるから、おまえも家へ
(いちどかえってよくそうだんしてこいと、おちょうはかのおんなからいいきかされて)
一度帰ってよく相談して来いと、お蝶はかの女から云い聞かされて
(きたのであった。)
来たのであった。
(こういうばあいにほんにんをすなおにかえしてよこすというのは、)
こういう場合に本人を素直に帰してよこすというのは、
(いかにももののわかったしかたで、せんぽうにあくいのないことは)
いかにも物の判った仕方で、先方に悪意のないことは
(よくわかっていた。きづかれでおくのさんじょうにうとうとねむっているおちょうを)
能く判っていた。気疲れで奥の三畳にうとうと眠っているお蝶を
(よびおこさせて、はんしちはかのじょからさらにくわしいはなしをききとったが、)
呼び起させて、半七は彼女から更に詳しい話を聴きとったが、
(やはりたしかなけんとうはつかなかった。おちょうのはなしによってかんがえると、)
やはり確かな見当は付かなかった。お蝶の話によって考えると、
(そのやしきはどうもしかるべきだいみょうのしもやしきであるらしく)
その屋敷はどうも然るべき大名の下屋敷であるらしく
(おもわれたが、そのばしょもほうがくもしれないので、それがどこの)
思われたが、その場所も方角も知れないので、それがどこの
(やしきだかけんとうがつかなかった。)
屋敷だか見当が付かなかった。
(「いまにだれかくるかもしれないから、まあ、まっていようよ」と、)
「今に誰か来るかも知れないから、まあ、待っていようよ」と、
(はんしちもこしをおちつけて、そこにいすわっていることにした。)
半七も腰をおちつけて、そこに居坐っていることにした。





