半七捕物帳 広重と河獺4
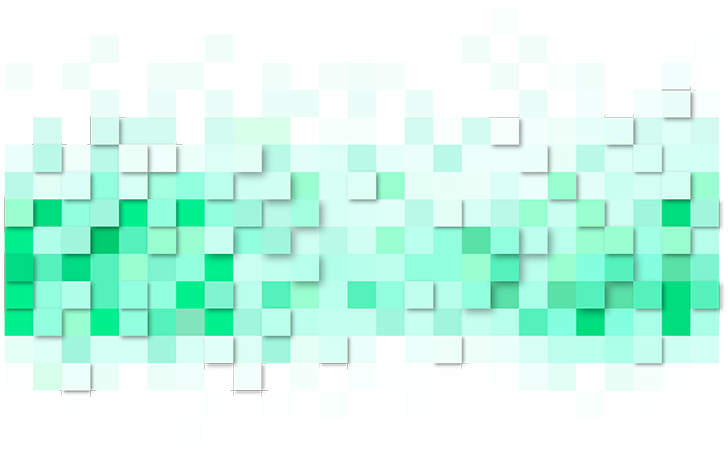
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第十話
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(むろんにこころあたりはないとぐんえもんはちゅうちょせずにこたえた。)
無論に心当りはないと軍右衛門は躊躇せずに答えた。
(ゆうべはやしきにかるたかいのもよおしがあって、しんるいのひとたちや)
ゆうべは屋敷に歌留多(かるた)会の催しがあって、親類の人たちや
(となりやしきのしそくやむすめや、おおどもこどもをあわせてにじゅうにんほどが)
隣り屋敷の子息や娘や、大供子供をあわせて二十人ほどが
(よりあつまって、よっつ(ごごじゅうじ)をすぎるころまでにぎやかにさわぎあかした。)
寄りあつまって、四ツ(午後十時)を過ぎる頃まで賑やかに騒ぎあかした。
(そのつかれでやしきじゅうのものもみんなよくねこんでしまったので)
その疲れで屋敷じゅうの者もみんな好く寝込んでしまったので
(たかいおおやねのうえにはいのぼったものがあったか、ころげおちたものがあったか、)
高い大屋根の上に這いのぼった者があったか、転げ落ちた者があったか、
(だれもいっこうきづかなかった。げんにけさもよそからちゅういされて)
誰も一向気づかなかった。現にけさもよそから注意されて
(はじめてそれをはっけんしたくらいであるから、それがよいのことか、)
初めてそれを発見したくらいであるから、それが宵のことか、
(よなかのことか、あけがたのことか、まるでなんにもけんとうは)
夜半(よなか)のことか、暁け方のことか、まるでなんにも見当は
(つかないといった。)
付かないと云った。
(「このこどものにんそうはまったくどなたもごぞんじないんですね」と、)
「この子供の人相はまったく何人(どなた)も御存じないんですね」と、
(はんしちはねんをおした。)
半七は念を押した。
(「わたしはむろんみおぼえがない。やしきじゅうのものものこらずせんぎしたが、)
「わたしは無論見おぼえがない。屋敷中のものも残らず詮議したが、
(だれもみしっているものはないといっている。このむすめのふうていからみると、)
誰も見識っている者はないと云っている。此の娘の風体から見ると、
(どうもちょうにんらしいが・・・・・・」)
どうも町人らしいが……」
(「さようでございます」と、はんしちはうなずいた。「どうしても)
「左様でございます」と、半七はうなずいた。「どうしても
(おやしきかたじゃございません。それからおそれいりますが、)
御屋敷方じゃございません。それから恐れ入りますが、
(このしがいのおちていたおおやねのあたりをいちどみせていただくわけには)
この死骸の落ちていた大屋根のあたりを一度みせていただくわけには
(まいりますまいか」)
まいりますまいか」
(「しょうちいたしました」)
「承知いたしました」
など
(ぐんえもんはさきにたってながやをでて、げんかんさきへはんしちをあんないした。)
軍右衛門は先に立って長屋を出て、玄関先へ半七を案内した。
(かれはふたりのちゅうげんをよんで、げんかんのよこてからふたたびながばしごをかけさせると、)
かれは二人の中間をよんで、玄関の横手から再び長梯子をかけさせると、
(はんしちにみづくろいをしてすぐにするするとのぼっていって、)
半七に身づくろいをしてすぐにするすると登って行って、
(おおやねのうえにつったった。そうして、だれかいっしょにきてくれと、)
大屋根の上に突っ立った。そうして、誰か一緒に来てくれと、
(うえからこてまねぎをすると、こづくりのちゅうげんひとりがあとから)
上から小手招(こてまね)ぎをすると、小作りの中間一人があとから
(つづいてのぼってきたので、そのちゅうげんにおしえられて、)
つづいて登って来たので、その中間に教えられて、
(かれはしがいのよこたわっていたばしょはもちろん、たかいおおやねのうえを)
かれは死骸の横たわっていた場所は勿論、高い大屋根のうえを
(ひとめぐりみまわっておりた。)
ひと巡り見まわって降りた。



