半七捕物帳 石燈籠5
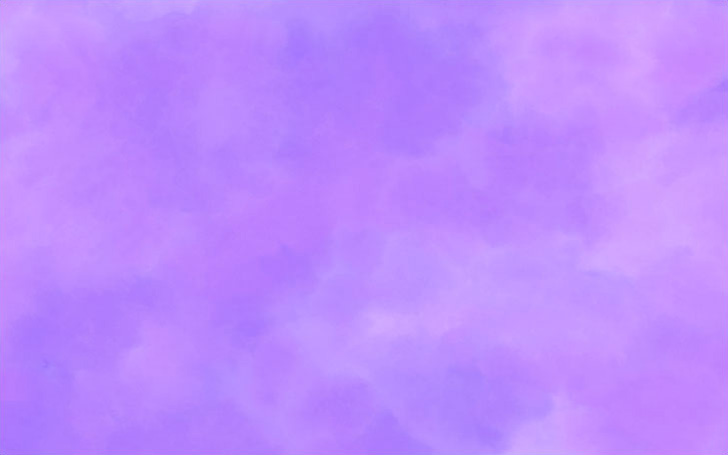
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第二話
関連タイピング
-
短編名作を数多くのこした、芥川龍之介の「羅生門」の前編です。
プレイ回数1万 長文かな6052打 -
夏目漱石「こころ」3-84
プレイ回数640 長文1523打 -
YOASOBIのハルカです!!いい曲だよね〜!!
プレイ回数149 歌詞かな30秒 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数104 長文3422打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数265 長文2582打 -
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数252 長文4339打 -
プレイ回数602 長文589打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(かれがなきながらうったえるのをきくと、ゆうべもぜんやとおなじひともしごろに、)
かれが泣きながら訴えるのを聞くと、ゆうべも前夜とおなじ燈ともし頃に、
(おきくはわがやへおなじかたちをあらわした。こんどはどこからはいってきたか)
お菊はわが家へおなじ形を現わした。今度はどこからはいって来たか
(わからなかったが、おくでおかみさんがとつぜんに「おや、おきく・・・・・・」とさけんだ。)
判らなかったが、奥でおかみさんが突然に「おや、お菊……」と叫んだ。
(つづいておかみさんがひめいをあげた。おたけとほかのじょちゅうふたりがおどろいて)
つづいておかみさんが悲鳴をあげた。お竹とほかの女中二人がおどろいて
(かけつけたときに、えんがわへするりとぬけだしてゆくおきくのうしろすがたがみえた。)
駈けつけた時に、縁側へするりと抜け出してゆくお菊のうしろ姿が見えた。
(おきくはやはりきはちじょうをきて、ふじいろのずきんをかぶっていた。)
お菊はやはり黄八丈を着て、藤色の頭巾をかぶっていた。
(さんにんはおきくをとりおさえるよりも、まずおかみさんのほうにめをむけなければ)
三人はお菊を取押さえるよりも、まずおかみさんの方に眼をむけなければ
(ならなかった。おとらはひだりのちちのしたをさされてむしのいきでたおれていた。)
ならなかった。お寅は左の乳の下を刺されて虫の息で倒れていた。
(たたみのうえにはいちめんにあかいいずみがながれていた。さんにんはきゃっとさけんで)
畳の上には一面に紅い泉が流れていた。三人はきゃっと叫んで
(たちすくんでしまった。みせのひとたちもこのこえにおどろいてみんなかけつけてきた。)
立ちすくんでしまった。店の人達もこの声におどろいてみんな駈け付けて来た。
(「おきくが・・・・・・おきくが・・・・・・」)
「お菊が……お菊が……」
(おとらはかすかにこういったらしいが、そのいじょうのことはだれのみみにも)
お寅は微かにこう云ったらしいが、その以上のことは誰の耳にも
(ききとれなかった。かのじょはおおぜいがただうろたえているうちにいきをひきとって)
聴き取れなかった。彼女は大勢が唯うろたえているうちに息を引き取って
(しまった。ちょうやくにんれんめいでうったえてでると、すぐにけんしのやくにんがきた。)
しまった。町役人連名で訴えて出ると、すぐに検視の役人が来た。
(おとらのきずぐちはするどいあいくちのようなものでふかくえぐられていることが)
お寅の傷口は鋭い匕首(あいくち)のようなもので深くえぐられていることが
(はっけんされた。)
発見された。
(かないのものはみなしらべられた。うっかりしたことをこうがいしてみせののれんに)
家内の者はみな調べられた。うっかりしたことを口外して店の暖簾に
(きずをつけてはならないというえんりょから、だれもげしゅにんをしらないとこたえた。)
疵を付けてはならないという遠慮から、誰も下手人を知らないと答えた。
(しかしむすめのおきくがいあわせないということがやくにんたちのちゅういをひいたらしい。)
しかし娘のお菊が居合わせないということが役人たちの注意をひいたらしい。
(おきくとわけのあることをはっけんされたせいじろうは、そのばからすぐに)
お菊と情交のあることを発見された清次郎は、その場からすぐに
など
(ひったてられていった。おたけにはまだなんのさたもないが、いずれちょうないあずけに)
引っ立てられて行った。お竹にはまだ何の沙汰もないが、いずれ町内預けに
(なるだろうと、かのじょはいきているそらもないようにおそれおののいていた。)
なるだろうと、彼女は生きている空もないように恐れおののいていた。
(「とんだことになったもんだ」と、はんしちはおもわずためいきをついた。)
「飛んだことになったもんだ」と、半七は思わず溜息をついた。
(「わたしはどうなるでしょう」と、おたけはまきぞえのつみがどれほどにおもいかを)
「わたしはどうなるでしょう」と、お竹はまきぞえの罪がどれほどに重いかを
(ひたすらにおそれているらしかった。そうして「わたし、もういっそ)
ひたすらに恐れているらしかった。そうして「わたし、もういっそ
(しんでしまいたい」などときょうじょのようになきかなしんでいた。)
死んでしまいたい」などと狂女のように泣き悲しんでいた。
(「ばかいっちゃあいけねえ。おめえはだいじのしょうにんじゃねえか」と、)
「馬鹿云っちゃあいけねえ。おめえは大事の証人じゃねえか」と、
(はんしちはしかるようにいった。)
半七は叱るように云った。
(「いずれごようききがいっしょにきたろうが、だれがきた」)
「いずれ御用聞きが一緒に来たろうが、誰が来た」
(「なんでもげんたろうさんとかいうひとだそうです」)
「何でも源太郎さんとかいう人だそうです」
(「むむ、そうか。せとものちょうか」)
「むむ、そうか。瀬戸物町か」
(げんたろうはせとものちょうにすんでいるふるがおのおかっぴきで、よいこぶんもおおぜいもっている。)
源太郎は瀬戸物町に住んでいる古顔の岡っ引で、好い子分も大勢もっている。
(いちばんこいつのはなをあかしておれのおやぶんにてがらをさしてやりたいと、はんしちのむねには)
一番こいつの鼻をあかして俺の親分に手柄をさしてやりたいと、半七の胸には
(つよいきょうそうのねんがひのようにもえあがった。しかしどこからてをつけていいのか、)
強い競争の念が火のように燃え上がった。併しどこから手を着けていいのか、
(かれもすぐにはけんとうがつかなかった。)
彼もすぐには見当が付かなかった。
(「ゆうべもずきんをかぶっていたんだね」)
「ゆうべも頭巾をかぶっていたんだね」
(「ええ。やっぱりいつものふじいろでした」)
「ええ。やっぱりいつもの藤色でした」
(「さっきのはなしじゃあ、むすめはどさくさまぎれにえんがわへぬけだして、)
「さっきの話じゃあ、娘はどさくさまぎれに縁側へ抜け出して、
(それからゆくえがしれねえんだね。おい、きどをあけておいらをにわぐちへ)
それから行くえが知れねえんだね。おい、木戸をあけておいらを庭口へ
(まわらしてくれねえか」と、はんしちはいった。)
廻らしてくれねえか」と、半七は云った。
(おたけがおくへとりついだとみえて、おおばんとうのじゅうぞうがめをくぼませてでてきた。)
お竹が奥へ取次いだとみえて、大番頭の重蔵が眼をくぼませて出て来た。
(「どうもごくろうさまでございます。どうぞすぐにこちらへ・・・・・・」)
「どうも御苦労様でございます。どうぞ直ぐにこちらへ……」
(「とんだこってしたね。おとりこみのなかへずかずかはいるのもよくねえから、)
「飛んだこってしたね。お取り込みの中へずかずかはいるのも良くねえから、
(すぐににわぐちへまわろうとおもったんですが、それじゃあごめんをこうむります」)
すぐに庭口へ廻ろうと思ったんですが、それじゃあ御免を蒙ります」
(はんしちはおくへあんないされて、おとらのちのあとがまだかわかないはちじょうのいまへとおった。)
半七は奥へ案内されて、お寅の血のあとがまだ乾かない八畳の居間へ通った。
(かれがかねてしっているとおり、えんがわはきたにむかっていて、まえにはじゅっつぼばかりの)
彼がかねて知っている通り、縁側は北に向っていて、前には十坪ばかりの
(こにわがあった。にわにはきれいにていれがゆきとどいていて、ゆきつりのまつや)
小庭があった。庭には綺麗に手入れが行きとどいていて、雪釣りの松や
(しもよけのばしょうがふゆらしいにわのいろをつくっていた。)
霜除けの芭蕉が冬らしい庭の色を作っていた。






