紫式部 源氏物語 松風 4 與謝野晶子訳
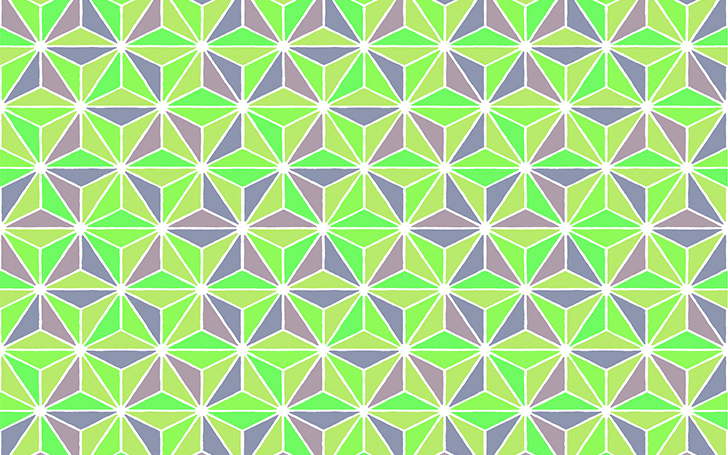
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | subaru | 8037 | 神 | 8.4 | 95.7% | 248.2 | 2088 | 93 | 36 | 2025/11/27 |
関連タイピング
-
プレイ回数1745 長文4369打
-
プレイ回数334 長文1952打
-
少年探偵団シリーズ第3作品『妖怪博士』
プレイ回数1077 長文4563打 -
プレイ回数282 長文2309打
-
原作 コッローディ
プレイ回数142 長文3086打 -
秋田県の民話です
プレイ回数690 長文180秒 -
青森県の民話です
プレイ回数1053 長文180秒 -
プレイ回数341 長文1931打
問題文
(さんそうはふうりゅうにできていて、おおいがわがあかしでながめたうみのように)
山荘は風流にできていて、大井川が明石でながめた海のように
(まえをながれていたから、すまいのかわったきもそれほどしなかった。)
前を流れていたから、住居の変わった気もそれほどしなかった。
(あかしのせいかつがなおちかいつづきのようにおもわれて、かなしくなることが)
明石の生活がなお近い続きのように思われて、悲しくなることが
(おおかった。ぞうちくしたろうなどもおもむきがあってえんないにひいたみずのながれも)
多かった。増築した廊なども趣があって園内に引いた水の流れも
(うつくしかった。けってんもあるがすみついたならきっとよくなるであろうと)
美しかった。欠点もあるが住みついたならきっとよくなるであろうと
(あかしのひとびとはおもった。げんじはしたしいけいしにめいじてとうちゃくのひのいっこうの)
明石の人々は思った。源氏は親しい家司に命じて到着の日の一行の
(きょうおうをさせたのであった。じしんでたずねていくことは、)
饗応をさせたのであった。自身で訪ねて行くことは、
(きかいをつくろうつくろうとしながらもおくれるばかりであった。)
機会を作ろう作ろうとしながらもおくれるばかりであった。
(げんじにちかいきょうへきながらものおもいばかりがされて、おんなはあかしのいえも)
源氏に近い京へ来ながら物思いばかりがされて、女は明石の家も
(こいしかったし、つれづれでもあって、げんじのかたみのきんのいとを)
恋しかったし、つれづれでもあって、源氏の形見の琴の絃を
(ならしてみた。ひじょうにかなしいきのするひであったから、ひとのこぬざしきで)
鳴らしてみた。非常に悲しい気のする日であったから、人の来ぬ座敷で
(あかしがそれをすこしひいていると、まつかぜのねがあらあらしく)
明石がそれを少し弾いていると、松風の音が荒々しく
(がっそうをしかけてきた。よこになっていたあまぎみがおきあがっていった。 )
合奏をしかけてきた。横になっていた尼君が起き上がって言った。
(みをかえてひとりかえれるやまざとにききしににたるまつかぜぞふく )
身を変へて一人帰れる山里に聞きしに似たる松風ぞ吹く
(むすめがいった。 )
女が言った。
(ふるさとにみしよのともをこいわびてさえづることをたれかわくらん )
ふるさとに見し世の友を恋ひわびてさへづることを誰か分くらん
(こんなふうにはかながってくらしていたすうじつののちに、いぜんにもまして)
こんなふうにはかながって暮らしていた数日ののちに、以前にもまして
(あいがたいくるしさをせつにかんじるげんじは、ひとめもはばからずに)
逢いがたい苦しさを切に感じる源氏は、人目もはばからずに
(おおいへでかけることにした。ふじんにはまだあかしのじょうきょうしたことは)
大井へ出かけることにした。夫人にはまだ明石の上京したことは
(いってなかったから、ほかからみみにはいってはきまずいことになると)
言ってなかったから、ほかから耳にはいっては気まずいことになると
(おもって、げんじはにょうぼうをつかいにしていわせた。)
思って、源氏は女房を使いにして言わせた。
(「かつらにわたくしがいってさしずをしてやらねばならないことがあるのですが、)
「桂に私が行って指図をしてやらねばならないことがあるのですが、
(それをそのままにしてながくなっています。それにきょうへきたら)
それをそのままにして長くなっています。それに京へ来たら
(たずねようというやくそくのしてあるひともそのちかくへのぼって)
訪ねようという約束のしてある人もその近くへ上って
(きているのですから、すまないきがしますから、そこへも)
来ているのですから、済まない気がしますから、そこへも
(いってやります。さがののみどうになにもそろっていないところにいらっしゃる)
行ってやります。嵯峨野の御堂に何もそろっていない所にいらっしゃる
(ほとけさまへもごあいさつによりますからに、さんにちはかえらないでしょう」)
仏様へも御挨拶に寄りますから二、三日は帰らないでしょう」
(ふじんはかつらのいんというべっそうのしんちくされつつあることをきいたが、)
夫人は桂の院という別荘の新築されつつあることを聞いたが、
(そこへあかしのひとをむかえたのであったかときづくとうれしいこととは)
そこへ明石の人を迎えたのであったかと気づくとうれしいこととは
(おもえなかった。 「おののえをあたらしくなさらなければ(せんにんのごを)
思えなかった。 「斧の柄を新しくなさらなければ(仙人の碁を
(けんぶつしているあいだに、ときがたってきがついてみるとそのきこりのもっていた)
見物している間に、時がたって気がついてみるとその樵夫の持っていた
(おののえはくちていたというはなし)ならないほどのじかんはさぞ)
斧の柄は朽ちていたという話)ならないほどの時間はさぞ
(まちどおいことでしょう」 ふゆかいそうなこんなふじんのへんじがげんじにつたえられた。)
待ち遠いことでしょう」 不愉快そうなこんな夫人の返事が源氏に伝えられた。
(「またいがいなことをおいいになる。わたくしはもうすっかりむかしのわたくしで)
「また意外なことをお言いになる。私はもうすっかり昔の私で
(なくなったとせけんでもいうではありませんか」)
なくなったと世間でも言うではありませんか」
(などといわせてふじんのきげんをなおさせようとするうちにひるになった。)
などと言わせて夫人の機嫌を直させようとするうちに昼になった。







