半七捕物帳 湯屋の二階7
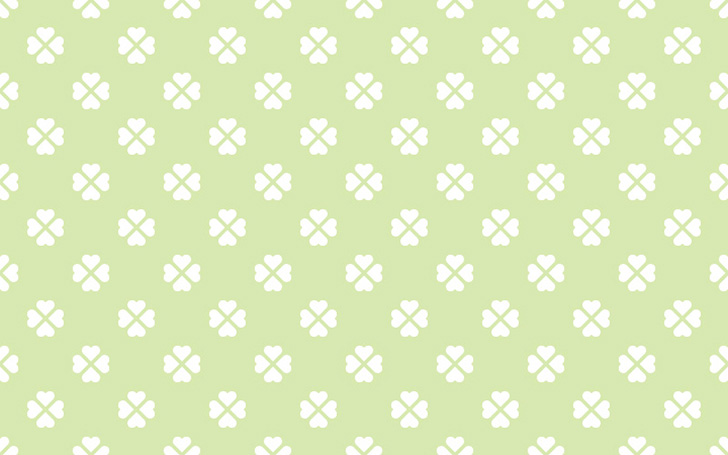
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第四話
タイトルの「湯屋」は「ゆうや」と読みます。
関連タイピング
-
プレイ回数5985 長文2707打
-
長文に挑戦したい時。
プレイ回数2万 長文2062打 -
短編名作を数多くのこした、芥川龍之介の「羅生門」の前編です。
プレイ回数1万 長文かな6052打 -
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数265 長文2582打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数104 長文3422打 -
YOASOBIのハルカです!!いい曲だよね〜!!
プレイ回数149 歌詞かな30秒 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数350 長文3869打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(こんなしょうばいをしていながら、わりあいにひとずれのしていないおきちは、)
三
こんな商売をしていながら、割合に人摺れのしていないお吉は、
(はんしちにおどされてもういきもでないくらいふるえあがっていた。)
半七に嚇されてもう息も出ないくらい顫え上がっていた。
(しかしかのぶしたちのみもとはどうしてもしらないといった。)
しかし彼の武士たちの身許はどうしても知らないと云った。
(なんでもあざぶあたりにおやしきがあるということだけはきいているが、)
なんでも麻布辺にお屋敷があるということだけは聞いているが、
(そのほかにはなんにもしらないとごうじょうをはっていた。それでもはんしちに)
そのほかにはなんにも知らないと強情を張っていた。それでも半七に
(おどしたりすかしたりされたあげくに、おきちはようように)
嚇したり賺(すか)したりされた挙句に、お吉はようように
(これだけのことをはいた。)
これだけのことを吐いた。
(「なんでもあのひとたちはかたきうちにでているんだそうでございます」)
「なんでもあの人達は仇討(かたきうち)に出ているんだそうでございます」
(「かたきうち・・・・・・」とはんしちはわらいだした。「じょうだんじゃあねえ。しばいじゃあ)
「かたき討……」と半七は笑い出した。「冗談じゃあねえ。芝居じゃあ
(あるめえし、いまどきふたりそろってえどのまんなかでかたきうちもねえもんだ。)
あるめえし、今どきふたり揃って江戸のまん中で仇討もねえもんだ。
(だが、まあいいや、かたきうちならかたきうちとしておいて、あのふたりのいどこは)
だが、まあいいや、かたき討なら仇討として置いて、あの二人の居どこは
(まったくしらねえんだね」)
まったく知らねえんだね」
(「まったくしりません」)
「まったく知りません」
(このうえにせめてもすなおにくちをひらきそうにもないので、はんしちもしばらく)
この上に責めても素直に口を開きそうにもないので、半七もしばらく
(かんがえていると、くまぞうがはしごのあがりぐちからくびをだして)
考えていると、熊蔵が階子(はしご)のあがり口から首を出して
(あわただしくよんだ。)
あわただしく呼んだ。
(「おやぶん。ちょいとかおをかしておくんなせえ」)
「親分。ちょいと顔を貸しておくんなせえ」
(「なんだ。そうぞうしい」)
「なんだ。そうぞうしい」
(わざとおちつきはらって、はんしちははしごをおりてゆくと、くまぞうはすりよって)
わざと落ち着き払って、半七は階子を降りてゆくと、熊蔵は摺り寄って
(ささやいた。「いせやじゃあかねのほかに、べんべらものをさんまいと)
ささやいた。「伊勢屋じゃあ金のほかに、べんべら物を三枚と
など
(さめのかわをごまいとられたそうです」)
鮫の皮を五枚奪られたそうです」
(「さめのかわ・・・・・・」と、はんしちはむねをおどらせた。「それはどろざめか、しあげのかわか」)
「鮫の皮……」と、半七は胸を躍らせた。「それは泥鮫か、仕上げの皮か」
(「さあ、そりゃあきいてきませんでしたが・・・・・・。もういっぺんきいてきましょうか」)
「さあ、そりゃあ訊いて来ませんでしたが……。もう一遍きいて来ましょうか」
(くまぞうはまたいそいででていった。やがてひっかえしてきて、それはみなみがきの)
熊蔵は又急いで出て行った。やがて引っ返して来て、それはみな磨きの
(しろいかわで、ろうげつちょうのつかまきしからしちにとったものだとほうこくした。)
白い皮で、露月(ろうげつ)町の柄巻師から質に取ったものだと報告した。
(どろざめではないときいて、はんしちはすこしあてがはずれた。)
泥鮫ではないと聞いて、半七はすこし的(あて)がはずれた。
(かれはゆうべいせやへおしこんだろうにんものと、きょうどろざめをうりにきたぶしとを、)
彼はゆうべ伊勢屋へ押し込んだ浪人者と、きょう泥鮫を売りに来た武士とを、
(むすびつけてかんがえることができなくなってしまった。)
結びつけて考えることが出来なくなってしまった。
(「どうもわからねえ」)
「どうも判らねえ」
(なにしろもうひるにちかくなったので、はんしちはくまぞうをつれて)
なにしろもう午(ひる)に近くなったので、半七は熊蔵を連れて
(きんじょへめしをくいにいった。)
近所へ飯を食いに行った。
(「あのおきちのやつは、よっぽどあのさむれえのひとりにござっている)
「あのお吉の奴は、よっぽどあの武士(さむれえ)の一人にござっている
(らしいな」と、はんしちはわらいながらいった。)
らしいな」と、半七は笑いながら云った。
(「そうです。そうです。それですからもうもうまくいかねえんですよ。)
「そうです。そうです。それですからもうも巧く行かねえんですよ。
(あいつおもうさまおどかしてやりましょうか」)
あいつ思うさま嚇かしてやりましょうか」
(「いや、おれもいいかげんおどかしておいたから、もうたくさんだ。)
「いや、おれも好い加減おどかして置いたから、もうたくさんだ。
(あんまりおどかすとかえってろくなことはしねえもんだ。まあ、もうすこし)
あんまり嚇かすと却って碌なことはしねえもんだ。まあ、もう少し
(うっちゃっておけ」)
打っちゃって置け」
(ふたりはくわえようじでかえってくると、ひとりのわかいぶしがゆやののれんを)
二人は銜(くわ)え楊枝で帰って来ると、一人の若い武士が湯屋の暖簾を
(くぐってでるのをとおめにみつけた。かれはさっきひかげちょうへどろざめをうりにいった)
くぐって出るのを遠目に見つけた。彼はさっき日陰町へ泥鮫を売りに行った
(ぶしにそういなかった。かれはもえぎのふろしきにつつんだいっこのはこのようなものを)
武士に相違なかった。彼は萌黄の風呂敷につつんだ一個の箱のようなものを
(だいじそうにかかえているらしかった。)
大事そうに抱えているらしかった。
(「あ、やろうがきましたよ。あのはこをひとつかかえだしたらしゅうがすぜ」と、)
「あ、野郎が来ましたよ。あの箱を一つ抱え出したらしゅうがすぜ」と、
(くまぞうはめをひからしてのびあがった。)
熊蔵は眼をひからして伸び上がった。
(「ちげえねえ。すぐつけてみろ」
「よがす」)
「ちげえねえ。すぐ尾けてみろ」
「よがす」
(くまぞうはすぐにかれのあとをつけていった。はんしちはひっかえしてゆやにはいって、)
熊蔵はすぐに彼のあとを尾けて行った。半七は引っ返して湯屋にはいって、
(ねんのためににかいにあがってみると、おきちのすがたがいつのまにかきえていた。)
念のために二階にあがって見ると、お吉の姿がいつの間にか消えていた。
(さらにとだなをあらためると、かのあやしいふたつのはこもみえなかった。)
更に戸棚をあらためると、かの怪しい二つの箱も見えなかった。
(「みんなもちだしてしまいやあがったな」)
「みんな持ち出してしまいやあがったな」
(「にかいをおりてきてばんだいのおとこにきくと、おきちはたったいまはしごをおりて)
「二階を降りて来て番台の男に訊くと、お吉はたった今階子を降りて
(おくへいったらしいというので、はんしちもつづいておくへいった。)
奥へ行ったらしいと云うので、半七もつづいて奥へ行った。
(かまのしたをたいているさんすけのはなしによると、おきちはちょいとそこまでいってくる)
釜の下を焚いている三助の話によると、お吉はちょいとそこまで行って来る
(といって、そそくさとおもてへでていったとのことであった。)
と云って、そそくさと表へ出て行ったとのことであった。
(「なにかかかえていやしなかったか」
「さあ、しりましねえ」)
「なにか抱えていやしなかったか」
「さあ、知りましねえ」
(やまだしのさんすけはぼんやりしていてなにもきがつかなかったのである。)
山出しの三助はぼんやりしていて何も気がつかなかったのである。
(はんしちはおもわずしたうちした。じぶんたちがめしをくいにいっているあいだに、)
半七は思わず舌打ちした。自分達が飯を食いに行っている間に、
(ちょうどかのぶしがきたので、おきちはかれとしめしあわせて、めいめいに)
丁度かの武士が来たので、お吉はかれと諜(しめ)し合わせて、めいめいに
(ひみつのはこをひとつずつかかえて、うらとおもてからわかれわかれにぬけだしたに)
秘密の箱を一つずつかかえて、裏と表から分かれ分かれに脱け出したに
(そういない。ひとあしちがいでとんでもないどじをふんだと、)
相違ない。一と足違いで飛んでもないどじを踏んだと、
(はんしちはじぶんのゆだんをくやんだ。)
半七は自分の油断をくやんだ。
(「こうとしったら、いっそおきちのやつをひきあげておけばよかった」)
「こうと知ったら、いっそお吉の奴を引き揚げて置けばよかった」
(かれはまたひっかえして、ばんだいのおとこにおきちのうちをきいた。みょうじんまえのうらに)
彼はまた引っ返して、番台の男にお吉の家を訊いた。明神前の裏に
(すんでいるというので、すぐにそこへおってゆくと、あにはしごとにでて)
住んでいると云うので、すぐにそこへ追ってゆくと、兄は仕事に出て
(るすであった。しょうじきそうなははがひとりでぼろをつづくっていて、)
留守であった。正直そうな母が一人で襤褸(ぼろ)をつづくっていて、
(おきちはけさいつものとおりにうちをでたぎりでまだかえらないといった。)
お吉は今朝いつもの通りに家を出たぎりでまだ帰らないと云った。
(ははのかおいろにはうそはみえなかった。せまいうちであるからどこにもかくれているようすも)
母の顔色には嘘は見えなかった。狭い家であるから何処にも隠れている様子も
(なかった。はんしちはまたしつぼうしてかえった。かえると、やがてくまぞうも)
なかった。半七はまた失望して帰った。帰ると、やがて熊蔵も
(つまらなそうなかおをしてかえってきた。)
詰まらなそうな顔をして帰って来た。






