半七捕物帳 お化け師匠9
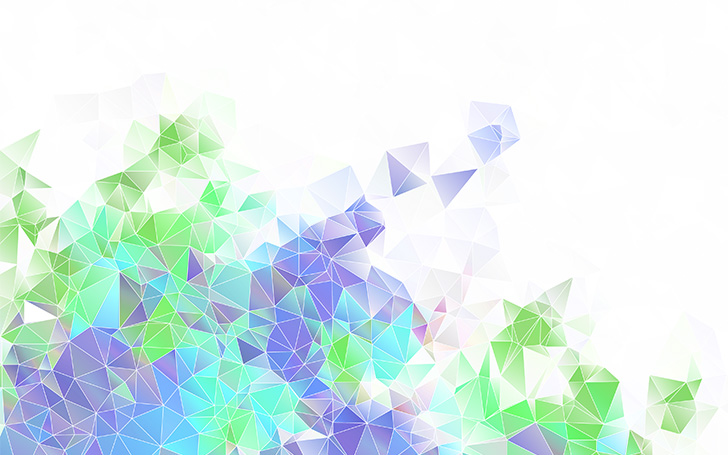
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第五話
関連タイピング
-
夏目漱石
プレイ回数17万 長文かな512打 -
シャーロックホームズシリーズ
プレイ回数2181 長文4844打 -
プレイ回数602 長文589打
-
プレイ回数743 336打
-
短編名作を数多くのこした、芥川龍之介の「羅生門」の前編です。
プレイ回数1万 長文かな6052打 -
作者 マーク・トウェイン
プレイ回数104 長文3422打 -
プレイ回数5466 長文2395打
-
YOASOBIのハルカです!!いい曲だよね〜!!
プレイ回数149 歌詞かな30秒
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(てらのもんをでると、はんしちはまつきちにあった。)
四
寺の門を出ると、半七は松吉に逢った。
(「おやぶんのうちへいまいったら、ここのてらへきているというから、)
「親分の家へ今行ったら、ここの寺へ来ていると云うから、
(すぐにひっかえしてきました。きのうもあれからまんねんちょうのほうを)
すぐに引っ返して来ました。きのうもあれから万年町の方を
(すっかりあさってみたが、どこにもそんなおふだうりらしいやつは)
すっかり猟(あさ)ってみたが、どこにもそんな御符(おふだ)売りらしい奴は
(とまっていねえんです。それからそれとさがしあるいて、ようようけさになって)
泊っていねえんです。それからそれと探し歩いて、ようよう今朝になって
(ほんじょのやすどまりにひとりいるのをみつけたんですが、どうしましょう」)
本所の安泊りに一人いるのを見付けたんですが、どうしましょう」
(「いくつぐらいのやつだ」)
「幾つぐらいの奴だ」
(「さあ、にじゅうしちはちでしょうかね。やどのていしゅのはなしじゃあ、し、ごにちまえから)
「さあ、二十七八でしょうかね。宿の亭主の話じゃあ、四、五日前から
(あつさにあたって、しょうばいにもでずにごろごろしているそうです」)
暑さにあたって、商売にも出ずにごろごろしているそうです」
(やさぶろうからきいたおとことはとしごろもまるでちがっているので、はんしちはしつぼうした。)
弥三郎から聞いた男とは年頃もまるで違っているので、半七は失望した。
(ことに、し、ごにちまえからやどにねているというのでは、どうにもせんぎの)
殊に、四、五日前から宿に寝ていると云うのでは、どうにも詮議の
(しようがなかった。)
しようがなかった。
(そいつひとりぎりか、ほかにつれはねえのか」)
そいつ一人ぎりか、ほかに連れはねえのか」
(「もうひとりいるそうですが、そいつはけさはやくからやまのてのほうに)
「もう一人いるそうですが、そいつは今朝早くから山の手の方に
(しょうばいにでたそうです。なんでもそいつはしじゅうぐらいで・・・・・・」)
商売に出たそうです。なんでもそいつは四十ぐらいで……」
(はんぶんきかないうちに、はんしちはてをうった。)
半分聞かないうちに、半七は手を拍(う)った。
(「よし。おれもあとからいくから、おめえはさきへいって、)
「よし。おれもあとから行くから、おめえは先へ行って、
(そいつのかえるのをまっていろ」)
そいつの帰るのを待っていろ」
(まつきちをさきにやって、はんしちはまたかめじゅのうちへいそいでゆくと、)
松吉を先にやって、半七はまた歌女寿(かめじゅ)の家へ急いでゆくと、
(げじょのおむらはきんじょのひとたちといっしょにやきばへまわったというので、)
下女のお村は近所の人達と一緒に焼き場へ廻ったというので、
など
(うちにはしらないおんながふたりすわっていた。かめじゅとけんかをしてかえったという)
家には識らない女が二人坐っていた。歌女寿と喧嘩をして帰ったという
(おとこについて、おむらからくわしいことをききだそうとおもって、)
男について、お村から詳しいことを訊き出そうと思って、
(はんしちはしばらくそこにまっていたが、おむらはなかなかかえってこなかった。)
半七はしばらくそこに待っていたが、お村はなかなか帰って来なかった。
(まちくたびれてげんじのうちへゆくと、これもとむらいのかえりにどこへか)
待ちくたびれて源次の家へゆくと、これも送葬(とむらい)の帰りにどこへか
(まわったとみえて、まだかえってこないとにょうぼうがきのどくそうにいった。)
廻ったとみえて、まだ帰って来ないと女房が気の毒そうに云った。
(にょうぼうをあいてにふたつみっつせけんばなしをしているうちに、やがてうえののかねが)
女房を相手に二つ三つ世間話をしているうちに、やがて上野の鐘が
(よっつ(ごぜんじゅうじ)をついた。)
四ツ(午前十時)を撞いた。
(「おふだうりもやまのてへのぼったんじゃあ、どうせひるすぎで)
「御符(おふだ)売りも山の手へ登ったんじゃあ、どうせ午(ひる)すぎで
(なけりゃあかえるめえ」)
なけりゃあ帰るめえ」
(はんしちはそのあいだにに、さんけんようたしをしてこようとおもって、そうそうにげんじのうちをでた。)
半七はその間に二、三軒用達をして来ようと思って、早々に源次の家を出た。
(それからかけあしでに、さんけんまわってとちゅうでひるめしをくって、)
それから駈け足で二、三軒まわって途中で午飯(ひるめし)を食って、
(おんまやがしのわたしにきたのは、やっつ(ごごにじ)すこしまえ)
御厩河岸(おんまやがし)の渡(わたし)に来たのは、八ツ(午後二時)少し前
(であった。ここでほんじょへわたるふねをまっていると、ひとあしおくれて)
であった。ここで本所へ渡る船を待っていると、一と足おくれて
(このわたしにきたのはすげがさをかぶったしじゅうかっこうのいろのくろいおとこで、)
この渡に来たのは菅笠をかぶった四十格好の色の黒い男で、
(てっこうきゃはんのわらじがけ、くびにちいさいはこを)
手甲脚絆(てっこうきゃはん)の草鞋(わらじ)がけ、頸に小さい箱を
(かけていた。それがちりゅうのおふだうりであることははんしちにも)
かけていた。それが池鯉鮒(ちりゅう)の御符売りであることは半七にも
(すぐにさとられたので、ものになれているかれもおもわずむねをおどらせた。)
すぐに覚られたので、物に馴れている彼も思わず胸をおどらせた。
(まつきちからさっききいたのはこいつにそういない。としごろもやさぶろうからきいた)
松吉から先刻(さっき)訊いたのは此奴に相違ない。年頃も弥三郎から訊いた
(おとこにふごうしている。しかしたしかなしょうこもないのにとつぜんにごようのこえを)
男に符合している。しかし確かな証拠もないのに突然に御用の声を
(かけるわけにもいかない。ともかくもやどへかえるのをつきとめたうえで)
かけるわけにも行かない。ともかくも宿へ帰るのを突き留めた上で
(なんとかせんぎのしようもあろうとおもって、はんしちはなにげないふうをして)
なんとか詮議のしようもあろうと思って、半七は何げない風をして
(ときどきにかれのかさのうちにちゅういのめをおくっていると、おふだうりのおとこも)
時々に彼の笠の内に注意の眼を送っていると、御符売りの男も
(それとさとったらしく、こっちのめをさけるように、わざとやなぎのしたにかくれて、)
それと覚ったらしく、こっちの眼を避けるように、わざと柳の下に隠れて、
(むねをすこしひろげておうぎをつかっていた。)
胸を少しひろげて扇をつかっていた。
(うすくくもったそらはひるからすこしずつはげてきて、こまがたどうのやねも)
うすく陰(くも)った空は午から少しずつ剥げて来て、駒形堂の屋根も
(あかるくなった。そよりともかぜのないひで、あきのあつさはおおかわのみずにも)
明るくなった。そよりとも風のない日で、秋の暑さは大川の水にも
(のこっているらしく、むこうがしからこぎもどしてくるわたしぶねにも、)
残っているらしく、向う河岸から漕ぎもどして来る渡し船にも、
(しろいおうぎやてぬぐいがのりあいのひたいにかざされて、おんなのこのえひがさがあかいかげを)
白い扇や手拭が乗合のひたいにかざされて、女の児の絵日傘が紅い影を
(ふなばたのなみにゆらゆらとうかべていた。)
船端の波にゆらゆらと浮かべていた。
(そのひとむれがこっちのきしへついて、ぞろぞろあがってゆくのを)
その一と群れがこっちの岸へ着いて、ぞろぞろ上がってゆくのを
(まちかねたように、おふだうりはいれかわってのった。)
待ち兼ねたように、御符売りは入れ替わって乗った。
(はんしちもつづいてとびのった。)
半七もつづいて飛び乗った。
(「おうい。でるよう」)
「おうい。出るよう」
(せんどうはおおきいこえでよぶと、こどものてをひいたおかみさんや、)
船頭は大きい声で呼ぶと、小児(こども)の手を曳いたおかみさんや、
(てらまいりらしいおばあさんや、ちゅうげんのさとうぶくろをさげたこぞうや、ご、ろくにんのだんじょが)
寺詣りらしいお婆さんや、中元の砂糖袋をさげた小僧や、五、六人の男女が
(おくればせにどやどやとかけつけてきて、ゆれるふなべりから)
おくれ馳せにどやどやと駈け付けて来て、揺れる船縁(ふなべり)から
(だんだんにのりこんだ。やがてこぎだしたときに、おふだうりはとものほうに)
だんだんに乗り込んだ。やがて漕ぎ出したときに、御符売りは艫(とも)の方に
(のりこんだひとりのおとこをきゅうにみつけだしたらしく、ほかののりあいをかきわけて)
乗り込んだ一人の男を急に見付け出したらしく、ほかの乗合をかきわけて
(かれのむなぐらをひっつかんだ。)
彼の胸倉を引っ摑んだ。








