半七捕物帳 半鐘の怪2
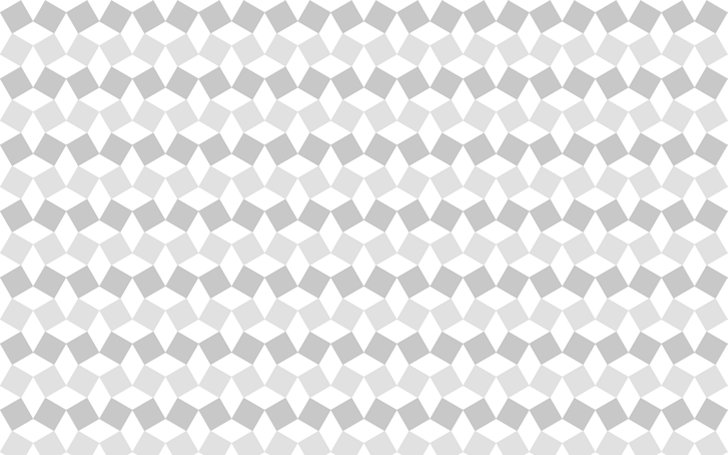
岡本綺堂 半七捕物帳シリーズ 第六話
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(さへえはもうごじゅうぐらいのひとりもので、ふゆになるといつも)
佐兵衛はもう五十ぐらいの独身者(ひとりもの)で、冬になるといつも
(せんきになやんでいるおとこであった。ほかのふたりはでんしちとちょうさくといって、)
疝気(せんき)に悩んでいる男であった。ほかの二人は伝七と長作と云って、
(これもしじゅうをこしたひとりものであった。このさんにんはとうのせきにんしゃであるだけに、)
これも四十を越した独身者であった。この三人は当の責任者であるだけに、
(ちょうやくにんからもきびしくしかられて、まいばんこうたいでひのみばしごを)
町(ちょう)役人からも厳しく叱られて、毎晩交代で火の見梯子を
(みはっていることになった。かれらがよどおしげんじゅうにみはっているあいだは)
見張っていることになった。彼等が夜通し厳重に見張っているあいだは
(べつになんのかわったこともなかったが、すこしゆだんしておうちゃくをきめると、)
別になんの変ったこともなかったが、少し油断して横着をきめると、
(はんしょうはあたかもかれらのらんだをいましめるように、おのずから)
半鐘はあたかもかれらの懶惰(らんだ)を戒めるように、おのずから
(じゃんじゃんなりだした。ちょうやくにんたちあいでけんさしたが、はんしょうには)
じゃんじゃん鳴り出した。町役人立会いで検査したが、半鐘には
(なんのいじょうもなかった。そのしぜんになりだすのはよるにかぎられていた。)
なんの異状もなかった。その自然に鳴り出すのは夜に限られていた。
(ふしぎをしんずることのおおいこのじだいのひとたちにも、まさかはんしょうがしぜんに)
不思議を信ずることの多いこの時代の人達にも、まさか半鐘が自然に
(なりだそうとはおもえなかった。ことにひとがみはっているあいだは)
鳴り出そうとは思えなかった。殊に人が見張っているあいだは
(けっしてならないのによっても、それがなにものかのいたずらであることは)
決して鳴らないのに因(よ)っても、それが何者かの悪戯であることは
(だれにもそうぞうされた。おいおいにふゆぞらにちかづいて、ひというものにたいするおそれが)
誰にも想像された。おいおいに冬空に近づいて、火というものに対する恐れが
(つよくなってきたのにつけこんで、なにものかがひとをおどすつもりでこんないたずらを)
強くなって来たのに付け込んで、何者かが人を嚇すつもりでこんな悪戯を
(するにそういないとおもった。しかもそのいたずらものがはっけんされないので、)
するに相違ないと思った。しかもそのいたずら者が発見されないので、
(しょじんのこころはおちつかなかった。たといにんげんのいたずらにしても、こんなことが)
諸人の心は落ち着かなかった。たとい人間の悪戯にしても、こんな事が
(まいばんつづくのは、やがてほんとうのたいかをよびおこすぜんちょうではないかとも)
毎晩つづくのは、やがてほんとうの大火を喚(よ)び起す前兆ではないかとも
(あやぶまれた。きのはやいものはにごしらえをして、いつでもたちのくことが)
危ぶまれた。気の早いものは荷ごしらえをして、いつでも立ち退くことが
(できるようにようじんしているものもあった。ろうじんをえんぽうのしんるいにあずけるものも)
できるように用心しているものもあった。老人を遠方の親類にあずけるものも
(あった。わらいっぽんをくべたけむりもこのちょうないのひとびとのめにするどくしみて、)
あった。藁一本を炙(く)べた煙りもこの町内の人々の眼に鋭く沁みて、
など
(かれらのとがったしんけいはわかいあしのはのようにふるえがちであった。)
かれらの尖った神経は若い蘆の葉のようにふるえ勝ちであった。
(もうこうなっては、じしんばんやばんたろうのもうろくおやじを)
もうこうなっては、自身番や番太郎の耄碌(もうろく)おやじを
(たよりにしていることはできなくなったので、しごとしはもちろん、ちょうないのわかいものも、)
頼りにしていることは出来なくなったので、仕事師は勿論、町内の若いものも、
(ほとんどそうでで、まいばんこのひのみばしごをちゅうしんにしてひとちょうないをけいかいすることになった。)
殆ど総出で、毎晩この火の見梯子を中心にして一町内を警戒することになった。
(いたずらものもこのものものしいけいかいにおそれたらしく、それからご、ろくにちは)
いたずら者もこの物々しい警戒に恐れたらしく、それから五、六日は
(はんしょうのおとをたてなかった。じゅうがつもおえしきのころからさむいあめが)
半鐘の音を立てなかった。十月もお会式(えしき)の頃から寒い雨が
(びしょびしょふりつづいた。このころははんしょうのおとがしばらくたえたのと、)
びしょびしょ降りつづいた。この頃は半鐘の音がしばらく絶えたのと、
(あめがまいにちふるのとにゆだんして、ちょうないのけいかいもおのずとゆるむと、)
雨が毎日降るのとに油断して、町内の警戒もおのずとゆるむと、
(あたかもそれをまっていたかのように、ふいのわざわいがひとりのおんなのあたまのうえに)
あたかもそれを待っていたかのように、不意の禍がひとりの女の頭の上に
(おちかかってきた。おんなはちょうないのろじのなかにすんでいるおきたというわかいおんなで、)
落ちかかって来た。女は町内の路地のなかに住んでいるお北という若い女で、
(いぜんはやなぎばしでげいこをつとめていたのを、にほんばしあたりの)
以前は柳橋で芸奴(げいこ)を勤めていたのを、日本橋辺の
(おおだなのばんとうにひかされて、いまではここにこぢんまりしたしょうたくを)
大店(おおだな)の番頭に引かされて、今ではここに小ぢんまりした妾宅を
(かまえているのであった。そのひはひるまからだんながきていつつごろ(ごごはちじ)に)
構えているのであった。その日は昼間から旦那が来て五ツ頃(午後八時)に
(かえったので、おきたはそれからきんじょのせんとうへいった。おんなのながゆをすまして)
帰ったので、お北はそれから近所の銭湯へ行った。女の長湯をすまして
(かえってきたのはいつつはんをまわったころで、おうらいのすくないあめのよるにたいていのみせでは)
帰って来たのは五ツ半を廻った頃で、往来のすくない雨の夜に大抵の店では
(おおどをはんぶんぐらいしめていた。あめにはすこしかぜもまじっていた。)
大戸を半分ぐらい閉めていた。雨には少し風もまじっていた。
(ろじへはいろうとすると、おきたのかさがにわかにいしのようにおもくなった。)
路地へはいろうとすると、お北の傘が俄かに石のように重くなった。
(ふしぎにおもってかさをすこしかたむけようとすると、そのとたんにかさがべりべりとさけた。)
不思議に思って傘を少し傾けようとすると、その途端に傘がべりべりと裂けた。
(めにみえないてがどこからかぬっとあらわれて、おきたのみつわのまげを)
眼に見えない手がどこからかぬっと現われて、お北の三つ輪の髷(まげ)を
(ぐいとひっつかんだので、きゃっといってよろけるひょうしに、かのじょは)
ぐいと引っ摑んだので、きゃっと云ってよろける拍子に、彼女は
(どぶいたをふみはずしてたおれた。そのこえをきいてきんじょのひとたちが)
溝板(どぶいた)を踏みはずして倒れた。その声を聞いて近所の人達が
(かけつけたときには、おきたはもうしょうきをうしなっていた。はねあがったどぶいたで)
駈け付けたときには、お北はもう正気を失っていた。跳ねあがった溝板で
(ひばらをつよくつかれたのであった。)
脾腹(ひばら)を強く突かれたのであった。
(うちへかつぎこまれて、かいほうをうけて、おきたはようよういきをふきかえした。)
家へかつぎ込まれて、介抱を受けて、お北はようよう息を吹き返した。
(とうじのことははんぶんむちゅうでよくはきおくしていなかったが、ともかくもかさが)
当時のことは半分夢中でよくは記憶していなかったが、ともかくも傘が
(ふしぜんにおもくなって、そのかさがまたしぜんにさけて、なにものかにあたまを)
不自然に重くなって、その傘がまた自然に裂けて、何者かに頭を
(ひっつかまれたことだけはひとにはなした。ちょうないのさわぎはまたおおきくなった。)
引っ摑まれたことだけは人に話した。町内の騒ぎはまた大きくなった。
(「ちょうないにばけものがでる」)
「町内に化け物が出る」
(こんなうわさがひろがって、おんなこどもはひがくれるとおもてへでないようになった。)
こんな噂がひろがって、女子供は日が暮れると表へ出ないようになった。
(ふだんききなれているうえのやあさくさのいりあいのかねも、まのとおるあいずで)
ふだん聞き慣れている上野や浅草の入相(いりあい)の鐘も、魔の通る合図で
(あるかのようにおんなこどもをおびえさせた。そのさなかにまたひとつのじけんがおこった。)
あるかのように女子供をおびえさせた。その最中にまた一つの事件が起った。




