化学2-5 水が沸騰するしくみ
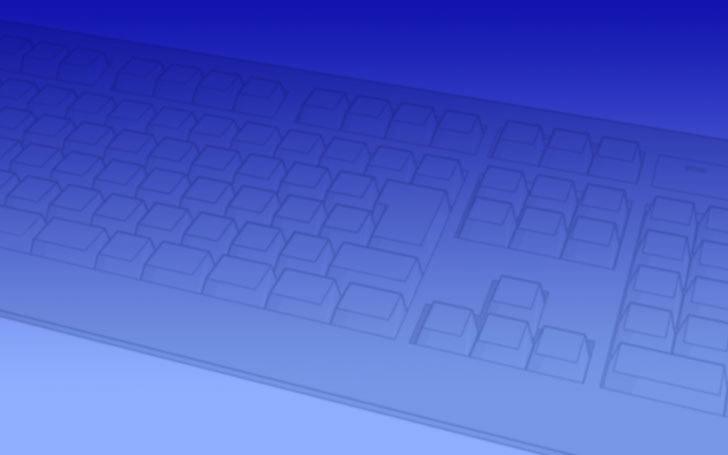
関連タイピング
-
プレイ回数125 長文2288打
-
プレイ回数151 長文1648打
-
プレイ回数212 長文1169打
-
プレイ回数88 長文1818打
-
プレイ回数107 長文1496打
-
プレイ回数93 長文1259打
-
プレイ回数281 長文684打
-
プレイ回数291 長文1143打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(すうぇーでんのてんもんがくしゃあんでるすせるしうすは、)
スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスは、
(みずのひょうてんとふってんをきめようとていあんし、)
水の氷点と沸点を決めようと提案し、
(さいしゅうてきにこおりになるおんどが0ど、ふっとうするおんどが100どとさだめられた。)
最終的に氷になる温度が0℃、沸騰する温度が100℃と定められた。
((とうしょはひょうてんが100ど、ふってんが0どときていしようとていあんしていた。))
(当初は氷点が100℃、沸点が0℃と規定しようと提案していた。)
(みずがどのような「おんど」と「きあつ」でこそうえきそうきそうのじょうたいに)
水がどのような「温度」と「気圧」で固相・液相・気相の状態に
(なるかをあらわしたのは「みずのそうず」、)
なるかを表したのは「水の相図」、
(みずがしょうか、ぎょうけつじょうはつ、ぎょうこゆうかいというへんかをするかんけいを)
水が昇華、凝結・蒸発、凝固・融解という変化をする関係を
(あらわしたのは「みずのそうへんか」。)
表したのは「水の相変化」。
(ふっとうとは、えきちゅうでじょうきほうがせいせいされるげんしょうのことで、)
沸騰とは、液中で蒸気泡が生成される現象のことで、
(きかいこうがくしゃのぬきやましろうがろんぶんであきらかにした。)
機械工学者の抜山四郎が論文で明らかにした。
(なべぞこにそんざいするめにみえないきずにくうきがとりのこされ、)
鍋底に存在する目に見えない傷に空気が取り残され、
(そこにせっしているすいおんが100どをこえると)
底に接している水温が100℃を超えると
(とりのこされたくうきが「ふっとうかく」となり、)
取り残された空気が「沸騰核」となり、
(じょうきほうがせいちょうしてそこからはなれるというしくみだ。)
蒸気泡が成長して底から離れるというしくみだ。





